昨年11月、15周年を記念して刊行された『恋文の技術 新版』。同月9日、物語の舞台である石川県の石川県立図書館さんにて森見登美彦さんのトークイベントが行われました。その一部をお届けします!

トークイベント聞き手:上田敬太郎さん(石川県立図書館員)
構成・写真:ポプラ社編集部
*
――今回はイベント参加者の皆様から募った質問にお答えいただくかたちで進めてまいります。まず一番多かった質問ですが、なぜ能登を舞台に選ばれたのでしょうか。
森見 『恋文の技術』はポプラ社の文芸誌『asta*』で連載されたものですが、当時の舞台は広島でした。妻の出身地が広島で一時よく新幹線で行っていたことがあり、多少土地勘もあったので。でも書籍化にあたり読み直したら、広島だと新幹線一本で気軽に京都と行き来できてしまうな、と。もう少し遠い、程よい距離感の場所はないだろうかと考えるなかで、たまたま旅行した能登のことを思い出したんです。とても印象深かったんですよね。そのときは曇りでちょっと寂しい感じが漂っていて、守田君が行くのはこういうところがいいんじゃなかろうかと結びつきました。
そこで改めて編集者の方々と能登に取材に行きました。恋路海岸など面白そうなスポットがあるので、和倉温泉に泊まって、半島を回ることにしたんですが、先っぽまでは鉄道が通じてないからタクシーを一日借り切って移動したんです。運転手さんには「この人たちは一体何者なんだろう?」と思われていたかもしれませんね。「あそこにいい感じにこんもりした鎮守の森がありますね」「じゃあここで降りましょう」みたいな感じで、観光地ではない妙なところばっかりに行くので(笑)。
――守田君は石川名物の天狗ハムをよく食べていますが、なぜこんな高級ハムを日常的に食べられたのでしょうか。
森見 取材で街中を歩いてたときにたまたま天狗ハムの看板を見かけたんです。天狗のマークがすごく素敵で、他の小説で天狗を出してもいたし、語感もいい。この名前を使いたいがため登場させたんですよね。実際に食べたのはどなたかからの頂き物で、連載終了後でした。『夜は短し歩けよ乙女』で偽電気ブランが出てくるのと同じです。僕の作品では、そういうこともままありまして……それはちょっと申し訳ない。
――守田くんと京都の面々が手紙だけでやり取りする、時間軸が複雑な構成ですが、タイムラインは作成されましたか?
森見 守田くんが手紙を出してる期間に起こったイベントをExcelでカレンダーに入れて矛盾しないように表を作成しました。手紙一通につき必ず A4一枚にプリントアウトして並べ替え、実際のやり取りを確認したりもしましたね。それぞれの章は守田くんの一方的な手紙で一つの話が終わるようになっていますが、同時に別々の相手に向けて手紙を書いているわけです。だからそれぞれの短編として仕上げられた手紙を一通ずつバラバラにして書かれた順に並べ替え、守田くんが実際はどの順番で手紙を書いたかを物理的に把握していったのですが、その作業がものすごく大変で。今なら絶対にこんな面倒なことはやりません(笑)。
――森見さんの本は面白くて読むのが止まりませんが、ご自身もノリノリで書いているのでしょうか。それとも冷静に何度も書き直しているのでしょうか。
森見 面白い文章が書けたときは確かに嬉しいし、『太陽の塔』を書いてたごく初期はノリノリだったかもしれないけれど、その後は結構必死で書いている感じがします。面白い文章やアイディアでもすっと頭に入ってこないと面白さが半減するじゃないですか。だから、できるだけ読者の方に読みやすいようにしたい。文章自体の意味や流れで読み手が混乱しないように、そこはかなり気をつけて何回も書き直しています。
――「O-81」なんて表現、どこで思いつくんですか?
森見 それに関しては、当時働いていた国会図書館の同僚などからも「悪ノリしすぎなのでは?」という厳しいご意見もいただきました(笑)。言い訳をさせてもらうと、デビュー当時、モテない薄汚い男がモタモタしてるっていうお話を書いていたこともあり、そういう男のアホさみたいなものをちゃんと書かなきゃいけないといった気持ちが強く……。「O-81」に関しても、煩悩の数と同じだけ本文に入れてみようなんて思いついてしまい、数えましたからね。一〇八にちょっと足りないから、さらに言わせてみたりして……今となっては若気の至りでお恥ずかしい。反省しております。
――『恋文の技術』続編の構想はありますか。
森見 新版を刊行するにあたり、編集者に続編的なものをとお願いされたんですけど、最終的に作中に登場するコヒブミー教授のスピーチに行きつきました。『恋文の技術』はどれだけ文章的技巧を詰め込めるかにこだわったものなので、もうこれ以上新しくできることがないんですよね。
――また石川を舞台にした小説を書かれませんか?
森見 基本的に、自分のよく知らない土地や旅先を舞台にするのは苦手なんです。『夜行』など旅先を舞台にしたものもあるんですけど、よほど何回も行った場所か気に入ったなにかがないと、小説になる種を絞り出すのが難しくてすごく苦労するんです。どちらかというと自分が日常的に馴染んだところから出てくるものを小説にすることが多い。東京で働いていた頃もあるので『熱帯』では東京がちらりと出てきますが、基本的に京都か奈良か東京しか舞台にしやすいところがない。東京は引き払ってしまった。奈良は書きにくい。だから京都しか残されていない(笑)。だから今後、僕が何らかの事情でこちらに住んだりすることがあれば、あるいは……。
――森見さんの創作意欲の原動力はなんですか。
森見 創作に関しては、中年の危機というか、いま意欲が減退していて、僕自身も知りたいところですが(笑)、僕の場合、何にでも好奇心を持ち色々調べて小説を書くのではなく、自分が毎日暮らすなかで色々妄想したことや面白いなと思ったことをなんとか小説にできないかと考えるタイプなんです。
一方で、それも本当の原動力かというとちょっと違っていて、多分文章だと思うんですよね。こんなお話が書きたいというより前になにか文章が書きたい。読者の方は完成形を読むわけだから、僕がこんな人物を登場させてこんなお話をつくろうと決めて書いてるように思われるかもしれないですが、そうじゃないんですよ。飛び石みたいにポンポンポンとこんなことが書けたらいいなというイメージがある。書いていくにつれて書けないこともあるし、新たなものが出てくることもあって、それをなんとか繋げていく。最初に完璧な図面があってそれを言葉で表現するというのとは違うんですよね。『恋文の技術』もストーリー的にはそれほど大きなものはないのだけれど、文章の面白さを追及していくなかで、文章の向こう側に守田君やその他の人たちの姿が見えてくるってところが面白くて。なにもないところに文章を書くことでなにかの世界が立ち上がっていくという小説の不思議さと面白さ――多分それが僕の原動力なのだと思います。
――森見さんの摩訶不思議な発想はどこから来るのでしょう。アイディアはどんなときに思いつくのですか?
森見 発想というのはどうして思いついたか自分でもわからないものなのですが、書きたくなるものってあるんですよ。たとえば今日、京都からサンダーバードでこちらに向かってたんですけど、車窓から一瞬不思議な池が見えたんです。遺跡みたいな橋が途中まで突き出していて、廃墟のようになっている。その池の中に島もあって――そういうのを見てなにか書けそうだなと思うんです。それ単体ではお話にならないんですけど、そういうものを色々見つけてそれに反応するっていうのが、 小説家としては大事なのかもしれないですね。
――ご自分で一番好きな作品は何ですか?
森見 あくまで今、暫定的な一番ということでいえば……『ペンギン・ハイウェイ』でしょうか。子どもの頃のことを書いているから、自分の原点に近いことになるので、やはり特別な感じはありますよね。『太陽の塔』も間違いなく原点なんですけど、『ペンギン・ハイウェイ』はもう一つの、個人的な原点のように思います。
――では、一番読んでほしい作品は何ですか。
森見 読んでほしい? 難しいですね……。自分としてはこれを読んでほしいというのはあまり思いつかないなあ。ちなみにどれだと思われます?
――今日のイベント的には『恋文の技術』でしょうか(笑)。
森見 それはそうですね(笑)。でもたしかに『恋文の技術』は一番が好きな作品ですと言われる頻度がすごく高いんですよ。どうしても『夜は短し歩けよ乙女』やメディアミックスされた『有頂天家族』なんかが目立つんですが、『恋文の技術』も必ず一定数一番好きと言ってくださる方がいて、とてもありがたいなと思います。文章勝負というか、文章で笑わせたり、書簡体ならではのトリックだったりといった、小説でなければ達成できない世界ということでいえば『恋文の技術』が一番純粋なかたちかもしれない。書簡体であることに意味があるので、映像や舞台で表現するのは相当大変だし、そもそも良さが伝えられるのか……。そういう点でも小説以外で触れることができないですから、恋文が一番とおっしゃる方には「私は森見登美彦の作品をうわべだけじゃなくてちゃんと読んでますよ」というのを示す意味でもあげてくる渋い人、というイメージがありますね。僕も「おっ」と思いますね。「『恋文の技術』ですか、おわかりですね」って(笑)。
*
■ 著者プロフィール
森見登美彦(もりみ・とみひこ)
1979年奈良県生まれ。2003年『太陽の塔』で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。07年『夜は短し歩けよ乙女』で第20回山本周五郎賞を、10年『ペンギン・ハイウェイ』で第31回日本SF大賞を受賞。他の著書に、「有頂天家族」シリーズ、『熱帯』『シャーロック・ホームズの凱旋』など多数。
■ 書誌情報
『恋文の技術 新版』(ポプラ文庫)本体790円(税別)
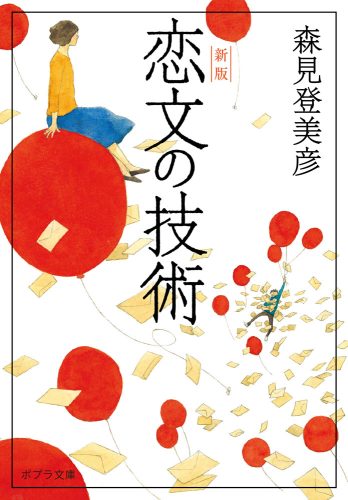
京都から遠く離れた能登の実験所に飛ばされた大学院生・守田一郎。文通修行と称して京都の仲間や家族らに手紙を書きまくるのだが、本当に想いを伝えたい相手には書けなくて――。森見節満載の傑作書簡体小説。








