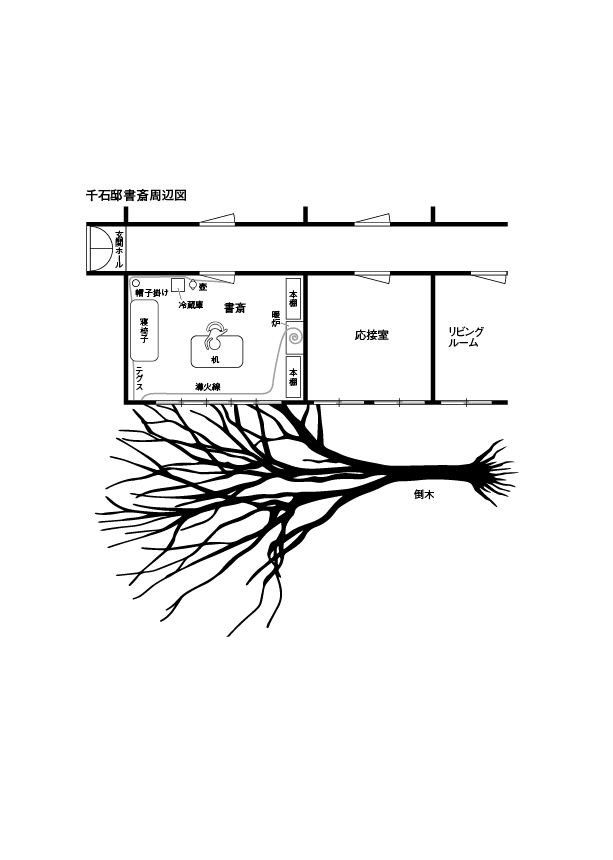
*
再び、リビングルームである。
今度は警察側の人数が多い。名和警部が二人の刑事を従えている。事件解決に備えての増員なのか、やけにがっしりした強面の二人である。
木島達がリビングに入って行くと、関係者の三人はソファで退屈そうにしていた。執事の辻村の姿だけ見えない。名和警部の合図で刑事の一人が奥へ向かい、厨房から辻村を連れてくる。手を拭きながら出てきた辻村は怪訝そうな顔をしていた。
ソファに座った千石登一郎が、
「そろそろ帰っても構わないだろうか、いつまでも拘束される謂われはないと思うのだが」
不機嫌さを隠すことなくそう云った。
その隣の千石正継も、
「もう話すべきことは話しました。いい加減解放してくださいよ」
辻村もその言葉に、立ったままでうなずいた。千石里奈子は目を伏せて、楚々とした佇まいで座っている。先ほど暗黒魔道士みたいなぐろぐろとした一面を見せたのは気にする様子もない。
勒恩寺は、そんな関係者達を見渡して宣言する。
「間もなくです。もう事件は終息します。皆さんもお帰りいただけますよ。ただし、犯人を除いてですが」
場が、ざわりと浮き足だった空気になる。登一郎が不満げに、
「まさか、我々の中に犯人がいるとでも云い出すんじゃないだろうな」
「そのまさかですよ。犯人はこの中にいます。俺の論理がそう告げている」
姿勢のよい立ち姿でそう告げた勒恩寺は、関係者、いや、今のひと言で容疑者候補に格上げされた四人を再び見渡す。
「では、始めましょう」
と、勒恩寺は、例によって空いているソファにどっかりと座って、話の口火を切った。木島はその斜め後方に目立たないように控える。長いソファには登一郎と正継が並んで座っている。彼らと九十度ズレた一人がけのソファには里奈子。辻村は、里奈子と正継の中間位置、やや後ろに立っている。名和警部と刑事二人が、出入り口を塞ぐように待機していた。
「では、まずマッチ棒について考えてみましょうか」
と、勒恩寺は悠然と足を組むと、少し改まった口調で云う。
「皆さん覚えていますね、執事の辻村さんが書斎の扉にマッチ棒を立てかけた件です。あの証言で、書斎の扉は一晩中ずっと開いていないということになっています。謂わばマッチ棒による簡易封印処置です。あの証言が本当かどうかは、この事件において重要なファクターになっています。今からこれを検証してみようと思います」
「お言葉ですが、私は嘘など申しておりません。本当にマッチ棒を置きました」
おずおずと主張する辻村を、勒恩寺は片手を突き出して制すると、
「それをこれから立証するのですよ。まず、辻村さんが犯人だった場合を考えてみましょうか。ああ、断っておきますが、もちろん辻村さんが犯人だと疑っているわけではありませんよ。すべての可能性について言及しておこうというだけの話ですので誤解なきように」
と、注釈を入れておいて勒恩寺は、
「辻村さんが犯人だったのなら、マッチ棒を置いたと自ら証言するでしょうか。先ほど木島くんが廊下で云っていたことを思い出してください。犯人が後で脱出したという仮説です。外部犯が書斎に潜んでいて中から鍵をかけており、廊下で呼びかける皆さんが引き上げたのを見計らってから、こっそりと抜け出して逃亡した。実にまっとうな仮説ですね。ところがマッチ棒による簡易封印処置のせいで、この仮説は成り立たなくなってしまいました。ただ、もし辻村さんが犯人ならば、外部から暗殺者が侵入して後からそっと脱出したとする木島仮説は大変に魅力的なはずです。警察がこの仮説に飛びついてくれれば、これ以上のことはないでしょう。犯人にとっては、殺人者が外部から入り込んだと誤解してくれるのはとても都合がいい。自分から疑いを逸らすことができる。これで判りますね。辻村さんが犯人ならば、マッチ棒を置いたなどと云い出す道理がないのです。犯人には何のメリットもない簡易封印処置の話を自分から持ち出すのは矛盾している。それが嘘だろうと本当だろうと、どちらのケースでもです。辻村さんが犯人ならば、余計なことは云わないはずでしょう」
と、勒恩寺は辻村のほうを向きながら断言した。
「次に、辻村さんが犯人でない場合です。犯人ではないのにマッチ棒を置いたという嘘をつくことはあり得るのか、という話になります。誰かを庇って嘘をつくケース、誰かに罪をなすりつけるために嘘をつくケース、犯人が誰か知っていて警察にそれとなく教えるために嘘をつくケース、犯人が誰かは知らないが何か得があって嘘をつくケース。と様々な可能性が挙げられますが、しかし、マッチ棒による簡易封印処置は何をもたらしたでしょうか。特定の何者かの容疑が濃くなったか、逆に特定の誰かが容疑圏内から外れたか、警察は何らかの結論に達したか、辻村さんに何かメリットがあったか。いずれの場合も、答えはノーです。マッチ棒による簡易封印処置は、これまでに何の結果も出してはいない。誰も庇っていないし誰かに罪を被せることに成功してもいないし、犯人が誰か仄めかしている様子もなければ辻村さんだけが何らかのメリットを享受したわけでもない。実は何も起きていないのです。せいぜい犯人がどうやって書斎から逃走したのか不明であるという不可解な状況が生じたくらいですが、しかしそんな状況を生むためだけにマッチ棒を置いたなどという嘘をつく必要があるとも思えません。嘘が小さすぎるからです。もし誰かを庇う目的があったのならば、庭に怪しい二人組の男が潜んでいるのを見かけた、というような具体性のある嘘をつけばいいだけの話です。誰かを陥れるのが目的ならば、その人物が書斎に忍び込むのを目撃したと、ストレートな嘘をつけばいい。不可解な状況を印象づけるのが目的ならば、謎の怪人物の集団が書斎の扉の前にしゃがみ込んで何かの細工をしているのを見た、とでも大げさな嘘をつけばいいのです。マッチ棒を置いただけという嘘は、嘘にしてはあまりにも矮小です。決定力不足で、結果をひとつも出してはいない。そんな小さな嘘をつく必然性など、辻村さんが犯人でない場合にはどこにもないと云わざるを得ない。何らかの理由で嘘をつくのならば、もっと大きな効果をもたらす嘘をつけばいいはずなのです」
長広舌を奮った勒恩寺は、ここで一旦言葉を切り、一同の様子を確かめる。皆、複雑な面持ちで探偵の台詞に聞き入っている。勒恩寺は続けて、
「辻村さんが犯人である場合でも、犯人でない場合でも、結局マッチ棒の件では嘘は云っていない。ここまでの話でそう推定できるのはご理解いただけましたね。よって私は、マッチ棒による簡易封印処置は本物だったと結論づけたいと思います。辻村さんの主張には嘘はないと判断できるのですから」
「信じていただけて幸いです」
と、辻村は恭しく一礼した。しかし勒恩寺は素っ気なく、
「お礼には及びません。探偵にとって真実を明らかにするのは当然の行為ですから」
そこに横から正継が、
「しかし、回りくどいですね。随分長々と喋るじゃないですか。探偵っていうのはこんなにくどい話し方をするものなんですかね」
にやにやと揶揄するように云った。登一郎も苛立ったように、
「そうだ、こんなまだるっこしい話に付き合わなくてはならんのか。早く解放してほしいのに」
不機嫌そうに不満を述べる。里奈子も、伏し目がちの視線をちらりと上げて不服そうだ。
勒恩寺はぼさぼさの髪を軽く掻き上げて、
「ご辛抱いただきます。皆さんに納得していただくにはどうしても丁寧に話を進めなくてはなりませんので」
しれっとした態度で云う。そして口調を改めて、
「さて、マッチ棒による簡易封印処置は本物だったと判明しました。ここから導き出される事実は何でしょうか。まずは犯行時間です。皆さんの証言によると、夕食後にコーヒーを飲んでいると庭で大きな音がした、ということでしたね。桜の木が倒れる音です。慌てて義範氏の籠もる書斎に駆けつけても、ドアは開かなかった。皆さんは義範氏が出て来ないと諦めてリビングに戻った。こうでしたね」
「そうだな、その通りだ」
と、登一郎が肯定する。
「廊下から立ち去る際、辻村さんはマッチ棒を仕掛けた。ここから次の朝、事件が発覚するまで簡易封印処置は利いています。義範氏本人はもちろん、他の誰も書斎には出入りしていないことが判ります。窓の鍵にはここしばらく手を触れた様子がなかったことから、そこから出入りしなかったのも確実ですので。これでおおよその犯行時間が割り出せます。犯行があったのは封印の前、つまり桜が倒れる前のことです。そのお陰で犯人の行動がだいたい読めるようになりました。七時に夕食が始まる前です。夕食前、登一郎さんと里奈子さんは二階の自室にいたとそれぞれ証言しています。正継さんはリビングに、そして辻村さんは厨房にいた。ただしお互いに証人はいません。つまり全員にアリバイがない。犯人にはここで動く時間がありました」
勒恩寺はそう云って、一同の反応を待つような間を置いた。誰も何も云わなかったので、勒恩寺は続ける。
「そこで犯人の行動をシミュレートしてみましょう。犯人は夕食前、七時より前に書斎で義範氏を射殺した。そう推定できます。その後は夕食で皆さんと一緒にいましたし、そして桜の木が倒れ、それからは簡易封印処置が利いていますからもちろん現場に入ることができません。従って七時前に殺害したのは間違いない事実でしょう。義範氏が一人で書斎に籠もっているところを訪問して、隙を狙って側頭部を一発、というわけですね。そして、現場の書斎で仕掛けを作ります。この仕掛けについては関係者の皆さんは当然ご存じですよね、警部殿」
問われて名和警部は、入り口のところで立ったままうなずき、
「ああ、事情聴取の時に説明した。こんな仕掛けがあったか心当たりはないか、と一通り聞いた」
「心当たりのあったかたはいましたか」
「いないね」
警部の返事に、関係者達も揃ってうなずいた。勒恩寺はそれを確認してから、
「結構です。仕掛けは警部殿から説明があったように、ピンセットとテグス糸で遠隔操作して鍵をかける仕組みでした。そして暖炉の中には渦巻き状の導火線と爆竹の仕掛けもありました。犯人はこの二種の細工をして書斎を出ました。義範氏が事前に『邪魔をするな誰も近づくな』と命じていたので、暴君の命令に逆らって書斎のドアを開けようとする人はいないだろうことは、容易に予測が立ちます。だから犯人は鍵をかけずに書斎を立ち去ることができたわけです。庭の外壁からピンセットと導火線を屋内に潜り込ませる作業は、犯行の前に済ませておいたのでしょうね。外側から、外れる壁板の一部を嵌め込んで、そこに糸と導火線を挟んでおけば、書斎の中からそれを回収することができます。仕掛けはそれを使って作ったわけです。ただし犯人は、犯行の直後にはテグスの仕掛けは作動させませんでした。それは恐らく、まだ外が明るかったからではないでしょうか。テグスを引っぱってあまり長い時間、外壁にへばりついてもたもたしていたら、誰かに見られる危険がある。この時、リビングには正継さん、二階には登一郎さんと里奈子さんがいました。特に里奈子さんは外の桜を眺めていたと証言しています。辻村さんもいつ厨房から出て来るか判らない。これでは誰かに目撃されるリスクが高すぎます。仕掛けを作動させるのは暗くなってから、闇に紛れて作業するほうがよさそうです。どのみち導火線に火を点けるのは外壁からやるわけですから、その時にテグスの仕掛けも作動させれば二度手間にならず無駄がありません。だから犯人は、夕食前にはまだ仕掛けは使わなかったのです。こうして犯行を終え、仕掛けの準備は整いました」
勒恩寺はそこで一度言葉を切って、元々乱れきっている頭髪を片手でざっくりと掻き上げた。しかしブレイクは一瞬。すぐに話を再開し、
「さあ、犯人はこの後どうするつもりだったのか。テグスとピンセット、そして導火線と爆竹。これらの遺留品から犯人が何をする気だったのか、だいたいの予測はつきますね。では犯人の行動のシミュレートを続けましょう」
と、勒恩寺は続ける。
「事前に泊まり込みで来いと義範氏の指令があったこと、そして夕食が七時から始まる習慣だったのも犯人は織り込み済みだったのでしょう。ですから恐らく夕食後、皆さんがバラけた直後に行動する予定だったのだろうと思われます。あまり時間が経ちすぎると、実際の犯行時刻と見せかけの犯行時刻がかけ離れていることが露見してしまう。死体の状況から、死亡推定時刻が割り出されますからね。ズレは少ないに越したことはない。長く見積もってもせいぜい一時間。これくらいが限界でしょう。それ以上の時間経過があると、死亡時刻と発見時刻とで齟齬が大きくなってしまう。警察が誤差の範疇として見てくれるだろう一時間程度のズレに抑えておきたかった。早いほうがいい。それには夕食直後です。夕食後、各自別行動になったら、犯人はこっそり庭に出て書斎の外側の壁に取り付く。そして例の仕掛けを作動させるわけです。この時にはもう辺りも暗くなって目撃される恐れもなくなります。テグスを引っぱって書斎のドアに鍵をかける。ピンセットとテグスを回収したら導火線に火を点ける。わざわざ導火線を使っているのは、着火する用途の他には考えられません。渦巻きの中心部に爆竹がセットされていることからも、導火線は火を点けるために用意したことは明白ですね。そして、導火線を渦巻き状にして長くしていることから、少し時間を稼いだ後に爆発音を一発轟かせようと画策していたことも間違いないでしょう。犯人は火を点けた後、急いで、かつ何喰わぬ顔で屋敷の中に戻り、他の人達と合流するつもりだったのでしょうね。そこで渦巻きが燃えきって爆竹が爆ぜます。パンっと一発、大きな音。屋敷の中の人達は皆、びっくりすることでしょう。そうなったら皆さん、どう行動しますか」
「もちろん、様子を見に参ります」
辻村が折り目正しく云い、勒恩寺はうなずき返すと、
「そう、一同揃って音のしたほうへ駆けつけるでしょうね。書斎です。しかしそこのドアはロックされています。さっき犯人がテグスの仕掛けで鍵をかけたからです。さあ、次に皆さんはどうしますか」
勒恩寺の問いに、正継が首を捻りながら、
「とりあえずドアを叩く、でしょうね。開かないんだったら呼びかけるしかない、昨日の晩にやったのと同じです。伯父さん、大丈夫か、今の音は何だ、と声をかけるでしょう」
「そう、しかし中からは何の反応もありません。当然ですね、書斎には義範氏の射殺死体があるだけですから。ドアが開かない返事もない、とすると次はどうしますか」
勒恩寺が尋ね、今度は登一郎が、
「庭へ回るだろうな。窓から中の様子を見るしかない」
「そうです、それで皆さんは机に突っ伏して亡くなっている義範氏を発見するわけです。机は血塗れ、手には拳銃。窓の外からそんな光景が見えたら、里奈子さん、あなたならばどう行動しますか」
名指しされた里奈子はびくりと少しだけ顔を上げて、消え入りそうに小さな声で、
「もちろん警察に通報します。あと、救急車も呼ぶでしょうね、まだ間に合うかもしれませんから」
「そうなると警察がやって来ますね。しかし現場は内側から鍵がかかっている。密閉状態です。中へは入れない。捜査の陣頭指揮を執る警部殿ならこの場合、どうするでしょう」
聞かれて名和警部は、面白くもなさそうな顔つきで、
「無理にでも押し入るだろうな。ドアを壊すか窓ガラスを叩き割るか、とにかく現場に入らなくては始まらん」
「そうやって警官隊が発見するのは片手に銃を握って事切れている義範氏の姿だけです。鍵は窓もドアも内側からかかっている。仕掛けは犯人によってとうに回収済みだ。この状況下で警察は、義範氏の死をどう判断するだろうね、木島くん」
「当然、自殺だと思うでしょうね。部屋が密閉されていては犯人の逃げ場がありませんから」
と、木島は最前の書斎での議論を思い出して答える。勒恩寺は満足そうに、
「その通り。誰もいない密室に頭を撃ち抜いた死体が一体。銃も故人の秘蔵のもの。これは自殺と判断するのがもっとも妥当でしょう。そして、それこそが犯人の目的であったのだろうと、私は思うのです。他殺を自殺に見せかける。これこそ殺人現場を密室にする目的の王道です。事件が自殺として処理されれば、犯人にとってこれ以上の成果はないでしょう。警察に追及されることもなければ、逮捕される危険も絶対にない。ややこしい仕掛けを作る面倒のリターンとしてはお釣りが来る。犯人の最終目的はそこにあったのですよ」
その言葉に、名和警部は渋い顔で、
「なるほど、現場を密閉してしまう理由としては充分に説得力があるな。我々も騙されていたかもしれん」
勒恩寺は、警部にうなずき返してから話題を変えて、
「では、ここで導火線に注目してみましょう。導火線が渦巻き状に何度も巻いてあったのは、時間を稼ぐためだと先ほど申し上げました。これは、誰がどう見てもそう判断できますね。書斎の内部で銃の発射音に似た音を立てたいだけならば、まっすぐで短い導火線でこと足りますから。わざわざ手間をかけて渦巻きにしたのは、少しでも爆竹の破裂を遅らせようとした意図があったと考える他にありません。木島くん、稼げた時間は?」
突然尋ねられて、焦りながらも木島は、
「二分三十秒です」
「そう、先ほど実験して、それだけの時間が稼げることが判明しました。この二分半で犯人は何をするつもりだったのでしょうか。推論を組み立てる必要もありませんね、答えは明白。アリバイを作る予定だったのでしょう。私がもし犯人ならば、導火線に火を点けたら大急ぎで屋敷の中に戻って、厨房にいる辻村さんにでも声をかけるでしょうね。『すみませんが、一杯やりたいんで氷はありませんか』などと何喰わぬ顔で尋ねます。『氷ならばこちらにございます』『やあ、ありがとう』とか会話をしている時に、パンっと爆竹が弾ける。屋内にいる人は誰しもそれが銃声だと思い込むでしょうね。直後に義範氏の射殺死体が発見されるわけですから、ああ、あの時の破裂音は銃の音だったのか、と誰もが納得することでしょう。いずれにせよ、この時辻村さんと厨房にいた人物にはアリバイが成立します。元々自殺に見せかけるのが犯人の目的です。このアリバイ工作はあくまでも補強だと思われます。それでも自分が犯人ではない、もしくは犯人など存在しないと印象づけるのには大いに役に立つことでしょう。屋敷の中にいた全員にアリバイができれば、これが最も望ましい形ですね。そうすれば事件は自殺だと強調されますから」
と、勒恩寺は一同を見回してから、
「そして逆に考えれば、犯人がこの屋敷の中にいた人物だということも判ります。導火線の渦巻きで稼げる時間は二分半。それでアリバイを作れるのは、ごく近くの範囲にいた者だけだからです。もし外部の者が犯人ならば、元々導火線の仕掛けなど作らなかったでしょう。二分半ではアリバイを作ることなどできないからです。屋敷の中の人を書斎に呼び寄せるためだけの爆発音ならば、これも渦巻きなどにせず短い導火線でこと足ります。もしどうしてもアリバイを確保したいのだったら、外部犯にとっては二分半では足りません。その際は導火線などではなく、何らかの機械的仕掛けで爆発音が鳴るように細工をしたことでしょう。例えばタイマーを一時間後にセットして、この土地を離れる。そして自分の地元などに戻って馴染みの店にでも顔を出す。店主や常連客にアリバイ証人になってもらうためですね。千石邸で射殺事件が起きた頃、自分は地元にいたと主張するわけです。しかし普通はそこまで面倒なことはしないでしょうね。どのみち自殺に見せかけるのが主目的なのですから、アリバイ作りはあくまでも補助的な役割しかありません」
と、勒恩寺はシャープな口調で続けて、
「ところが今回の犯人はアリバイの保険もあったほうがいいと判断しました。自殺に見せかけるにしても、アリバイも確保したほうがより安心だとでも思ったのでしょうか。ただ、いずれにせよ稼げる時間は二分半です。移動できる距離は限られている。当然、他の町などへは行く余裕などなく、せいぜい外の壁から屋敷の中に戻って来るのが精一杯でしょう。そして、このことが犯人が内部にいる人物であることを示しています。二分半の移動でアリバイを確保できるのは昨夜この屋敷の中にいた者のみ、つまりこの四人だけなのですから」
勒恩寺はそう云うと、容疑者候補の四名の顔を見回す。辻村、登一郎、正継、里奈子。四人は一様に、硬い表情で勒恩寺の言葉に耳を傾けている。
「私は最初に、犯人はこの中にいると云いました。その意味が判ってもらえましたね。ついでに云うのなら、犯人は単独犯で共犯者がいないことも判明しました。共犯者がいれば、導火線の渦巻きなどを作るよりも手軽に、互いのアリバイを証言し合えますから。二人で口裏を合わせればいいだけなのです。導火線に渦巻きの仕掛けを施したのは、犯人が単独だった証に他なりません」
と、勒恩寺はまとまりのない頭髪をまた、ざっくりと掻き上げてから、
「失礼、少し脱線しましたね、話を戻しましょう。先ほど私は犯人がどう行動して、事件をどう誘導するつもりだったかシミュレートしてみました。犯人はテグスを用いて現場を密室にし、導火線と爆竹を使うことで時間も誤認させようとしました。すべては事件を自殺に見せかけるために。しかし現実は予定通りにはいかなかった。思わぬアクシデントが起こり、計画は瓦解してしまいました。犯人がまったく予期していなかったアクシデント、それが何か判るね、木島くん」
またしても突然、話を振られた木島は一瞬頭がついていけずに混乱した。
ええっと、アクシデントって、何だっけ? 何が起きたんだ?
即答できない木島に、名和警部が助け船を出してくれて、
「桜の木だな、あれが倒れた」
勒恩寺は警部のフォローに感謝の笑みを返すと、
「そうです、桜の木です。強風のせいであれが根元からひっくり返った。これは犯人にとって不慮の出来事だったに違いありません。天気予報で強風になるのが判っていても、まさかそれで庭の桜が倒れると予測できる人物などいようはずがないからです。当然あれは人為的なものではありません。もし暴風に紛れて計画的に桜を倒そうと目論んだのならば、大変な手間がかかったはずです。重機を庭に入れて、引っぱるか根元を掘り起こすかするしかありません。いくら何でもそんな大掛かりなことを企む犯人がいるとも思えない。山の中の一軒家でもあるまいし、重機を出動させてそんな大工事を始めたら近隣の人の目に留まるのは必定。そもそも屋敷の中にいる犯人以外の人達がすぐに見つけて騒ぎになることでしょう。大風の夕刻、突如として頼んでもいないクレーン車が庭に入って来たら、皆が仰天するに違いありませんから。だから桜の木が倒れたのは、犯人の計画外のことだったと判断できます。あくまでも自然のアクシデントだったのです」
と、いきなりここで勒恩寺はひょいっとこちらを向いて、
「ああ、そういえば木島くんとここへ到着した時、現場は桜の木が倒れている庭ではないと俺は云ったね。あれは、木が倒れた原因が人為的なものではないと判断したからだ。何者かの計画で起きたことでないのなら、それは事故だ。もし桜の木の近くで死者が発見されたとしても、それは事故死か、もしくは倒木で損壊された死体でしかない。そんな現場ならば一課の刑事さん達の手に余るはずもない。我々特専課に招集がかかる事案ではないね。だから俺は、現場はそっちじゃないと木島くんを止めたんだ」
と、勒恩寺はひとしきり木島に説明してから、一同に向き直って、
「おっと、また脱線しました、失敬、話を戻しましょう。桜の木が倒れたことで犯人の計画にズレが生じた、というところまで話しましたね。導火線の爆竹を鳴らす予定より早く、皆が書斎の前に駆けつけてしまった。犯人は内心で、マズいと焦ったことでしょう。まだ書斎の中にはテグスやら何やら仕掛けが丸々残っている。あんな物が見つかったら自殺に見せかける当初の計画が成り立たなくなってしまう。ところが、書斎のドアは開きませんでした。犯人はほっとすると同時に、大いに驚いたはずです。まだテグスの仕掛けを作動していないのにドアが開かなくなっているのですから、これはびっくりしたことでしょう。他のかたは当然、義範氏が中からロックしているのだと思ったでしょうが、犯人だけはまだ鍵がかかっていないことを知っています。自分が義範氏を射殺してドアを出る際、ロックはしていないことを犯人自身が一番よく知っていましたから。しかしなぜか扉は開かない。犯人は大いに困惑したことでしょう」
「どうして扉は開かなかったんだ?」
入り口の前で刑事達を従えた名和警部が、不思議そうに尋ねた。正継も首を傾げて、
「あの時、鍵はかかっていましたよ、探偵さん。僕もてっきり中から伯父貴がロックしたものだと思い込んでいたけど、今の話だとそうじゃないみたいだ。だとすると誰が鍵をかけたんですか」
里奈子も無言で、不可解そうに首を捻り、登一郎も口を開いて、
「我々三人でドアを押したんだ。間違いなく鍵はかかっていたぞ。どうやったら鍵がかかるというんだね」
「その件に関しては後で詳しくお話ししましょう。その前に、犯人側の視点での話を続けさせてください」
と、勒恩寺は皆の疑義を抑えておいて、
「とにかく犯人は不可思議に思ったことでしょう。死体と仕掛けが発見されなかったのには安心したけれど、内心ひやひやしていたことでしょうね。そして、皆さんはドアの前から解散しました。義範氏がいつもの癇癪で返事もしないで閉じ籠もっていると思ったのでしたね。倒れた木で被害が出なかったのならば放っておこうと判断した。ただ、犯人は慌てて行動を開始したでしょう。こんなアクシデントが起きた以上、テグスなどの仕掛けは速やかに回収しないといけない。自殺に見えなくなってしまいますからね。扉が開かないので、当然犯人は庭に回ります。例の外壁の隙間から、テグスを引っぱって回収するつもりです。ただ、庭に出た犯人はそこで愕然としたことでしょう。理由は、判るね、木島くん」
今度はすぐに判った。木島はうなずいて、
「はい、桜の枝ですね、倒れた枝が外の壁にのしかかっていたんです。仕掛けの先端を隠してある場所を含めて、外壁全体が枝で覆われてしまっていた。それで犯人は仕掛けを操作することができなくなってしまったんです」
木島の答えに満足したようで、勒恩寺は大きく首肯して、
「そう、刑事さんが五人がかりで三十分かけてようやく撤去できたくらい、枝は大量に絡みついて外壁を覆っていた。暗い中、犯人一人の力で外壁に辿り着くのは到底不可能でしょう。これではテグスの回収もできないし、導火線に火を点けることもできない。犯人はさらに焦ったことでしょう。いっそ密室は諦め、窓ガラスを破って中に入ろうか。そう思っても窓にも枝が密集していて、それが邪魔で近づくことができません。どうしたわけか扉が開かず、窓にも近寄れない。仕掛けを施した外壁も枝に阻まれて辿り着けそうもない。書斎の中にはテグスとピンセット、導火線などの仕掛けが残ったまま。だのに書斎に入る手立てがない。犯人は進退窮まってしまった」
木島は、まるで自分のことのように焦った気分になってきた。
「それで、犯人はどうしたんだね」
名和警部に尋ねられ、勒恩寺は軽く肩をすくめた。
「どうにもできませんね。扉が開かないので書斎には手出しができません。他の皆は、暴風関連のニュース特番など見ながら呑気に夜を過ごしています。犯人はその中に交じりながら、内心うろたえていたことでしょう。しかし打てる手は何もありません。そのまま夜が更け、一泊することになった。犯人は寝つけなかったことでしょうね。恐らく、何度か書斎のドアの前へこっそり出向いて行って、開くかどうか試してみたりもしたのでしょう。あの仕掛けが残っているのは非常に具合が悪い。自殺に見せかけるという当初の目論見が潰えてしまう。しかしドアは開かず、どうにもできずに手をこまねいていることしかできなかった。そのうち朝になり、死体の発見に至ったという次第です。こうして警部殿とそのご一行は、射殺死体と、ドアに奇妙奇天烈な細工を施した現場を見ることになったわけです」
と、勒恩寺はここで大きく息を継ぎ、深呼吸してから続けた。
「と、これで不運な犯人の物語は終わりです。昨夜は一睡もできなかったでしょうし、今日も一日やきもきして過ごしたことだと思います。自殺に見せかけるという計画は頓挫し、今はこうして探偵に追い込まれようとしている。天網恢々、悪いことはできませんね。という教訓のお話でした」
「いや、それより扉はどうしたんですか。昨日の夜、誰がどうやってロックしたのか、それがまだ判っていませんよ」
木島が主張すると、名和警部も同感だったらしく小刻みにうなずいている。お供の刑事二人も怪訝そうな顔だ。
「ああ、それが残っていたね。では、実際にやってみましょう。皆さん、移動です、ただちに書斎前に集合してください」
そう云い置いて勒恩寺は立ち上がると、すたすたと歩いて行ってしまう。名和警部達が出口を固めているのをすり抜けて、廊下へと出て行く。
一同は一瞬顔を見合わせた後、慌てて探偵の後を追う。木島もわたわたとそれに従った。奇矯な探偵の行動についていくのに精一杯である。
そして全員が廊下に集結した。書斎の扉の前だ。さっきの事情聴取の時より廊下は渋滞している。ごつい刑事が二人増えたせいでもある。というより、人数が多いこと自体が混雑の原因だった。勒恩寺に木島、辻村、登一郎、正継と里奈子。そして名和警部と二人の刑事。これだけ立っていればぎゅうぎゅうにもなる。
そんな押しくら饅頭の中で、勒恩寺が集団から一歩前へ出て語り出す。
「さて、昨夜この扉はどうして開かなかったのか。その原因は犯人の仕掛けが作動したからではないことは、警部殿始め捜査官の皆さんはよくご存じですね。ピンセットとテグスの細工は手つかずで残っていましたから。では、犯人がもう一セット、鍵をロックする仕掛けを作っていたとしたらどうでしょう。もしくは犯人ではない別の何者かが、仕掛けを作っていたとしたら? いや、それはいくら何でもナンセンスというものでしょうね。殺人現場で、犯人でもない誰かが現場を密室にする仕掛けを作っていたと考えるのはさすがに無理があります。犯人自身がもう一セット仕掛けたというのも無理筋です。そんなことをする意味などありませんからね。だいいち鍵のサムターンはピンセット一本で塞がれてしまっています。別の仕掛けを施す余地など、物理的にいってもないわけですから。ああ、木島くん、ちょっと扉を開けてみてくれたまえ」
「はあ」
人混みを縫ってドアの前へ進むと、木島は云われた通りにした。ノブを握り、ドアを押す。何の抵抗もなく扉は開いた。
「開きましたけど」
と、木島は見た通りのことを報告した。何だか間の抜けた報告だと思いながら。
「結構、では閉めてくれ」
勒恩寺の指示通り、木島は扉を閉める。何をやっているのだろうか、これは。
「では警部殿、さっきの件、お願いします」
勒恩寺に云われて、名和警部は刑事の一人に目顔で合図を送る。刑事は携帯電話を取り出し、誰かと通話する。
「始めてくれ」
と、その直後に、どこか遠くのほうから、
「せーのっ」
と、大人数のかけ声が聞こえた。ヤケクソみたいな胴間声だった。「せーのっ」? 何だ、今のは? 外のほうから聞こえてきたぞ。疑問に思う木島に、勒恩寺が命じる。
「よし、もう一度だ、開けてみてくれ」
「はあ」
なぜ同じことをするのか、訳が判らない。不承不承ノブを握り、木島はドアを押して開こうとする。
扉は開かなかった。
一枚板の重厚なドアはびくともしない。
えっ? これは何だ。中に誰かいたっけ、と木島は思わず首を傾げてしまう。中で誰かがロックをかけたのか? いや、さっき開けた時、確かに誰もいなかったはずだ。
改めて、扉を押してみる。やはり開かない。どうしたんだ、これは?
「開きません」
と、木島はまた見た通りの報告をした。唖然としているせいで、今度は間が抜けているとは感じなかった。
そこへ登一郎が近づいてきて、
「開かないはずはないだろう、何もしていないんだから」
半ば強引に割って入ってきた。登一郎はドアノブを掴み、力を入れてからびっくりした顔になる。びくともしない感触を自ら味わったのだろう。
「どれどれ、僕にもやらせてみてよ」
と、正継が、野次馬みたいな顔でやってきて扉に取り付く。そして、
「本当だ、開かない。昨日と同じだ」
ぽかんとしたように云った。里奈子と辻村は少し離れた場所で、不思議そうに目をしばたたかせている。
木島は思わず、勒恩寺のほうへ詰め寄るように近寄って、
「どういうことですか、これは。なぜ開かなくなったんですか。ほんのさっきは開いたばかりなのに」
一瞬で開かなくなる扉。これはミステリーである。
勒恩寺は、にやりと不敵に笑って。
「なあに、簡単なことだよ、木島くん。仕掛けではないと先ほど云っただろう。つまりドアは、人為的要因で開かなくなったのではないんだ。誰かが何かをやったせいでこうなったのではない。では人為的でなければ何だ。他に考えられる可能性はひとつしかないだろう。自然現象だよ。それしかないはずだ。そこで俺は考えた。昨日の夜、犯人の計画に反して扉を開かなくした自然現象は何か。昨日の夜だけに起こった特徴的な現象だ。ほら、思い出すまでもない。あったじゃないか、大きな自然現象が」
「風だっ」
と、正継が叫ぶ。さっきまでの人を小馬鹿にしたみたいなにやにや笑いではなく、珍しく真顔だった。
「ニュース特番にもなっていた。昨晩は関東じゅうに強風が吹き荒れていた」
正継の言葉を引き継いで、登一郎もびっくりしたように、
「ああ、そうか、風か」
茫然とつぶやく。
勒恩寺はそんな周囲の反応にお構いなくごく冷静に、
「皆さんのおっしゃる通り、風です。他には特別な要因は見つかっていません。風と特定しても構わないと私は判断しました」
と、一同をぐるりと見渡して勒恩寺は、
「数十年に一度という規模の暴風、それが昨日は吹いていました。日没の頃から夜明けまで、猛烈な風が続いていましたね。犯人が殺害に手を染めた頃はまだ夕刻で、風はさほど強くはなかった。しかしその後、風はどんどん強烈になっていったことでしょう」
と、勒恩寺は続ける。
「強風の最初のピークで桜の木が倒れました。その方向を思い出してください。木は、西側へ頭を向けて倒れていました。つまりこの近辺では、風は東から西へと吹いていたことになります。当然、木だけではなくこの屋敷にも風圧がかかります。東側の壁には強烈な風が吹きつけたはずです。そりせいで、斜めにひずんだのですよ、この館自体が。この屋敷は古い木造です。失礼ながらあちこちボロくてガタがきている様子です。そこへ数十年に一度クラスの強風がモロにぶち当たってきた。ほんの少しとはいえ、ひずんでもおかしくはないでしょう。特にここは西側の一階です。歪みの影響が一番強く出る地点といえるでしょう。さらにドアの枠は風向きとはほぼ垂直の角度ですね。真横からの歪みの力を強く受けたドア枠は斜めにひずみます。長方形が平行四辺形になるように、です。木造なので金属のドア枠と違って歪みやすいということもあったのでしょう」
と、勒恩寺は、両掌を平行にして見せてから、それを左右別々の方向へズラす動きをする。
「ドア板は厚い一枚板です。これが、ドア枠が斜めに歪んだせいで挟まる形になった。ひずんだドア枠に嵌まり込んだドア板は、それで固定されてしまったのですね。そう、ドアには鍵などかかっていなかったのです。犯人の仕掛けはまだ作動していなかったのですから、そう考える他にないでしょう。ドア板は単に、歪んだドア枠に押さえつけられていただけ。その押さえる力が猛烈な風のため強く、人一人が押したくらいではびくともしなくなったわけです。これが密室の正体です。一時的にドアが動かなくなったのは自然現象でしかなかった。そして朝になって風がやめば、当然ドア枠の歪みも解消されて、ドア板にかかる力もなくなった。そうしてドアは再び自由に開くようになったのでした」
何とまあ、中途半端な密室は強風が原因だったのか。木島は唖然として言葉も出なかった。自然現象だから気まぐれで、人の意志が介在していないからこその中途半端具合だったわけだ。そういえば最初に外からこの屋敷を観察した時、建物が古くてコントのセットみたいにひしゃげて潰れそうだと、木島は感じたものだった。あの第一印象は正しかったのだ。
びっくりして何も云えないでいる木島と同様、他の面々も驚いたのか呆れたのか茫然とするのみである。
勒恩寺はそんな中、一人だけなおも饒舌に、
「だから警部殿に頼んで強風を再現してみた。東の壁に暴風と同じような圧力を加えてもらったのです。刑事さん十数人がかりで壁を押してもらいましてね。見事、建物の歪みが再現できたでしょう」
さっきの「せーのっ」のかけ声は、その時の気合いの声だったのか、と、やっと木島はそれに思い当たった。それにしても、十数人の刑事が揃いも揃って必死の形相で壁の一面を押しているのは、シュールな光景というか何というか。
「探偵、もういいだろう」
名和警部に声をかけられ、勒恩寺はこともなげに、
「あ、もちろんもう結構です。実験は終わりましたので」
それを聞いて、さっきの刑事が再び電話をかける。
「おい、もういいぞ、押すの終了」
今の長話の間もずっと押し続けていたのか、刑事達は。いやはや、ご苦労なことである。「さあ、これで事件は解決です。密室の正体も判明しました。もう解明していない謎はないはず。探偵の出番もここまでのようですね」
と、勒恩寺は至って呑気な調子で云った。名和警部が慌ててそれを止めて、
「いやいや、ちょっと待て、まだ犯人が判っておらん。ここまで来て犯人を指摘しないのは画竜点睛を欠くというものだぞ」
そうだ、事件の概要は完全に解けたが、しかし犯人が誰かは判明していない。木島が見ると、勒恩寺は照れたように笑って、乱れきった髪を手櫛でざっくりと掻き上げながら、
「ああ、これは失礼しました。重要なことはもう話し終えたので、つい失念してしまいまして」
犯人指摘がどうでもいいことみたいな云い草で勒恩寺は、
「では、犯人が誰か、お話ししましょう。犯人は内部にいると、私は推定しましたね。それについては先ほどお話しした通りです。執事の辻村さん、千石登一郎さん、千石正継さん、千石里奈子さん、と容疑者の候補はこの四人です」
名を挙げられた四人は、緊張した面持ちでそれぞれ顔色を窺い合った。勒恩寺は彼らとは対照的に、至ってのどかな顔つきで、
「犯人は風という不可抗力によって、書斎に仕掛けたテグスなどの細工を回収できなくて困ってしまった、というのが先ほどまでのお話でしたね。そんなものが現場に残っていたら、自殺に見せかけるという当初の目的が頓挫するどころか、物証が丸ごと警察の手に渡ってしまいます。犯人はどうにかして仕掛けを回収したいと考えたはずです。しかし、残念ながらそれは叶いませんでした」
と、勒恩寺はそこで一度、容疑者候補達の顔を見渡して、
「ではまず、発見者でもある辻村さんのことを考えてみましょう。辻村さんは今日の早朝、風が止んで歪みから解き放たれた扉を開き事件を発見。警察に通報しました。しかし辻村さんはテグスや導火線の仕掛けには手をつけていません。犯人ならば何をおいても回収したいはずの証拠品を隠そうともしていない。辻村さんが犯人ならば、行動に大きな矛盾が生じますね。辻村さんは現場の仕掛けに目もくれずに、そのまま警察に引き渡しています。犯人ならばこんな行動を取るはずがないのです。誰も起きてきていない時間帯に現場に自分一人きり。犯人ならば確実にこの好機を逃さず、証拠品を回収するはずです。従って辻村さんが犯人ではないことは明白でしょう」
勒恩寺の言葉に、辻村は恭しく一礼して応えた。
「次に、ピンセットとテグスの仕掛けですが、あれはなかなか精巧にできていました。実地検証してみて、私も思わずエキサイトしてしまったほどです。あれは一朝一夕にできるものではありません。必ず何度か実演し、試行錯誤を繰り返して完成したはずです。書斎の床の隅に隙間があることや、外壁にあちこち外れやすくなっている箇所があることも、この屋敷にある程度詳しくなければ知る機会がありません。その点、里奈子さんは、この屋敷に来るのは今回が二度目だと証言しています。この屋敷の構造を熟知したり、テグスの仕掛けのリハーサルをしたりする時間が取れたとは到底思えません。もちろん証言は嘘で、誰にも知られず忍び込むことは可能です。しかし住み込みの辻村さんがいて、主の義範氏も週に何度か都心の会社に行く以外は書斎で仕事をしていることが多いといいます。彼らの目を盗んでリハーサルをするのはまず不可能と云っていいでしょう。だから里奈子さんも犯人候補からは外れることになります」
里奈子は俯いたままだが、ほっとしたように薄い笑みを唇に浮かべた。勒恩寺は続ける。
「残りは登一郎さんと正継さんです。お二人は伯父さんに借金の申し込みのためよくこの屋敷に出入りしていたそうですね。義範氏に意地悪をされて、書斎に置き去りにされたこともよくあったとおっしゃっていました。お二人ならば、仕掛けのリハーサルをする時間は充分に取れそうです。では、どちらが犯人なのでしょうか」
と、勒恩寺は混雑する廊下で、犯人候補の二人を交互に見やって、
「そこで、凶器の拳銃について考えてみましょう。あの銃は被害者当人の机の引き出しにしまってあったそうですね。では犯行前、銃を引き出しから取り出したのは誰でしょうか。被害者の衣服に争った様子がないことから、被害者が取り出したところを犯人が強引に奪い取ったということはなさそうです。言葉巧みに被害者を誘導し、被害者自身が取り出したのを犯人が受け取ったというのにも無理があります。なぜなら犯人は手袋をしていた可能性が極めて高いからです。犯人は凶器の銃に自分の指紋がつかないように、極力注意していたことでしょう。せっかく自殺に見せかける計画なのに、犯人の指紋が銃から見つかったらすべては台無しです。だから犯人は犯行時、手袋をしていたに違いありません。この季節に屋内で手袋を嵌めているのはとても不自然です。だからその犯人の手で、ちょっとそれを貸してください、と云われて被害者が不審に思わないはずがないのです。不審に感じた被害者が銃をすんなり渡すとは思えない。ですから、銃を引き出しから取り出したのは、被害者ではないと考えるべきだと思います。となると、銃を取ったのは自然と犯人だという結論に達しますね」
と、勒恩寺は続ける。
「ではどのタイミングで取り出したのか。この犯行は、書斎に籠もった被害者を犯人が訪ねて行き、話している途中でいきなり発砲した、という段取りだったはずです。その時、被害者は机に向かっていて、犯人はその右側にさりげなく近づいたことでしょう。そういう動きでなければ、被害者の姿勢が発見時のあの姿にはなりませんから。それに、後で自殺に見せかけるためにも、そうした動きをするのが最も効果的です。ところが銃は、被害者の座る机のまん中の引き出しに入っていた。これでは被害者の腹部が邪魔で、こっそり抜き取るのは不可能です。だからといって『これからあなたを射殺しますんで、ちょっと場所を空けて銃を取らせてください』と云うわけにもいかない。だとすると、銃を取り出したのは犯行の直前だとは考えられないのです。被害者が机に座っている状態で、銃を手にするのは不可能。となると、被害者がまだ籠もる前、犯行の少し前に取り出したと考える他はない。被害者が不在の時に犯人がこっそり忍び込んで、そっと銃を抜き取ったに違いないのです。とはいえ、何日も前にくすねたりしたら、義範氏が無くなっているのに気付いて騒ぎになることでしょう。ですから犯人は昨日ここへ来て、義範氏が帰宅する前の時間を狙って忍び込んだと考えるしかありません。そこで昨日皆さんがここへ到着した順番を思い出していただきたい。まず里奈子さんが来ました。この時、義範氏は不在でした。次に登一郎さんが来た。そして義範氏が帰宅します。大層不機嫌な様子で、誰も近づけるな声もかけるな夕食も要らん、と辻村さんに命じて、義範氏は書斎に閉じ籠もってしまいます。それとほぼ同時に正継さんが到着。さあ、どうでしょう。これで判りますね。正継さんには銃を持ち出す機会がなかったのです。来た時にはもう、義範氏が書斎に籠もっていたのですから」
勒恩寺の言葉に、正継は唇を尖らせて口笛を吹くマネをした。
「これで残ったのは登一郎さんしかいません。他の三人は除外されました。ですから登一郎さん、あなたが犯人ですね」
勒恩寺の静かな口調の指摘に、登一郎は目を泳がせながら、
「バカな、どこにそんな証拠がある。これは名誉毀損だぞ」
言葉では否定しても、額には大粒の汗が浮いている。勒恩寺は涼しい顔で、
「証拠ですか。では銃を撃った時、あなたはサイレンサーを使いませんでしたか。本当の犯行時刻を知られたくない今回のようなケースでは、銃声が響くのは避けたいはずです。以前に伯父さんに銃を見せびらかされた時、型番を覚えておいて合致する消音器を入手したのではないですか。銃本体より消音器だけのほうが入手しやすいでしょうしね。それとも小型のクッションでも当てがって銃声を殺したか。いずれにしても、あなたの荷物の中に隠してあるのではないでしょうか。返り血の付着した消音器が。それにテグスの予備や導火線の余り。そんな物も荷物の底に隠していませんか。事件は自殺として処理される予定だったから、私物の中まで改められるとは想定していなかったでしょうからね。昨日からここに缶詰状態だったあなたには、それらを処分する時間はなかったでしょうし」
勒恩寺が云い終わるやいなや、名和警部が視線だけで合図を送った。それを受けて刑事の一人が足音も立てずに、素早くその場を離れて行った。
登一郎はそれで観念したのか、がっくりと頽れて膝をついた。肩を落として俯いてしまう。こうなっては罪を認めたのも同然だった。
「動機はさっき云い争いになっていた金銭絡みでしょうが、俺はそんなことには興味がない。テグスの手動密室装置、あっちのほうがはるかに気になる。登一郎さん、あなた、どうしてあの手口を使おうとしたんですか。何か特別な理由があるんですか」
勒恩寺が砕けた口調に戻って問いかけても、登一郎は下を向いたまま絞り出すような声で、
「別に理由なんてない。あんたが云ったように、自殺に見えるようにしたかっただけだ。それにはドアの鍵が内側からかかっていればいいと思った。昔読んだ推理小説に、そんな糸を使う仕掛けが出てきた。それを思い出して真似しただけだ」
「何か、密室に対する思い入れや美学があったわけではないんですね」
「ないよ、そんなもの。くそっ、ケチな伯父が金を出し渋らなかったら、こんなことにはならなかったのに、畜生っ」
登一郎は顔も上げず、膝に拳を打ちつけている。
それを見て勒恩寺は、とたんにすべての関心を失ってしまったかのように、
「警部殿、これで本当に特専課の仕事は終わりです。後の処理はお任せしますんで、帰っていいですね」
勝手極まる云い分に、名和警部は少し不満そうに、
「ああ、構わんよ」
仕方がない勝手にしろ、というふうにうなずいた。うまくすれば手柄を一課のものにできるかもしれないし、実際、勒恩寺と木島がいても、もうすることがない。
「行こう、木島くん」
と、勒恩寺は惜しげも未練もない様子で、さっさと歩き出す。振り返ろうともしない。
木島は慌てて、残っている人達にお辞儀をする。
登一郞は膝をついてうなだれたままで、正継と里奈子は探偵が立ち去ったほうをぽかんと見ている。辻村執事だけが丁寧に一礼を返してくれた。
挨拶を終えた木島は、勒恩寺を追って大急ぎで玄関に向かう。
玄関ホールを出たところで勒恩寺に追いついた。陽は大きく傾き、もう夕暮れ時になろうとしている。
歩きながら勒恩寺は口を開いた。
「今回の収穫は、本物の犯人が作った糸と針の密室の仕掛けが動くところを見られたことだけだったな」
と、あまり面白くもなさそうに云う。
「しかしね、欲を云えば、あんな即物的な理由ではなく、犯人が何らかの美意識を持って作った密室を見たかった。密室殺人はロマンだ。探偵にとっては陽炎のごとく遠く淡い永遠の憧れだ。今回は叶わなかったが、いつか出会いたい。木島くん、俺はそう願っているんだよ。犯人が、犯罪に対する美学と形而上的な探究心のみで創造した芸術のような密室。そういうものに出会いたいんだ。感性豊かな美の結晶のごとき密室を。それを夢見てやまない。この名探偵勒恩寺公親と対決するに相応しい名犯人と相見えることを。ただ、今回は密室になった原因も人為的なものでなかったから興が薄いな。単なる自然現象だったのもポイントが低い。屋敷が斜めに傾いでできた密室だから、今回の一件を名付けるとしたら、さしずめ斜め屋敷の犯ざ」
最後まで云わせないよう木島は泡を食って、
「いつかきっと出会えますよ、その夢のような美しい密室に」
お為ごかしを云ってみると、勒恩寺は存外素直に、
「そうか、木島くんにも判るか、俺のロマンが。ありがとう。うん、君は見どころがあるな、随伴官として優秀なのかもしれないね」
誉められても、あまり嬉しくない。
二人並んで、門のほうへと向かった。
隣を歩く自称名探偵を横目で見ながら、木島は思う。
願わくば、この珍妙な部署から早く抜け出したい、と。やっぱり自分には向いているとは思えない。まっとうな公務員としてデスクワークに邁進したい。
それだけを願う木島だった。








