ビストロの朝食 〜おいしいパンとよい酒があれば〜
まだ暗い部屋に、トイピアノの音が響きわたった。
どこか気の抜けるようなその音は、有悟が設定した、仕事用電話の着信音だ。
手探りで電話を探すが、手の届く範囲にはないらしい。薄目を開けると、カーテンの隙間から床に夏の終わりの朝日がこぼれ落ちているのが見えた。窓の外からは賑やかな物音が聞こえる。モー、モーと、のどかな牛の鳴き声、金属がぶつかるカチャカチャした音、遠くに響くひとの話し声。牧場の朝は、どうやらもうとっくにはじまっているらしい。壁掛け時計を思わず二度見し、しゃっきり目が醒めた。
午前五時。予約の電話にしては早すぎる。少なくとも常識的な時間じゃない。
軽く咳払いして声を整えてから、ようやく見つけた電話の通話ボタンを押す。
「お待たせいたしました。ビストロつくしです」
僕はまだ寝ぼけているらしかった。
電話の向こうからも、モー、モーと、牛のような声が聞こえる。
声の主の男性は、たぶん僕と同じか少し上の年頃、三、四十代といったところだろう。牛の声のシンクロに困惑したせいか、早口にまくし立てているのが日本語じゃないと気づいたのは、やや経ってからだった。
国際電話ならば、こんな時間なのも頷ける。そうとわかると、時折聞こえるゴー、ゴーという音の前に、小さなユの音が聞き取れた。有悟? とたずねているのだとわかった。
言葉は不思議だ。慣れた言葉でもいつもと音や形が少し違うだけで、わからなくなる。
有悟がいるはずの、隣のベッドはもぬけの殻だった。
タオルケットと毛布はめくれあがったまま、バスルームにも姿はなく、牧場の宿舎の小さな部屋には他に居場所もない。ベッドの上を跳ねるように移動してカーテンを開けると、列をなして移動する牛の向こうに、有悟の丸い背中が見えた。
電話の相手に待ってくれ、と片言の英語で言ってみたが、一向に伝わらない。相手はいっそう熱心に話し出し、抑揚の強い言葉がまるで音楽のように響いた。
フランス語だろうか。歌うみたいに聞こえるせいか、声に感情がそのまま溶け込んで、耳から心にまで沁みてくるようだった。感じる憂いや哀しさが勝手な憶測なのか正しいのかもわからないが、切実さが伝わってきて、有悟に早くつながなくてはと焦る。
たびたび繰り返されるモーモーという音が、牛たちの歩みに重なる。
互いに言葉が通じないと十分わかったはずなのに、相手は歩み寄ることもせず、容赦なくあちらの言葉でまくし立ててくる。対処に困り、こちらも日本語で、あとで、と大きく言うと、ぴたりと黙った。気持ちを込めれば、言葉を超えて伝わるものなのかもしれない。
そんなところに感心しながら、僕は手早くシャツを羽織って、有悟を追いかけた。
牛舎に足を踏み入れると、一角では今まさに、仔牛が生まれようとしていた。牧場主の菅江さん、息子の文広さん、その奥さんの穂波さんが、緊張した面持ちで介助している。
張り詰めた空気の中にひとり、場違いなのがいる。背中を丸めて柵に頰杖をつく白シャツのずんぐりむっくりした有悟の後ろ姿は、動物園で飼い慣らされたシロクマのようだ。
国際電話だと告げて電話を渡すと、眠たげな瞳で僕を見あげ、ボンジュー? と語尾に疑問符をつけたような話し方で、のっそり牛舎を出て行った。
「颯真くん、出産に立ち会うの、はじめて? 今日はちょっと大変な子なの」
穂波さんが、マットのようなものを手に、近寄ってきた。菅江さんが、母牛の苦しそうな息遣いに合わせて、牛の体に付けた器具のようなものを動かす。
「あれは助産器。逆子だから、酪農家が手伝うの」
赤ちゃんの体はもう半分ほどが見えていた。細い足にロープをかけ、菅江さんと文広さんが母牛と息遣いを合わせて介助し、少しずつお産が進んでいく。牛とひと、互いの言葉がわからなくても、たしかに通じ合っている。
あうんの呼吸で穂波さんがマットを敷くと、透明なゼリー状の羊膜に包まれた赤ちゃんが生まれ落ちた。小さな口に菅江さんが指を突っ込み、羊水を吐かせる。母牛は、産み落としたばかりの我が子を、長い舌で、いとおしそうに舐めた。時間をかけて、全身をくまなく舐めるその姿に、ほぼ部外者の僕ですら、胸にぐっと込みあげてくるものがある。
いつの間にか隣に、有悟が戻ってきていた。
有悟も感動しているのか、目を真っ赤にして、袖口で目を擦すりながら、母牛の初乳を飲む赤ちゃん牛の姿を、じっと見つめていた。
一歩外に出ると、昨日と同じはずの牧場の朝が、昨日よりもずっとかがやいているように思えて、土と緑のにおいに満ちた空気を、僕は胸いっぱいに吸い込んだ。
有悟は、ひとことで言うなら、無謀な男だ。
度胸があるのかもしれない。あるいは、なにも考えていないのかもしれない。これまでの長い付き合いで、僕はたぶん、後者だと睨んでいる。
かつて料理修業に単身フランスに乗り込んだ時も、ボンジュールとメルシーしか知らなかったらしい。いまだに単語をつぎはぎしたインチキフランス語ばかりで、きちんとは話せないようだ。専門用語だけで修業できるものなのか不思議だが、欠点を補って余りあるなにかが有悟にはあるのかもしれない。
なにがしかの才能に恵まれているのは、たしかだ。
有悟は、おいしいものを見つけ出し、つくり出すことに長けている。それを料理の才と呼ぶべきか、食いしん坊の才と呼ぶべきかは悩むところだが。
あのシロクマめいた丸っこい体軀と、クリームパンのようなぷくぷくのふたつの手から、驚くほど繊細な料理が生み出されるさまは、人体の神秘と言っていいだろう。
ただし天は二物を与えなかった。他が著しくぽんこつなのだ。
──おいしい食材を、おいしい時期に、おいしく料理してお出しする。
有悟のシンプルな理想を形にした、旅するビストロを手伝いはじめて、数年になる。
小さいが選り抜きの厨房設備を整えたキッチンカーと、ブルーグレーと生成色の小さなサーカステントを詰め込んだトラックで、町から町へ、旬を追って旅をする。
昔の船乗りは、波止場ごとに妻がいたとか聞くが、有悟の場合もそれに似て、行く先々に心を寄せる食べ物がある。有悟の脳内の地図と暦は、おいしいもので描かれているに違いなくて、その羅針盤はおそらく胃袋にある。
僕の仕事は航海士に近い。嵐に突っ込む無謀な船長から、船と積み荷を守るのだ。
キッチンカーの鍵をぶらつかせながら、有悟が歩いてきた。
瞼がまだ腫れぼったいのは、さきほどの仔牛のためか、あるいは寝不足のためだろうか。
「颯真、朝食のパン買いに行こう」
「まだ六時にもなってないだろ、開いてる店なんてあるかな」
「ほんの少し足を延ばせばあるよ。パン・ド・カンパーニュがおいしい店だけど、前に行った時は、バゲットとか、ブリオッシュもあったはず。今日みたいな朝にはとびきりおいしい朝ごはんが必要だ」
今日に限らず、そんなことばかり言っているのだが。
「まあ、近いなら」
「大丈夫、すぐ近くだよ。ビストロ式の最高の朝ごはんが食べたかったら、一にも二にも、おいしいパン屋さんが大切だからね。すぐだよ、片道ほんの一時間だ」
僕の意見など聞くつもりもないらしく、有悟はパン講釈を続けて車へ歩き出す。
「焼きたてのフランスパンやクロワッサンがあるといいな。フランスパンは、細めのバゲットでも食べやすいシャンピニオンでも構わないけど、できれば皮がパリパリと繊細な音を立てて歌うようなのがいいんだ」
半ば諦めて、僕は車の鍵を受け取り、運転席に乗り込んだ。
夏とはいえ、緑の濃い高原の朝に吹く風はまだ涼しい。窓を開けたまま走れば、心地いい風が車の中を爽やかに吹き抜ける。
「あのさ颯真、今度店を出す場所、おまつりの近くなんてどうだろう? ひとがいっぱい集まる場所なら、いろんな出逢いが生まれるし、お客さまも増えるんじゃないかな」
「構わないけど、そういうのは気が散るから嫌だって、前に言ってたろ?」
以前イベントへ出店した時には、つくる方も食べる方も落ち着けないと駄々をこね、以来イベントには重ならないように、営業場所や日時を計画してきた。急にどうしたというのだろう。
「ええと、でも、いろんなひとに話を聞けたら、刺激にもなるし面白いかと思うんだ」
「有悟は接客せず、厨房にずっとこもってるのに?」
「そ、それじゃ私も、接客を」
「なにか隠してる?」
有悟が口ごもる。無茶を言い出すのはいつものことだが、明らかになにかがおかしい。
「言えないことなのか?」
「いや、そうじゃないけど、どこから話したらいいのか」
「結論から話して」
「わかった。ひとを捜したいんだ」
もっと突拍子もない話が飛び出すかと思っていた僕は、いささか拍子抜けした。ひとを捜すなんて、有悟がこれまで持ち掛けてきた話に比べたら、ずっとまともな部類に思える。
以前はおいしいタマネギを求めて北海道から佐賀、淡路島へ車を走らせたこともあったし、潮目に乗って北上する魚を追い、太平洋側と日本海側の海沿いをジグザグに横断したことも、ジビエが獲れたと聞けば、どこにいようとすっ飛んでいくこともあった。
有悟の無謀な考えを現実と摺り合わせて、その都度、営業場所の確保や手続き、コストの調整や宿泊場所など、折り合いをつけるのが僕の役割だった。有悟の思い付きで動いた時は食材が確保できずに、定番メニューが出せない苦労もした。天才と天災は予想がつかない点でちょっと似ているのだ。
それらの過去の経験に比べればひと捜しなど、造作もないことのように感じた。
「どんなひと?」
「すごく世話になったひとなんだ。今はどこにいるかわからないんだけど、日本にいることはたしかで」
「ちょ、ちょっと待って。どこにいるか、わからないのか?」
「うん。わからない」
話がきな臭くなってきた。
「そのひとの連絡先は? 電話番号とか、メールとか」
「知らないんだ」
「じゃあどうやっていつも連絡を取ってたんだ?」
「使いのひとが伝言を持って来てくれて」
いつの時代の話だ。ミラー越しの有悟は、冗談を言っているようにはもちろん見えない。いつもどおり大真面目に、僕の常識から外れたにわかには信じがたい話をしている。
「そのひとを、どうやって捜すつもりなんだ?」
「だからさ、ひとの集まるところに行って、話を聞いてまわったら、噂話を聞けるかもしれないだろう?」
「全国津々浦々をしらみつぶしに? 何百年かかるんだよ。写真とか似顔絵で指名手配でもしないかぎり、情報だって集まらないだろ」
「似顔絵も指名手配も無理だよ。会ったこともないし、名前も知らない」
「……なんだって?」
「翁って呼んでた。それしか知らない」
「他に知ってることはないのか?」
「もちろんある。重大な情報だよ。私の料理を気に入ってくれた。特にナス料理を褒めてくれたんだ」
有悟は満面の笑みを見せたが、僕は頭を抱えるしかない。
翁というからには男性、それもおそらく年配のひとなのだろうが、ナスが好きな爺さんというだけで、なぜ捜せると、捜そうと思えるのか。有悟の思考回路がまるで理解できない。無謀にもほどがある。
「悪いが、捜すならひとりでやってくれ。無理だとしか思えない。僕は手伝わないよ。行き当たりばったりで仕入れもろくにできずに、定番メニューが出せないような営業はもうやりたくない」
「ええっ、颯真が手伝ってくれなけりゃ、見つけられる気がしないよ」
「僕が手伝っても手伝わなくても、見つからないだろうよ」
「颯真なら見つけてくれると思うんだよ。いつも、私が話すことを魔法みたいに叶えてくれるじゃないか」
魔法なんかじゃない。血と汗と涙をグジュグジュにじませた、僕の努力の賜物だ。
「無理と言ったら無理だ」
有悟の気の向くままに食材を追って営業した一年目は、ひどいものだった。胃袋に忠実な旅路は無秩序な動きも多く、仕入れ先もその都度開拓しながらで苦労したし、燃料費だって無駄に嵩んだ。二年目からは、有悟の希望を聞きつつ大まかなルートを僕が選定して、効率的にまわれるよう、努力を重ねてきた。店が存続しているのは、ひとえに僕のおかげだろう。
なんの手掛かりもないひと捜しのために、無謀な旅に逆戻りするのは店の営業にとってはデメリット以外のなにものでもない。どうしてそれが有悟にはわからないのだろう。
有悟の頭の中は、いつも料理が優先する。
牧場に戻った時はあれほどしょんぼりと車を降りたのに、厨房に一歩踏み入れると、もう鼻歌を歌っていた。体をゆすりながら朝食の準備をする有悟の姿に、僕は軽くため息をついた。
*
気持ちのよい風の吹き抜ける木陰のテーブルに白いクロスを敷くと、木もれ日がレース模様の影を落とした。
ポットたっぷりのコーヒーと搾りたてミルク、人数分のカフェオレボウルを食卓に並べる。採れたての夏野菜サラダ、店の定番ペーストのポークリエット、ふわふわのスフレオムレツを添えれば、なかなか充実した朝食になる。主役はたっぷりのパンだ。
ブリオッシュにクロワッサン、シャンピニオン、四等分したバゲット。といっても輪切りではなく、縦半分と真ん中で割った四等分に、自家製ジャムの瓶を添える。
支度の整った食卓に菅江さん一家をお招きして、朝ごはんがはじまる。
「このオムレツふわっふわね。有悟くん、あとでつくり方教えてくれない?」
「颯真くんの淹い れるコーヒー、うちの牛乳にすごく合うな。これなんの豆?」
「このポークなんとかって上等なコンビーフみたいなの、おかわりしていいんかね」
穂波さんがオムレツをつつき、文広さんがあっという間にカフェオレを飲み干し、菅江さんが新聞を片手にリエットにフォークを突き立てる。ひと息ついたところで、有悟はバゲットとバターナイフを手に、立ちあがった。
「では、みなさま。パリ仕込みの、ビストロ式最高の朝ごはんを伝授いたしましょう。まず、パンにバターとお好みのジャムを塗るんです。タルティーヌといいます」
話しながら有悟は、四つ割りのバゲットに菅江牧場のおいしいバターを塗る。びっくりするような量の厚塗りに、菅江さんと文広さんは度肝を抜かれたようだ。
有悟はさらに、あんずジャムを分厚く塗り重ねた。旅暮らしのよいところは、あちこちでおいしいものに出逢えることだ。果樹園を通るたびに増える自家製ジャムは、ブラックベリーとラズベリー、桃にあんずにマーマレード。今朝つくったばかりのミルクジャムもある。
「ジャムまで塗ったら、お手元のカフェオレに、じゃぼん」
有悟が着席と同時に、ありえないほどバターとジャムを塗りたくったバゲットを、躊躇なくカフェオレボウルに沈めると、菅江さんと文広さんの目が点になった。穂波さんはラズベリージャムを塗ったブリオッシュをつまみ、優雅におふたりの驚きぶりを楽しんでいる。スイスでチーズづくりを学んだという穂波さんは口元に穏やかな笑みをたたえて、瓶詰ジャムを吟味している。パリ流の朝ごはんがどんなものなのかご存じなのだろう。
あれをはじめてやられた時は、僕だって驚いた。
カフェオレボウルでひたひたにして、くったりやわらかくなったバゲットを、有悟は大きな口で迎え入れた。
「あら? 颯真くんは、カフェオレにつけないの?」
「はい。僕は歯応えたっぷりのパン皮と、もっちりした中身の弾力を楽しむ方が好きで」
「ふうん」
穂波さんは、頰杖をついて、僕と有悟をそれぞれ見比べた。
「あなたたち兄弟って似てないのね。有悟くんはおっとり、颯真くんはしっかり」
菅江さんも、僕らを交互に見て、バゲットの先端のみをカフェオレに浸す。
「顔つきや体形も、だいぶ違っとるなぁ。有悟くんはシロクマみたいに大きいが、颯真くんは細くてもっと俊敏な……猫かなにかみたいだ」
「ああ、言えてる。颯真くん猫っ毛だしね。もしかして兄弟って戸籍上のご関係?」
「いえ、それが、同じ親から生まれた、血を分けた兄弟なんです。でも似てると言われたことは一度もありません」
そうなのだ。僕と有悟は、見た目だけじゃなく、たぶん生き方も、ちっとも似ていない。
料理だけをまっすぐに追ってきた有悟と、のらくら過ごしてここに流れ着いた僕とでは、まるで違う。同じ江倉家に生まれ、両親から同じように育てられたはずなのに、どうしてこうも違うのかと思うほど。
「颯真は母親似で、私は父親似なんですよ」
三つ目のバゲットをカフェオレに浸しながら、有悟がのんびり応じる。
文広さんは、感心するように言った。
「兄弟でお店をするなんて仲がいいんだね」
「そうでもありませんよ? 先ほども有悟とは営業方針について決裂したところですし」
「それはまたなんで? 興味あるなあ、兄弟喧嘩?」
穂波さんの目が好奇心にかがやくと、有悟は身じろぎをして、仕込みがあるからとキッチンカーへ逃げていった。その足音に驚いて、牧草を食は む牛たちが、モー、モーと声をあげる。
「喧嘩ではなく、意見の相違ですね。いつもどおりと言えばそうなんですが、有悟がまた無茶を言い出しまして」
みんな腕を組んで、首を縦に振る。菅江さんたちとのご縁も、元はといえば、有悟の無茶にはじまる。牧場を訪れた有悟がその味わいの虜になり、生産量が限られていると断られても、どうしても取引させてほしいと拝み倒したのだ。
文広さんもあの時のことを思い出しているのか、苦笑気味に、顎を指で撫でた。
「熱意でもあるけどね、有悟くんの無茶の発端って」
「ええ、そうなんですが。さすがに付き合いきれないので断りました。朝にモーモー言う国際電話がかかってきてから、なんだか妙なんです」
「モーモー? 颯真くん、それってもしかしてフランス語だった?」
「ええ、おそらく。有悟がボンジュー? って挨拶してましたし」
穂波さんから微笑みが消えた。考え込むように視線を下げた眉間に、縦皺が刻まれる。何度も話そうとしてはためらい、言葉を注意深く選んでくれているのがわかる。
「あのね、颯真くん。フランス語でmortは、死のことなの。わからないけど、もしかしたら、有悟くんの知り合いが、亡くなったって報せだったのかも」
「え」
あの電話の主の、モーモー言う声が、耳に蘇った。
そういえば僕は電話の声色に、深い哀しみや憂いを感じたのではなかったか。
牛舎に戻ってきた有悟が目を赤くしていたのは、仔牛の誕生に感動したのではなく、もしかしたら、訃報が原因だったのかもしれない。
「よく話し合った方がいいね」
文広さんの言葉を合図にしたかのように、みんなが一斉に腰をあげる。
読んでいた新聞を丁寧に畳んでいた菅江さんは、文広さんと穂波さんが立ち去るのを待って、話しかけてきた。
「颯真くんは、やり遂げなけりゃと思う気持ちが強くて、有悟くんの今回の無茶にも反対しとるのかもしれんな。有悟くんがうちで粘ってみんな困り果ててた時も、間に入って実行可能な方法を見つけ出してくれとったろう? ま、あくまでも一意見だがね、失敗に終わるとしても取り組むこと自体に、なにか意味はあるもんだ。やってだめだったことと、やらずに終わったこととでは、後者の方が人生に悔いを残すというよ」
菅江さんは僕に新聞を手渡してくれた。紙面にはバレリーナから建築家になった満島ゆかりさんや、元政治家から家具屋を復興した橋澤直輝さんが載っていた。おふたりとも、以前有悟と働いていた東京の店のお客さまだ。挑戦をたしかな形に変えたおふたりの姿は、菅江さんからのエールにも思えた。
キッチンカーへ顔を向けると、有悟がボウルと泡立て器を手にしているのが見え
た。新聞を握る手に力がこもる。
「有悟と、話してみます」
*
黒塗りのキッチンカーの厨房は、こだわり抜いた機材がコックピットみたいに機能的に配置されていて、ようやくふたりで並べるくらいの広さしかない。大柄な有悟には狭いだろうに、ひらりひらりと身を翻して調理するさまは、踊っているようにも見える。
有悟は銅の片手鍋をコンロにかけ、木べらを丁寧に動かしていた。しゅっしゅっと規則正しいリズムが、厨房に響いている。
話してみるとは言ったものの、どう切り出したらよいか迷い、僕は下げてきた食器を横で片付けながら、ようすを窺った。有悟の手元からはなにか甘い香りが漂ってくる。
「いつも食べてるものが全然違うものみたいだと、有悟の腕前を褒めてくれてたよ、菅江さんたち」
「素材がいいんだよ。菅江さんたちの牛が好きって気持ちが素材に出てるんだ。朝に仔牛が生まれるところを見せてもらって、すごく納得したよ。牛もひとも、愛情深い」
「あの時の電話、友達?」
規則的だった木べらのリズムがかすかに乱れた。
「うん。パリの店にいた時のテオっていう元同僚。私は厨房、テオはホール係で。面倒見がよくてさ、年下だけど店では先輩だからって、なにくれとなく世話を焼いてくれたんだよ」
「フランス語だったからひとつもわからなかったが、気持ちって言葉じゃなくても、伝わるもんだな。あとでって大きく言ったら、黙った」
有悟が笑い声を立てた。
「それ、いい具合に聞き違えたんだ。待って、って意味のフランス語と似てる。テオもずいぶん取り乱してたから」
しばらく無言で木べらを動かしていた有悟は、鍋を火からおろして、作業台に置いた。
「蒸し返して悪いんだけど、やっぱり私、翁を捜さなきゃならない」
「あの電話と関係が?」
「約束を、守りたいんだ」
そうして有悟は、厨房の片隅から、薄汚れた封筒を取り出した。
封筒には水に濡れたような跡があった。いびつに歪んで、青いしみや泥の跡があちこちにある。
「私と翁をつないでくれていた、マダムという恩人が、亡くなったらしい。東京の店にいた頃、翁からのこの手紙を届けてくれたんだ。翁の支援のおかげで、私は前の店を開くことができた」
その翁という人物は、芸術家などを支援しているらしい。自身を竹取翁に見立て、光りかがやく才能を持つひとをかぐや姫になぞらえて、かぐやびと、と呼んでいたという。翁は、かぐやびとの才を天からの授かりものだと考えて、彼らがその才を存分に発揮して、かがやくまでを支援しているのだそうだ。
取り出された便箋もにじんだしみや汚ればかりで、なにも書かれていなかった。
「文字は消えてしまったけど、パリの店で食べた私のナス料理がどんなにおいしかったか、心を込めて綴ってあった。心が躍るような店をつくらないかと言ってくれたんだよ。でもその約束を私は守れなくて。だから今度こそ、守りたい」
翁とのやりとりは手紙の他は伝言で、翁の代理人であるマダムと呼ばれるひとが、取り次いでくれていたという。翁もマダムも芸術に造詣が深く、感性の磨き方を教わったそうだ。遠くまで買いに行った朝食のパンは、マダムを偲んで、彼女の好物を揃えたらしかった。
「マダムから預かったものを、翁に返したいんだ。颯真も見たことあるはずだよ。
時々テントに飾ってる、漆の箱」
「あの六角形の?」
つややかな漆黒に、粉雪のような金蒔絵と螺鈿細工の雪の結晶がきらめく、うつくしい箱のことだ。小さめのスツールほどの高さのある箱で、端正な六角形がふんわりふくらんだような、曲線を帯びた愛らしい姿をしている。金の粉雪に舞う虹色の雪は、ひとつとして同じ姿がない。ひょいとその辺に置いておくような代物ではなく、美術館のガラスケースの方がよほど似合う品だが、有悟は時折これを店に飾っていた。
「もしも自分が亡くなった時、あの箱がまだ私の手元にあったら、翁に届けてほしいとマダムから言われてる。私には大事な約束なんだよ」
「何年かかっても? 下手したら、見つからないとしても?」
「それでも守りたい。できる限りの努力はしたい」
唇をぎゅっと嚙み締めた有悟は、こうなったら考えを決して曲げない。この店をはじめた時だってそうだった。
やり遂げられないかもしれないことに、どうしてそう情熱を傾けられるのか、僕には理解ができない。僕と有悟の違いは、こういうところにあるのかもしれない。
困難しかない道に向こうみずに突っ込んでいく兄はいつだって理解しがたい。
だけど、真摯な思いだけは伝わってくる。言葉を超えて。
「マダムってことは、そのひとは翁の奥さんなのか?」
「たぶんね。マダム・ウイって呼ばれてた。ウイっていうのは、はいといいえのウイじゃないかと思うんだ。穏やかな笑みでなんでも受け止めてくださる方だったから」
「じゃあ、奥さんの方も本名はわからないんだな。翁もマダムも日本人なんだよな?」
「うん、そう聞いた。日本とパリに家があるはずだけど、パリの家は引き払われたとテオが言ってた。翁は、日本のどこかにいるはずなんだ」
「パリでナス料理を食べたと言ってたな、パリの店に来ていた日本人客はわかるか?」
有悟はしげしげと僕を見た。
「……颯真、もしかして、手伝ってくれるの?」
「ほんの少しだけだ。長いこと付き合う気はないからな。どのみち一緒に動くなら、有悟の突拍子もない動き方よりは、多少ましな道筋を見つけられるだろうから。有悟のためっていうより、僕自身のためだ」
そう、僕自身のためだ。
無謀だとただ切り捨てる前に、自分とは違う価値観と向き合うためにも。
なにより、この隙だらけの男に任せておいたら、僕の毎日だって大変なことになる。
有悟は、僕の手を取って、ぶんぶん振りまわした。
「ありがとう! よかった、颯真の好きな甘いものをつくりまくって、逆兵糧攻めでもしないと無理かと思ってたんだよ!」
有悟が取り出したボウルには、たまご液をふくふくに吸い込んだバゲットが入っていた。
熱した鉄のフライパンにバターを放り込み、バゲットを入れると、ジュ、といい音がして甘い香りが広がる。そのまま中弱火で両面を焼きあげて皿に盛り、癖のないできたてチーズ、フロマージュブランを添えて、先ほどの銅手鍋からすくいあげた茶色いソースをとろりとかけた。
「言葉代わりにこれで籠絡しようと思ってたんだよ。パンペルデュ。失われたパンって意味だよ」
屈託なく腹の内を明かした有悟は、フォークを添えて、その皿を差し出した。
あつあつのパンペルデュからは甘い香りが漂い、たまご液をたっぷり吸ったバゲットは、フォークで難なく切り分けられるほどやわらかくなっていた。表面はカリッと、中はじゅわっとしたところと、ふるふるしたところがあって、酸味のないヨーグルトのようなフロマージュブランと合わせると、口の中がやさしさにあふれた。ところどころぎゅっと甘いのは、あの茶色のソース。正体は、搾りたてミルク
でつくられた、生キャラメルのソースだった。
こんなもので毎日のように攻められたら、たしかに僕はひとたまりもない。それも悪くないかもしれないが。
「硬くなって捨てるはずのパンを、諦めずに工夫しておいしくやわらかくした料理だよ。無理に思えることでも、なにか工夫できるかもしれない。颯真、どうか協力してください」
最後のひとくちを食べる僕に、有悟が頭を下げた。
エスプレッソでひと息ついた僕らは、有悟が指折り数えるパリの店のお客さまを、メモしながら整理した。
「私は厨房を離れられなかったから、日本人のお客さまの予約があると、テオが教えてくれてた。ええと、よく来てくれたのは近くに勤めていたアラキさん、フルカドさん、カメザワさん。ご近所に住む美食家のカトウ夫妻と、出張のたびに寄ってくれたオオニシさん。ひとりでも、ご夫婦でもよく来てくれたアシザワさん。あ! ということは、マダムとご一緒に来ていたカトウ夫妻かアシザワさんかな?」
「そうとは限らない。他のひとにも配偶者はいるかもしれないだろ」
翁がパリの店で食事したのなら、名のあがったうちの誰かなのだろうか。とはいえ、そのひとたちの足跡を辿たどるのも、ほとんど不可能に思われた。有悟がパリで働いていたのは十年近くも前のことだ。今も同じように暮らすひとがどれほどいるのだろうか。
作業台に置いた、先ほどの新聞が目に入った。満島さんや橋澤さんのように、年月の中で仕事や生活環境が変わるひとだっているだろう。
「情報が少なすぎて、踏み出す一歩が決められないな」
「私ら、ちょっと凝り固まってるかも。少しゆるんだ方がいいよ」
有悟は頭の上に両腕を伸ばし、手のひらを合わせると、左右にゆれた。なんと吞気なことか。呆れて見ていたが、体がほぐれると気持ちが上を向くと促され、真似てみると、全身がびりびりと痛んだ。体中がこわばっていた。
「同じように支援を受けた知り合いでもいたらいいんだけど」
「ひとつの分野にひとりって決めていたらしいから、同業のひとはいないんだ。でもパリの店でふたりだけ会ったことがある。有名なひとだったよ。あ、このひと」
有悟が新聞をすっと指さした。そこには世界中で活躍するピアニスト、山科実のコンサートツアーの広告が載っていた。
「一緒に撮った写真もあるよ。いつでも連絡してって言ってた。そうだ、山科さんに会ってみたらどうだろう?」
それはきっと社交辞令だろうが、万が一にも話を聞けるなら、どんな小さな情報でもありがたい。
「私もいろいろ考えたんだ。今の私が心躍るような店にするなら、世界で一番おいしい料理をつくろうって」
「世界で一番おいしい料理?」
「お腹だけじゃなく、心にもおいしい料理だよ。翁を捜して旅する間に、その場所ならではのおいしいものにもたくさん出逢うと思うんだ。だからさ、もし定番メニューが出せなくても、それ以上に魅力ある特別メニューを出す」
たとえば、とメモに有悟が書くアルファベットの文字が長く伸びていく。ただしそれはやっぱりインチキフランス語で、単語のつなぎ合わせのようだった。
「無謀だって颯真は言うけど、私は、うまくいくんじゃないかって思ってるよ。おいしいパンと、いいお酒があれば、いい道ができる」
「なんだって?」
「フランスのことわざなんだ。おいしいパンといいお酒は、ここにふんだんにあるじゃないか。いい道はきっとできるはずだよ」
この困難しかない状況でそう言える楽天家ぶりには閉口するが、それが有悟なのだろう。羅針盤が嵐を示していても、迷わずに突っ込んでいく。
困難は、ひとを窮地に陥れもするが、ほんの少しずつでも、できることを増やしてくれるのかもしれない。ならば有悟といる限り、巻き込まれた流れに翻弄されるだけじゃなく、対処を覚えていくことで、僕自身、成長できるかもしれない。僕は小さくため息をついて、有悟に向かって笑いかけた。
「さきほどはありがとうございました。ご助言のおかげで兄と話し合えました」
牧場の売店を整える菅江さんたちのもとに、さきほどの礼を言いにいくと、三人は互いに顔を見交わして、笑った。
穂波さんが、秘蔵のチーズを冷蔵庫から出して、手渡してくれる。
「さっきは似てないって言ったけど、やっぱりあなたたちって兄弟ね。芯し んの部分がそっくり」
「それは、よろこんでいいのやら、悩むべきなのやら」
「ついさっき、有悟くんも挨拶に来てくれたの。彼の方は、おいしい牛乳のおかげで弟に食べさせたいキャラメルソースができました、ってレシピごと」
小さな瓶と手書きのメモを、穂波さんがうれしそうに見せてくれた。
「次に来る時は、うちで商品になっとるから、楽しみにしててくれ」
菅江さんたちに送り出されて、僕たちは、それぞれの車に乗り込んだ。
牧場では牛たちが散歩したり、寝そべったり、モー、モーと鳴きながらゆったり過ごしている。
群れの中に、ひときわ小さな仔牛を見つけた。
生まれたばかりなのに、仔牛はもう、小さな一歩を、力強く踏み出していた。
*
続きは7月2日発売の『すきだらけのビストロ うつくしき一皿』で、ぜひお楽しみください!
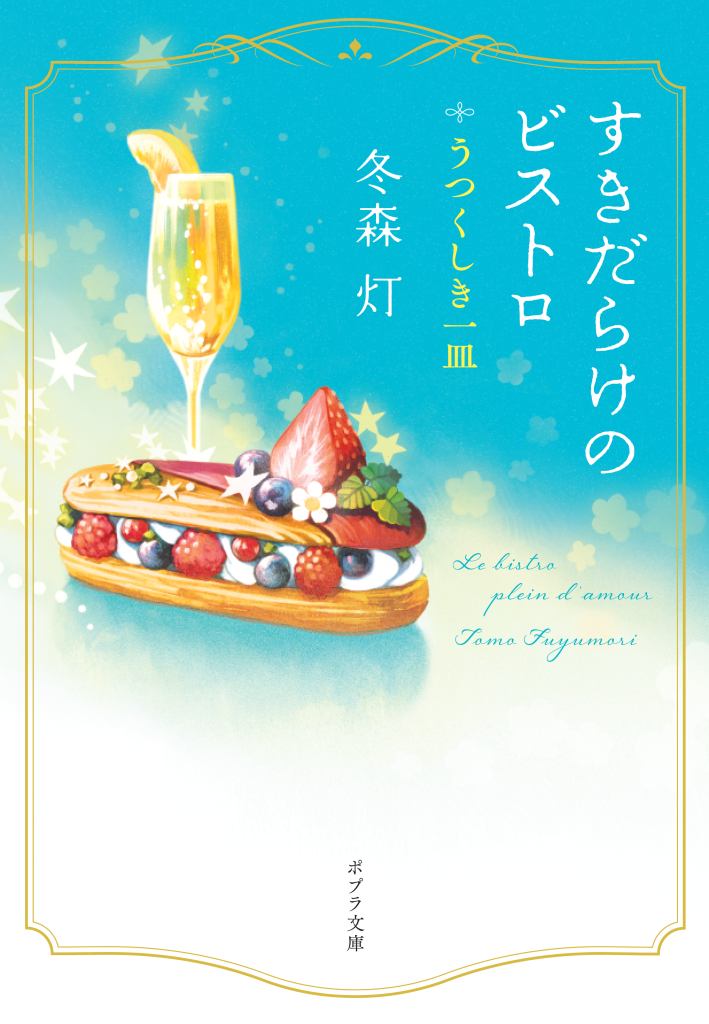
■ 著者プロフィール
冬森灯(ふゆもり・とも)
第1回おいしい文学賞にて最終候補となり、2020年、『縁結びカツサンド』でデビュー。他の著書に、『うしろむき夕食店』『しふく弁当ききみみ堂』がある。








