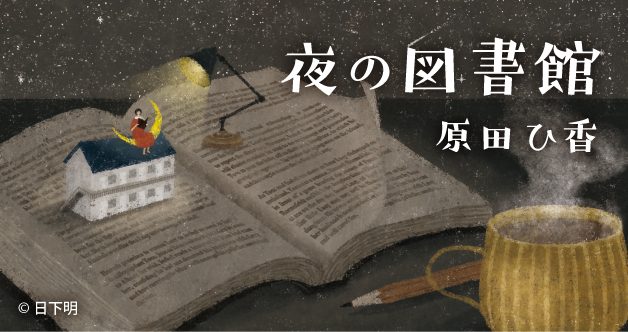引っ越しを終えたあと、一眠りして午後三時に図書館に行った。
玄関のところに大きな黒塗りの車が駐まっていた。大きいだけでなく、車体もぴっかぴかで、一目で高い車とわかる。思わず中をのぞくと、スーツに黒い手袋をした年配の運転手が座っていて、週刊誌を読んでいた。
こんな立派な車、乗ってきたのはいったい誰だろう、と乙葉は考えて、はっと思い当たった。
もしかして、ここのオーナーではないだろうか。
篠井はあんなことを言ったけど、もしも、何かの拍子にオーナーが来て、ばったり会うことができたら、ご挨拶もできるかもしれない。
乙葉は急ぎ足で中に入った。
図書館の受付にちょうど篠井がいて、どこかに電話をかけていた。少し深刻な顔をしている。彼の隣に、紺の背広を着ている初老の男性も立っていた。
あの人、もしかしてオーナーだろうか、と思いながら近づいた。
乙葉に気づいて、彼も軽く会釈した。
篠井の電話が切れるのを待って、声をかけた。
「おはようございます! あ、いや、おはようじゃないですけど……」
もう午後だ、ということに気がついて、乙葉は慌てて口をふさいだ。
「ごきげんよう」
「はい?」
「ごきげんよう」
ここでは、いや、この人はごきげんようで挨拶するのか……。
「ごきげんようなら、時間は関係ありませんからね」
「あ、確かに……」
「それはともかく、こちらは図書館探偵の黒岩さんです。樋口さんは初めてでしたよね」
「え」
オーナーじゃないんだ、図書館探偵……いや、連日、新たな驚きがあるな……ここ。乙葉は挨拶より先にまじまじ彼を見てしまった。
「どうも、初めまして。図書館探偵の黒岩鉄次です」
「あ。失礼しました。初めまして。樋口乙葉です!」
「黒岩さんは元警察官なんですよ。基本的には図書館が開館している時間に来てもらってます。昨日は、樋口さんはほとんど整理室にいたから会わなかったですね」
「はい」
「探偵という肩書きですが、まあ、一種の警備員みたいなものです」と黒岩が説明した。低くて落ち着いた声だった。
「今日は、連絡して早く来てもらったんです……図書館の前に駐まっていた車に気がつきましたか?」
「あ、はい!」
「今、お客様が来ていて」
「それって、オーナーですか⁉」
「えええ⁉」
初めて、篠井は目を見開いた。
「あの車、もしかして、ここのオーナーかと」
彼はふっと微笑んだ。
「そんなわけない……こちらにはあの方はいらっしゃいませんよ。いえ、いっそのこと、そうだったらいいんですけどね」
「違うんですか……」
乙葉は自然に首が垂れてしまった。
「お会いしたかったのに」
「残念ながら、ちょっとむずかしいお客様でね。じゃあ、失礼します。黒岩さんも来てください」
篠井と黒岩は、蔵書整理室の方に向かった。
乙葉は昨日篠井に借りた寝袋を持ってきていたのだが、返しそびれてしまった。彼も気がついていたはずなのに、何も言わなかった。そんなにすごい客なんだろうか……と考えながら、受付の中の足下に寝袋を置かせてもらった。
彼らと入れ替わりのように、受付の中のスタッフルームからみなみが出てきた。手にお茶をのせたお盆を持っている。
「みなみさん、おはようございます。いや、ごきげんよう」
「ああ。乙葉ちゃん、ごきげんよう」
「なんか、お客さん、来ているんですか」
みなみに聞いてしまったのは、彼女が篠井どころではないくらい、困った顔をしているからだ。
「そう。急に来たの、さっき……」
みなみは声をひそめた。
「誰ですか? むずかしい人だって、篠井さんが言ってたけど」
「篠井さんがそう言ったの? じゃあ、乙葉ちゃんにも言っていいのか」
みなみは乙葉を手招いた。耳を近づけるとそこにささやいた。
「田村淳一郎先生よ」
「げ、田村淳一郎?」
田村淳一郎はこの業界なら誰もが知っている、有名作家だ。確か、七十歳くらいで、若い頃からヒット作をバンバン出しているし、今も新刊書を出せば必ず数週間くらいはベストセラーに入る。
そして……乙葉のような末端の書店員にさえ、その名がとどろくほど「性格が悪い」と有名だった。
テレビなどのメディアで見せるのは、ちょっと豪快な、でも懐の深そうなおじいちゃん、という姿なのだが、編集者には一転、気難しく威張り屋で、わがまま言いたい放題なのだという。
「……どうしてまた、うちに?」
ふと気がつくと、自分がまだ二日目なのに職場を「うち」と呼んでしまっていた。言ってしまってから心の中で少し照れたが、みなみは気がついていないようだった。
「わかんない。どうもあたしたちの出勤前から来てたみたい。北里さんと篠井さんが応対して、応接室に通したの。それから篠井さんがあちこちに電話掛けまくってる。とにかく、あたしはお茶、出してくるわ。頼まれたから」
「私、着替えてきます!」
「お願い。受付、手伝ってくれる?」
「あ、そう言えば、応接室ってどこなんですか」
「二階の、カフェの隣よ。カフェが開いてる時間なら木下さんにコーヒーも出してもらえるんだけど」
「なるほど、あそこですか」
みなみが二階に上がっていくのを見送って、乙葉は「蔵書整理室」に足早に向かった。昨日、正子たちに、蔵書整理をしている間はそこのロッカーを使いなさい、と言われていた。
一大事、一大事。気がつくと小声でつぶやいてしまっている。本棚を開いてそこに入ると、中で正子と亜子、篠井、黒岩が立ったまま話していた。
「……そんなの急に言われてもねえ」
正子の声が聞こえた。首をかしげている。
「まだ、段ボールの整理もできてませんよ。亡くなってから、数週間なんだから。うちに届いているのも早いくらいよ」
「それで、あの人はなんて」
入り口から背中を向けていた亜子が言った時、篠井が小さく首を振った。乙葉がそこにいるのを気づかせようとしたみたいだった。亜子が振り返って、乙葉を見た。
「あら。樋口さん、おはようございます」
「すみません、お話中に」
なんだか、四人のただならぬ様子に、乙葉は身体が固まってしまった。
「いいのよ」
正子さんがすぐに気を取り直したふうに言う。
「私、荷物を置いて……エプロン付けてすぐに……あの受付に座ってって言われてますから」
あんまり四人がこちらを凝視しているから、ちょっとしどろもどろになってしまった。
「いいじゃないの、篠井さん。樋口さんにも聞いてもらった方がいい。今は彼女もここの一員だし、蔵書整理に関係していることなんだから」
「そうですね。着替えながら聞いてください」
「はい」
乙葉は部屋の端の、ロッカーに荷物とコートを置き、エプロンを取り出した。
「実はね、今、図書館の前に駐まってる車、田村淳一郎先生なの」
「ちょっとだけ、みなみさんに聞きました」
乙葉はエプロンの紐を後ろ手で結びながらうなずいた。手こずっていると、亜子が自然に乙葉の後ろに来て、紐を結んでくれた。亜子は結び終わると、とんとん、と乙葉の背中を優しく叩いた。まるで、大丈夫よ、と言うように。
「田村先生、なんの連絡もなしに押しかけてきて……本を見せて欲しいって言うの」
「本……ですか」
ここは一応、図書館だ。本を見せて欲しいと言われるのは当たり前のことだが。
「それが、あれなの。白川忠介さんの本を見せてって」
「……白川忠介……? 誰です?」
「そうよね、乙葉さんくらいの歳の方はご存じないかも知れないわね」
ここは本当に過去に生きる図書館だ、と思った。昨日から何度も「乙葉さんの歳ではわからないわね」と言われている気がする。
ふっと、早く歳を取りたいな、と思った。歳を取る……経験を積んで、自分も皆に加わりたい、と。
ずっと、「早く決断しないと、すぐに歳を取ってちゃんとした就職ができなくなっちゃうよ」と親たちに言われていたし、自分もそれは意識していたのに。
就職のことはともかく、二十代半ばにさしかかってきて、「もう、そろそろ三十代になっちゃうなあ」と焦る気持ちはなくはなかった。女として。
それが、一瞬とは言え、歳を取りたいな、と思うなんて。
「田村先生と白川先生は両方、関東文学賞の受賞者なのです。それも同時受賞の」
「ああ、関東の」
関東は中堅どころの出版社が主催している、文学新人賞だ。今も存続している。
「あ、でも関東は純文学の賞では?」
「そうです、当時は田村先生も純文学の作家さんだったのです」
篠井が口をはさんだ。
「なるほど」
「白川先生の方は受賞作がそのまま芥川賞の候補になりました。惜しくも受賞は逃されましたが、評価は高く、その後も順調にキャリアを積まれていました」
「そうですか」
「田村先生の方はなかなかむずかしい時期が続きました。書いても書いても出身文学賞の雑誌に載せてもらえることもなく、何度も何度もボツを食らって悔しい思いをしたと聞きます」
亜子さんが小さく肩をすくめ、「それであんなに性格がひん曲がっちゃったのかしらね」とささやいた。正子さんが唇に人差し指をあて、「し」と押さえた。
「いえ、話に聞くと、その頃は田村先生も性格が良かった、真面目だったと聞きます。とにかく、頑張られていたと」
篠井は言った。
「だけど、ある編集者の説得があって、エンターテインメントの小説を書いて、花開きました。最初のエンタメ小説がいきなり、有名書評家の目にとまり、大絶賛されてそこそこヒットしたのです。そこからはご存じの通りです。そして、性格がひん曲がったのもその頃で……」
「篠井さんまで」
正子が眉をひそめる。
「やっぱり、人はずっと苦労してきて、急にちやほやされるとおかしくなっちゃうんでしょうね」
「なるほど」
「有名な話ですが、山登りが好きな田村先生が担当編集を引き連れて登り、一番先に登ったやつに次の原稿を書く、と言って、我先にと競争させ、その時編集者が転んで大けがをしたとか、いや、先生の帽子が風で飛んで、それを拾ってきたやつに次の原稿をやると言って、岩場から転げ落ちた編集者が足を折ったとか……とにかく、真偽はわかりませんが、そういう噂には事欠かない人です」
「とにかく、噂は噂。今は私たちがどうするか、考えましょう」
正子がきっぱりと言った。
「白川先生の本を見たいというのはどういうことなんでしょうか。お二人は仲がよかったんですか」
乙葉がおそるおそる聞く。
「……実はね、それもまた、いろいろあるの」
亜子が眉をひそめる。
「田村先生がエンタメで成功した頃、白川先生が新聞エッセイを書かれたのよ。それがすごい内容で。君死にたまふことなかれ、って題名で……まあ、与謝野晶子をまねているんでしょうね」
「ずいぶん大仰よね」
「自分のライバルがひどい作品を量産している、がっかりした、自分はいつか彼に勝ちたいと思ってやってきたのに、あれではもう彼に勝つことはできない、彼は死んだも同然だから、とか……せめてこれ以上死なないでくれ、とか」
「だから、君死にたまふことなかれ、なんですね」
「それから、二人は犬猿の仲と言われてるわ。というか、ほとんどなんの接点もなかったはずだから、犬猿も何もないのかもね。住んでる世界も変わってしまったし。田村先生は流行作家、白川先生は……残念ながら、結局、芥川賞を取ることもなく、たんたんと文芸誌に作品は発表されていたけど、ここ十年くらいは本も出されていなかった。あまり売れないから。評価は高いんだけどね」
「私は大好きよ。静謐で誇り高くて、でも、斬新で、いつも驚きに満ちている……人には、人生にはこんな真実がまだ潜んでいたのか、って毎回、感嘆する。白川先生がお書きになった雑誌は必ず買って読んでた」
その時、ドアが開いて、みなみが入ってきた。
「篠井さんか、誰か来てください。先生がいつまで待たせるんだ、って怒っていて、あたしには手に負えません」
「ああ、すみません。僕が行きましょう」
みなみと篠井が出て行った。黒岩もあとに続く。田村が暴れていたりしたら、彼の出番だからだろう。
「……じゃあ、私、受付の方でみなみさんを手伝いますね」
「そうね、頼むわね、樋口さん」
「だけど、白川先生の本は今、どこにあるんですか」
正子が首を振る。
「まだ、この部屋にさえ来てないわ。倉庫に入れっぱなし。膨大な量よ。他の方の本もあるし、たぶん、整理するまで早くても数ヶ月はかかると思う」
「なるほど。じゃあ、私は行ってますね」
乙葉は受付に戻るため、部屋を出た。
受付のところにはお盆を小脇に抱えたみなみと今、登館したばかりの渡海がいて、顔をつきあわせてひそひそと話していた。たぶん、内容は田村に関することだろう。
みなみは乙葉に気がつくと、一つうなずいた。
「大丈夫ですか」
「うん、あたしがお茶を淹れた時は『いつまで待たせるんだ』って言ってたけど、その言い方がさ、もう、なんか妙に怖いわけ。低い声で」
乙葉は田村が任侠ものや刑事ものが得意な作家だったことを思い出した。
渡海が首を振る。
「俺が田村さんにそんなこと言われたら、ぶるっちゃう」
「ここにいらした時はどんな感じだったんですか」
「……最初にいたのは入り口の北里舞依さん。あの人はいつも始業時間の四時の三十分前に来て、玄関を開けるでしょ。その時はすでにあの黒塗りの車が駐まってたんだって」
「へえ」
「で、田村先生は怒り狂っていて、いったい、何をやってる。いつまで待たせるんだって」
「事前に連絡が来てたんですか」
「ううん。だけど、図書館という名を拝しているなら、昼間に開けていてしかるべきだろうって。まあ、自分が調べもしないで勝手にやってきたから、ちょっと恥ずかしかったのかもしれない」
「ああ」
確かに一理ある。勢いで乗り込んできたら、閉館してたんだから。
「で、無理矢理入ろうとするのを、北里さんが押しとどめて、玄関の前で押し問答になっているところに、篠井さんがやってきたわけですよ」
「へえ。北里さん、女性一人でよく」
「ほら、あの人、空手の有段者だからさ」
「なるほど」
「何事にも動じない」
「それ、空手と関係ありますか」
「いや、あの人、普段あまりしゃべらないけど、時々、話すとおもしろいよ。『わたくしは人間の急所を知っておりますから』っていうのが口癖だし」
「ひゃー」
「とにかく、それで篠井さんがしかたなく応接室に通したところで、あたしたちが来たわけ」
「白川さんの本は今どこに……?」
そこまで黙って話を聞いていた渡海が尋ねた。
「まだ倉庫ですって。かなりの量があるはず」
乙葉は今、聞いたばかりのことを説明した。
「ああ、そうなの。どうするのかしらね」
話しているうちに篠井が二階から降りてきた。深刻そうな顔をしている。
そして、たぶん、自分でもあまり気づかないうちに、小さくため息をついた。そして、そんな自分を三人が見ていることに気づいて、はっとし、受付に歩いてきた。
「どうでしたか」
みなみが一番最初にせき込むように尋ねる。
「白川先生の本はまだ整理できてないし、それはたぶん、数ヶ月後になる、整理が終わったら一番にお知らせする、と申し上げたのですが…………やはり……どうしても今日、白川先生の本を見たいと言って、譲られないのです」
「ああ。いやあねえ。わがままよ」
みなみがずけずけ言う。
「もちろん、お忙しい方ですし、そうそうこんな辺鄙な場所まで来られない、というのはしかたないことですが」
篠井がそれでも少しだけかばった。
「今から倉庫から出してきて、こちらに並べるまで、数時間はかかるし、量もたくさんだから、先生が一通り見るのもお時間がかかりますよ、とは申し上げたのですが」
「倉庫ってどこなんですか」
乙葉の問いに、篠井は渡海やみなみと顔を見合わせて小さくため息をついた。
「……これがまた遠いのです。青梅の奥の方に古い家があって倉庫代わりに使ってるんです。ここから車で一時間くらいはかかりますし、これから向かって、本を車に運び入れ、また戻って……」
「二時間半はかかりますね」
「まあ、田村先生もそれでもいいから、行ってこい、とおっしゃるので」
「なるほど」
「蔵書整理係は正子さんと亜子さんですが、お二人に行ってもらうわけにはいきません。遠いし、重労働です。ここは僕と、渡海さんと徳田さん……それから……」
篠井の目が乙葉のところで止まった。
え、私? と自分の顔を指で指してしまう。
「ええ、樋口さんもご同行してもらえますか。樋口さんは倉庫、初めてでしょう。ちょうどいい機会ですから」
「黒岩さんに行ってもらった方がいいんじゃないですか」
渡海が気の毒そうに言った。
「いえ、黒岩さんには念のため、ここにいてもらいましょう。またごねると面倒です。ああいう人は女性には上から来るから……」
「ああ」
確かに、相手が女性となると、元々尊大なクレーマーがさらに強気になることがある。乙葉も書店でよく見てきた。
「今も、応接室の前に立ってもらってます」
「わかりました。私、行きます。倉庫、行ってみたいです」
乙葉は言った。
「今日は冷えるし、倉庫はここよりさらに冷える場所です。たいした暖房器具もないので温かくして行きましょう。必要なら、寮に戻られて、何か着るものを取ってきてください」
「ダウンコートを着てきたから大丈夫です」
「では、行きましょう。車一台で運べるかなあ?」
篠井が首をひねる。
「ここの車はハイエースですよね。俺、自分の車、持ってきます。普通の乗用車ですが」
「それだけあれば、なんとかなるか」
「僕たち、入り口に車を回してきますから、徳田さんを呼んできてください」
篠井はみなみに向き直った。
「お茶はまめに淹れ替えてください。そのうち木下さんも登館されるでしょうから、そうしたら、先生にお聞きしてコーヒーを淹れて差し上げてもいいですね」
「ラジャー」
みなみがおどけて、敬礼した。
「何か、困ったことがあったら、正子さんや亜子さんに相談してください。僕の携帯に連絡くださってもいいです」
「アイアイ・サー!」
みなみはもう一度、敬礼した。
徳田と一緒に入り口で待っていると、二台の車がやってきた。徳田が自然に渡海の車の助手席に乗ったので、乙葉はハイエースの助手席に座った。
「ラジオでも付けますか」
乙葉がコートを脱いで、後ろの座席に置いていると、篠井が言った。
「はい、お願いします」
篠井とのドライブがこれから一時間くらい……復路を合わせると二時間は続くのか、と思ったら少しだけ緊張した。
「いつもどんな曲を聴きますか」
「なんでも聴きますよ」
「じゃあ、適当に」
篠井が選んだのはNHKで急にクラシックの弦楽四重奏が流れてきたので、驚いたが、彼は特に気にするふうもなくそのままにした。
「……こういうこと、よくあるんですか、作家の先生が来ること」
しばらく走ると、乙葉は沈黙に耐えられなくて尋ねた。
「いや、ないです。あっても年に二、三回ですかね……それに、ほとんどの先生はたぶん、黙って普通のお客様と同じようにいらっしゃって、本を見て帰って行かれますから、こちらで気がつかないこともあるでしょうし」
「確かに」
「あちらから連絡していらっしゃるのは数回です。ご自身の作品の資料としていらっしゃったり、作家の卵の方が、別の作家さんの蔵書を見て参考にしたいといらっしゃったり。単純にファンとして見に来る方もいます。中にはご自分の死後、どんなふうに本が管理されるのか見たいとおっしゃって来る方もいる。でもこんなのはめずらしいです」
「でしょうね」
それからまた沈黙が続いた。
「……あの、ちょっと変なことを聞いてもいいですか」
乙葉はおそるおそる尋ねた。
「なんなりと。僕の答えられることでしたら」
「こちらの図書館……やっていけるのは……あの、いえ、私は気にしてないんですけど、両親が私立の図書館なんてどうしてやっていけるんだ、とか、そんな経営でどうしてやっていけるんだ、とか、なんとか、気にしてまして」
「ああ」
篠井がうなずいた。
「こんな経営で不思議ですよね。ご両親が心配なさるのも無理はないです」
「いえ、本当に私は気にしてないんです。万が一何かあっても、地元に帰って別の企業に就職できるとは思います」
あ、と自分で言っていて、自分で慌てた。
「だからと言って、適当に働いているとか、適当な気持ちでここまで来たわけじゃなくて……昨日一日働いただけですけど、可能ならずっとこちらで働きたいなあって本当に思うほど素敵な職場で、だからこそ、私も少し心配という気持ちもあって」
話しているうちに息が切れてしまった。
「わかりました、いや、もちろん、わかっています」
前を向いているからわかりづらいが、篠井は苦笑しているようだった。
「樋口さんはちょっとまわりを気にしすぎですね。繊細さんなんですね。もっと、力を抜いて、言いたいことを言っていいんですよ、ここでは」
「繊細さん……あ、ありがとうございます」
そんなことを職場で言ってもらったことはなかった。
「まあ、僕はちょっと鈍感なところがあるし、正子さんや亜子さんは鈍感ということはないけど、歳を重ねられてますから、どんと構えているところがある。あまり気にせず、働いてくださればいいと思いますよ」
「篠井さんが鈍感ですか!? それはぜんぜん思いませんでした」
思わず、笑ってしまった。
「まあ、私、昨日来たばかりですからわからないこともたくさんありますが」
「親には、お前は本当に鈍感だねえ、なんて言われることありますよ」
「へえええ!」
「まあ、それはいいや。とにかく、あまり気を遣いすぎないで。これから長くお付き合いするんだから、職場ではリラックスしていきましょう」
「本当にありがとうございます」
思わず、助手席で、深々と頭を下げてしまった。
「で、さっきの話ですが……」
「あ、はい」
「僕がちょっと聞いたところによると、あの図書館の建物自体は、昔……いわゆる、バブルの時代に、不動産でもうけた金持ちが趣味で建てた図書館らしいんです。それがバブル崩壊で倒産して、競売に掛けられ、でも、うまく使われることなく何度も持ち主が変わって、廃墟のようになってうち捨てられていたのを安く買い取って直したんだって、聞いてます。裏のアパートも同じです。そして、最初はほそぼそと作家の蔵書を引き取ってオーナー一人で整理していたのを、数年前、海藤亮一が」
篠井は英訳されてから海外でとても売れ、さらに、ノーベル文学賞にノミネートされてからさらに売れた作家の名前を挙げた。彼は五年ほど前に亡くなっている。
「死後、蔵書をうちに残してくれてから、やっとお客さんがコンスタントに来てくれるようになりました。海藤亮一は海外でも有名だし、英語の本もたくさん持っていたので、海外からもファンが絶えず来てくれるようになりました。本当にありがたいことだと思っています。まあ、彼の蔵書が盗まれて、オークションに掛けられて、ちょっとしたニュースになったりしましたが」
「そんなことがあったんですか」
「それから、入り口の警備を強化し、黒岩さんが来るようになったんです。でも、その事件でまた少し有名になりましたから怪我の功名です。ある程度、経営が楽になりました。蔵書を寄贈してくれる作家さんやそのご家族も増えました。中には、財産の一部をうちの存続のために残してくれる方もいますし……それから、国の方からも文化財保全のため、補助金が下りるようになりました」
「そうですか」
「でも、いまだ運営資金のほとんどは、うちのオーナーの個人資産から出ていることも嘘ではありません」
「え、そうなんですか!」
それはオーナーのポケットマネーということか。
「実は……」
「はあ」
「さっきの田村先生、もしも、今日中に白川先生の蔵書を見せてもらえたら、先生の死後、蔵書を寄付してくれる、と約束してくれました。それから、多額の寄付も」
「そうだったんですか」
「まあねえ、僕もただでは動けませんよ」
篠井はめずらしくちょっと笑った。
「先生の蔵書には『日本国語大辞典』もあるそうです。セットで、ほぼ手付かずのやつが」
「あの、日本で一番でかくて高価な辞書ですね。篠井さん、意外とやりますね」
思わず、口が滑って、乙葉はまた自分の口を手でふさいだ。
「すみません、調子に乗りました」
「わかってます。でも、褒めてくれたんでしょ。そういう時は気にしなくていいんです。僕も嬉しいです」
「はあ、ありがとうございます」
また、しばらく静かなクラシック音楽が流れていた。
「樋口さん、よかったら寝てていいですよ。昨日の今日で疲れたでしょう。引っ越しもあったし」
「いえ。大丈夫です。引っ越しが終わったあと、結構ちゃんと寝ました」
「でも、まだ時間がかかるし、向こうに行ったら働いてもらわないといけませんからね」
絶対に寝ないでいようと思ったけれど、篠井の優しい口調のせいか、気がついたら寝てしまっていた。
※ ※ ※
あたしはそんなにいい人ではないし、しっかりした人間でもない。何より、明るい性格でもない。
慌てて出て行く、篠井と乙葉の後ろ姿を見送りながら、みなみは思った。
「アイアイ・サー!」なんていったいどこから出てきたんだろう。気がついたら、口が勝手に動いていた。
なんだか、四人が出て行くのを「明るく」見送ったら、めちゃくちゃ疲れた……。
あーあ、とため息をつきながら、よろよろと受付に座る。
「榎田みなみさん」
後ろから声をかけられて、どきっとして振り返った。
正子さんが立っていた。
「お一人で大丈夫?」
「大丈夫です!」
大きく笑顔を作って、親指まで立てて見せた。
「そう? なんだか、元気がないみたいだったから……疲れたら言ってね。それから、田村先生」と言いながら、彼女は上を指さした。「あの人が何か言ってきたら遠慮なく声かけて」
「本当に一人で大丈夫?」
亜子も心配そうに言う。
「あ……」
本当は一人にして欲しくなかった。誰かに脇にいて欲しかった。あのおじさん……いや、おじいちゃん……田村淳一郎、すごく怖かった。また怒鳴りつけられたりしたら泣いてしまいそうだ。それに、何か言われたら声かけて、って言ってくれても、その「言われた」時に誰かが横にいてくれなくちゃ、あたしが一人で対処するわけじゃないか……怖いよ、そんなこと一人じゃできないよ、今日は渡海さんも倉庫まで行っちゃったんだし。
「大丈夫です!」
心とは裏腹に、また笑顔で言ってしまった。今度は両手の親指を立て、それをそろえて「ぐっ」とやってみせる。
「あんなおじい、一人でやっつけちゃいます」
「やっつけるまでしなくていいのよ」
正子が思わず、吹き出した。
「あ、そうですね。とにかく、あたし、負けませんから」
「……負けていいのよ」
亜子がそう言ってくれて、はっとした。
「え」
「じゃあ、あたしたち、整理室にいるわね」
みなみの表情には気づかなかったようで、二人は去って行った。
亜子さんが言った「負けていい」ってどういう意味だろう。そう考えながら受付業務の準備をした。嵐が来ても、雪が降っても、変な小説家がやって来ても、図書館は開けなければならない。
パソコンを開いて、机を片付ける。図書館の公式問い合わせメールアドレスに来ている質問に答える。ほとんどが蔵書や扱っている作家の質問だ。
――埼玉県出身の作家、石川清孝について調べています。彼の蔵書の中に医療関係の専門書はありますでしょうか。あったら、どのようなものか、目録を作って送ってください。
同郷の郷土史研究家らしい。大方、高校の社会の先生かなんかが、退職後、研究家だと名乗ってるクチだろう。
知らねえよ、ウザいな。
心の中で毒づく。
ここは公立の図書館でもないし、自分はボランティアでもない。なんで、見知らぬ研究家風情に、メール一本で目録まで作って送らなきゃならないのか。
いや、もちろん、そういうリファレンスが図書館司書の大きな仕事の一つだということはわかっているが、ここでそこまでやってやる必要があるのか。
――その中に興味深いものがあれば、そちらに伺って直接調べるのもやぶさかではなく……。
は? いい資料があれば行ってやってもいいよ、とでも言いたいのだろうか。やっぱり、きっとこの人は教師か……学者だろう。この上から来る感じ、間違いないね。
しかし、無視もできない。みなみは石川清孝の蔵書一覧を探し出し、それをメールに添付して送り返した。できるだけ慇懃無礼な言葉を添えて。
――このたびは当館にご連絡いただき、ありがとうございます。石川清孝氏の蔵書から医学関係のものを抜き出そうと作業を始めましたが、医学については門外漢の私には見落としてしまう可能性があると途中で気づき、こちらを全部送って、見ていただいた方が確実かと思いました……。
もちろん、全図書には索引と図書の分類番号が付いているから、検索機能を使ってそれだけを取り出して目録にすることはできる。だけど、この相手はどこかむかつく。頼めば一瞬で答えが返ってくると思っている図々しさがたまらなかった。
イライラしながらメールを打って、送ってしまったら気持ちが晴れると思っていたのだが、それが「シュッ」というかすかな音とともに送信されると、書く前以上のイライラが襲ってきた。
こういう時に、みなみは自分が、本やそれに関する仕事がそう好きではないのかな、と思う。
子供の頃はおとなしい子だった。公園や校庭が嫌いだった。何事にも不器用で、運動神経が悪く、走ったら転ぶし、ボールを投げたら突き指するし、うんていやジャングルジム、鉄棒からは落ちた。怪我しないようにするには家の中でじっと本を読んでいるくらいしかなかった。幸か不幸か、両親も本が好きな人だった。
「みなみは本が好きなのね」「みなみは国語が得意なのね」「みなみは学校の先生か図書館の先生になるといいわ」……そんな言葉に背中を押されるように、なんとなく、大学の英文科に通い、図書館司書と教員の資格を取った。免許は持ったものの、学校の先生にはなりたくなかった。あまり好きではなかった学校生活にまた戻るのを考えるとぞっとした。
東京の中堅大学を卒業しても、図書館司書の仕事なんてそうはなかった。みなみは結局、地元の公立図書館のアルバイトに応募した。アルバイトはどんな仕事でも一律、三ヶ月の期限付きだった。市内には図書館が地域ごとに点在していた。自然、そこを三ヶ月ごとに転々とすることになった。同じことをしている人が何人かいて、それで、なんとかその市の図書館は持っているのだけど、誰もそれを是正しようとはしないのだった。
面接の時から、図書館司書ではなくてアルバイトとしての採用ですがいいですか、と聞かれた。つまり、専門職としてではなく、誰でもできる仕事として雇われるのだ。他には募集がないのだから否も応もなかった。
実を言うと、みなみ自身もそれを強く求めようとも思っていなかった。最低賃金の時給はもらえる。ただ、あまり高額の給与は出せないと聞かされていて、月に働ける日数や時間が決まっており、その他はサービス残業になった。年金や健康保険料を引かれると月十二万くらいが毎月振り込まれる。実家から母が作ってくれる弁当を持って通っている分にはまあ、生きていける。家に三万入れて、少しは好きなものも買えて、貯金もできる。親も「娘は市の図書館で働いています」というのは、悪くなかったらしい。こういう生活をして、いつか知り合った人と結婚するのだろうと思っていた。
地方の図書館司書、非常勤です、というプロフィールでSNSをやっていた。ハンドルネームは「サウス」。本当は関東近郊在住だったのだが、怖かったので、まるでどこかの地方に住んでいるように装った。たいした投稿もしておらず、時々、食べたケーキやカフェの写真を上げたり、小説の感想を書いたりしているくらいだったのに、数年で、数百人くらいの人とフォローしたりされたりしていた。平均的な、おとなしいSNS活動だった。
ある時、何気なく、自分の置かれている境遇について書いた。市の規約でアルバイトは一律、三ヶ月までと決められていること、だけど、実際は期間が終わると数日だけ休み、別の図書館に移るという形式で何年も続けていること、給料は手取り十二万で増えることはまったく期待できないこと……自嘲気味に書いた文章だったのに、それは瞬く間に広がった。大学出の図書館司書と教員免許を持っている「知的な女性」がこのような境遇に置かれていることは日本の根本的な構造問題ではないか……とインフルエンサーの男性に引用リツイートされて、さらに広まった。
正直、そこまで何かを訴えたくて書いた文章でもなく、みなみ自身がかなり戸惑った。もしも、これ以上広まり、社会問題になるようなことがあったら、アカウントごと消そうと思っていたけれど、それは二日ほどで鎮火し、「いいね」を数千、「リツイート」を数百されたところで、ほとんど話題にならなくなった。
ほっとしていた時に送られてきたDMがここへの誘いだった。
――拝啓、いつもツイート拝見しております。わたくし、ハンドルネーム、スリーカラーストーン、と申します。このたびの、図書館の仕事に関する、サウスさんのツイートに驚きました。もし、よろしければ、本に関する仕事をご紹介できるかもしれないのですが、いかがでしょうか。
みなみが魅かれたのは、図書館の仕事という内容でも、作家の蔵書を集めているという特異性でもなく、その待遇だった。給料も今より三万も高いし、無料の寮が付いている……。その少し前から、親の「結婚しろ」という声がうるさくなってきていた。うっとうしかったし、いずれ結婚するとしても一度は一人暮らしをしてみたかった。
あまりにも消極的な理由で、みなみはここに来た。
思っていた以上に、ここは働きやすかった。仕事はのんびりしていて、優しい人ばかりだ。
乙葉が来るまで、ここで一番若いのはみなみだった。どこか職場の「末っ子」のような振る舞いが身についてきた。ここにいる人は、ずっと年上の正子と亜子、物静かな篠井、お兄さんのような渡海(徳田はみなみが入館した頃にはまだいなかった)という面々で、「いつも明るく、おちゃめな末っ子」を必要としている気がした。いや、考えるより先に、身体がそう反応していた。
だけど、こうして、わがままな利用者のメールに返事を書いていると、自分の本性が現れてきてしまって怖い。
この図書館で働いている他の人と、自分はまるで違う……。
あとから入ってきた徳田も、昨日来た乙葉も「本が大好き!」「小説が何より好き!」ということは隠そうとしない。
みなみは実は仕事上必要なものくらいしか読まないし勉強しない。ただ、必要なものが多いから、読書家に見えているだけだ。
いつか、自分の化けの皮が剥がれるんじゃないか……。
みなみはいつも怯えている。
※ ※ ※
「樋口さん、そろそろ着きますよ」
篠井の声で目覚めると、あたりは真っ暗で山の中の道を入っていた。思わず、後ろを見ると、もう一台、渡海の車はちゃんと後ろを追ってきていた。しかし、それ以外は真っ暗闇だ。
「すみません、寝ちゃっていました」
「いいんですよ。僕が言ったんだし」
「すごい場所ですね」
「これでも、東京都なんですよ」
林を抜けると小さな集落が出てきて、その中の木造の一軒家に篠井は車を止めた。家は農家のような作りで二階建て、周りを竹林に囲まれている。広い庭があって、一部は畑のようになっていた。
「ちょっと待ってください」
篠井は運転席側から降りて、車の後ろに回り、懐中電灯を二つ取り出した。一つは後ろの車の渡海たちに渡し、一つの電気を付けて、助手席を開け、足下を照らしてくれた。
「ありがとうございます」
冷気がさあっと入ってきて、思わず、首をすくめた。夜の図書館のあたりだって十分郊外だし寒いけど、ここはまた一度くらい温度が低い気がした。
「真っ暗でしょう。気をつけて」
四人で懐中電灯の明かりを頼りに、農家風の家の戸口に立つと、篠井が鍵を出して、がちゃがちゃ音を立てながら引き戸を開けた。
ここ、東京らしいけど実家の方の雰囲気に近いわ、と乙葉は思った。乙葉の家は町中でマンションだったけど、友達の家にはこういううちがたくさんあった。
「倉庫ってここなんですか」
「はい。ここもオーナーが気に入って買った家の一つなんです。裏に倉もあるから、本を置けるだろうって」
「なるほど」
「一見、普通の木造だし、古いから湿気や何かが心配に思うけど、木材で建てた家で意外としっかりしているんです。とはいえ、オーナーはもう少ししたらちゃんとした倉庫を買って、そっちに移すつもりだとは言ってたけど」
「いや、それにしても冷えますね」
渡海が言って、徳田もうなずく。
「今、電気を付けますからね」
篠井が玄関の電気を付けると、ぱちんという音がしてあたりが急に明るくなった。思わず、ため息がもれる。それだけでも少しだけ温かくなってきた気がした。
玄関は土間になっていて、乙葉の寮の部屋くらいの広さがある。前の持ち主のものなのか、木製の鷹の像が飾ってあった。
篠井がまた引き戸を開けるとひろびろとした部屋があって、真ん中に囲炉裏が切ってある。
「いや、これは立派だ。旅館でもできそうだな」
これまで黙っていた徳田が言った。
「徳田さんも初めてなんですか」
「いえ、前に一度来たけど、その時は別館の方の蔵書を取りに来ただけだから」
「別館もあるんですか」
「ええ、この裏に離れがあるんですよ」
囲炉裏の部屋の隣に台所があって、その奥に客間のような日本間が二部屋続いており、段ボール箱が積み上げられていた。
「白川先生の蔵書はここです」
「うわ、これですか」
「まあ、とにかく、運んでしまいましょう」
「このままやりますか。さすがに寒すぎませんか」
徳田が口をとがらせて言う。
「じゃあ、まあ、ヒーターだけ付けますか。このヒーターは家をリフォームする時に間に合わせで付けたものらしくて、小さくてあまり利かないんですよ。もしかしたら、僕らが運んでいる時間くらいじゃぜんぜん暖まらないかもしれない」
それでも篠井がスイッチを探して入れた。ぶおーとおかしな音がして部屋の端に付いていたヒーターが動き始めたが、確かに、風が出てくるばかりで逆に部屋が冷えてきたような気がした。
「正子さんと亜子さんに聞いてきました。白川先生の箱は全部で二十三箱。すべて上と横に先生の名前が入っています」
「これですね」
乙葉は一つ見つけて言った。
「このあたりは、全部そうみたいです」
「結構あるね」
「作家としてはごく普通の量です」
そこからは、全員、黙って運んだ。乙葉には無理しないように、と言い、小さめの箱を回してくれたけど、それでも本の入った箱はみっちりと重かった。
部屋はいつまでも暖まらず、冷気が足下から上がってくるようですぐに身体が冷え切った。板の間の上を歩く時は、裸足でスケートをしているみたいだ、と思った。靴下一枚で来たことを後悔していた。
それでも、部屋と車までの往復を何度かして、三十分ほどで運び終わった。その頃やっと、ほんの少しだけ部屋が暖まってきたような気がしたが、もしかしたら、身体を動かしたからかもしれなかった。そのくらい、その家は底冷えした。
帰りは行き以上に無言だった。乙葉は、車の運転を代わりましょうか、と言ってみたけれど、篠井は自分がすると言って聞かなかった。
「郊外といえど、一応東京ですし、昨日出てきたばかりの人には酷ですよ。それに僕、運転はわりと嫌いじゃないです」
乙葉も地元では運転していたし、山道を攻めたことは何度もあるので、ハンドルさばきには自信があるのだが、それ以上は言わなかった。
一度だけ、コンビニの前に止まって交代でトイレ休憩を取り、温かいコーヒーを飲んだ。
「……どこか、ファミレスで軽く食べて帰りませんか」
渡海が提案したけど、篠井は首を横に振り、スマートフォンを取り出した。
そこには、正子からの何度かの着信とみなみからのショートメールが来ていた。「さっき正子さんにかけ直してみたけど、田村先生、もう限界に近いそうです」
「なるほど」
みなみのショートメールには、「あと何分で着きますか?」「コーヒーは嫌いだって言われました」とあり、それ以外にも何度か、泣き顔のスタンプが送られてきていた。
四人で顔を見合わせて、自然にため息が漏れた。
「事故を起こしたり捕まったりするわけにはいかないけど、できる限り急ぎましょう」
車に乗ってから先はさらに無言が続いた。図書館がある町の名前が道路標識に出てくるとほっとした。
「あ、一言、言っておきたいのですが」
図書館が見えてくると、篠井が言った。
「なんですか」
「あの家……今日行った、倉庫代わりの家ですが、本当はとても素敵な建物なんですよ。今夜はあいにくの天気だし、ただただつらい記憶になってしまうかもしれませんが、今度、天気のいい日に機会があったら行ってみるといいですよ」
「そうなんですか……わかりました」
今はその気にならないな、と心の中で思った。
図書館の入り口には台車を用意した三人……正子、亜子、みなみが待っていた。
「お疲れ様。もう、今か、今かと待っていたんですよ」
正子が言う。
「もう、あの人、応接室の中にいてくれればいいのに、図書館の中を歩き回って、『あいつ、くだらない本読んでやがる』とか、『売れもしない癖にいっちょまえに小難しい本を読みやがって』とか悪態つくし、カフェでは木下さんのメニューに難癖つけて喧嘩になりそうになるし……」
みなみがうんざり、という顔で言う。
「すみません、大変でしたね。僕ももう断ればよかった、と何度も思いました」
「まあ、黒岩さんが先生の後ろにぴったりくっついてくれていたからね。多少はましだったのかも」
「本当に申し訳ない」
篠井が深く頭を下げた。
「篠井さんのせいじゃないわよ。さあ、運びましょ」
亜子だけがほがらかだった。
まず、男たちが車から本をおろし、台車に乗せた。
「樋口さんは休んでていいですよ」と皆に言われたが、亜子の台車に乗せた二つの段ボール箱が少し安定が悪く、ぐらぐらしているのを見て、手を貸すことにした。
「私が押しますから、亜子さん、段ボールを押さえててくれますか」
「この段ボール、少し詰めすぎて膨らんでるから安定しないのね」
エレベーターで二階に上がって、応接室に入っていくと、すっかり疲れ切っている田村がだらしなくソファに腰掛けていた。
「やっと来たか……」
礼もない。その言い草には腹が立ったが、考えてみるとこのおじいさんは、昼間からここで待っていたわけで、疲れるのは仕方ないかもしれない、と思った。
亜子たちは黙って台車から段ボール箱をおろし、一つずつ、ガムテープを剥がして箱を開けた。
「ああ、ああ。それ、なんか、はさみ……いや、ナイフみたいなもん……」
厳重に貼られたガムテープに手こずっている亜子の姿を見て、先生はイライラと叫んだ。
「カッターですか」
みなみが無表情に答える。
「そう。カッターでさっさと開けられんのかね」
「本が傷つくかもしれません。大切な本が。そんなことはできません」
正子がきっぱりと言った。
さすがに、田村も黙った。
そんなに焦っているのに、田村は全部の箱が運び込まれるまで、箱を改めようとはしなかった。箱の横にずっと立っていた。
「これで全部ですが……」
篠井が最後の箱を開きながら言った。
「そうか。じゃあ、皆、出ていってくれ。あとは自分でやるから」
最後まで礼もなく、むしろこちらに恩を着せるように言った。
やれやれ、やっと終わった……皆にはどこかほっとした空気が流れた時だった。
「そういうわけにはいきません」
正子がきっぱりと言った。
「白川先生の本はまだなんの整理もしていません。冊数も数えてないし、索引や名簿も作ってない。ここから本が紛失しても私たちにはわかりません」
「……つまり、俺がここの本を盗む、と言いたいのか?」
「紛失、と言ってます。何かの折に、本が紛れ込んだり、わからなくなったりしたら、困ります」
「俺を疑っているんだな? 俺がこんなしけた野郎のしけた本を盗むような男だと」
「男か女かは関係ないし、紛失したら困る、と言っているんです。誰か一人でもいいから、ここにいさせてください」
「俺がお前たちから本を盗むから、見張っていたいってそういうことだな?」
田村が一言一言を発するたびに、その声は太く大きく低くなっていった。最後の方はほとんどヤクザものの映画のようだった。
でも、正子はまったくひるんでいなかった。痩せている正子にのしかかるように、大男の田村が声を荒らげても。
「だから、盗むなんて一言も言ってません。それから、ここの本が私たちの本というのも違います。ここにある本はすべて、作家という種類の人たちが遺した文化財で、国民の、いえ、全人類の宝です。もちろん、田村先生、あなたが本を遺されたら、その本もそうですし、そういうふうに扱います。私たちは作家というものを愛しているからです」
怒りで膨れ上がり、はち切れそうになっていた田村の顔が急に小さくなった。
「……じゃあ、お前。お前ならいていいよ」
正子を指さした。
「だけど、他はダメだ」
「わかりました」
篠井が何か言おうとして前に出たが、正子が首を横に振って止めた。
「私が先生のお世話をしますから、他の方は出て行ってください」
皆、ぞろぞろと……正子以外は応接室の外に出た。
「正子さん、すごいですねえ」
「さすがにパソコンがない時代から図書館司書をしていた人は気構えが違う」
渡海が頭を振りながら言った。
「それ関係ありますか」
「ありますよ。正子さんたちは自分の図書館の蔵書の名前や内容、場所を五千は覚えなきゃだめっていう時代だからね」
「へーえ」
受付に戻ると、黒岩が外から入ってきたところだった。
彼は乙葉たちに近づくと、親指で外を指さしながら「今、あの車の運転手……大先生の運転手に聞いてきたんですが」と言った。
そういえば、黒岩は段ボール箱を運ぶのは手伝ってくれていたけど、最後の方になったらいなくなっていたな、と乙葉は気がついた。
「なんか、わかりましたか」
「木下さんにコーヒーをボトルに詰めてもらって差し入れしたんです。先生のお抱えの運転手ではないそうですね。だけど、ハイヤー会社と契約して、必要な時だけ車を出してもらうようにしているみたいです。彼はよく先生に指名されているらしくて、わりによく知ってるみたいでした」
「そういう方なんですね」
「さすがにちゃんとしたハイヤーの会社なんで、口は堅いです。コーヒーくらいじゃ簡単にはしゃべらない。だけど、先生は普段、外出にはどこかの出版社の社員や編集者を秘書代わりに付いてこさせるってことは聞けました」
それがどう関係あるのだろう、と乙葉は思った。
「尊大で、顎で人をこき使って、鞄持ちさせて、ああしろ、こうしろとうるさいから、皆に嫌がられている。しかも、下手すると飯代やハイヤー代も出版社に払わせようとして、本当にケチなんだと。ハイヤー代は経費に回せるはずなのに、です」
話さないというわりに、よく聞いてきてるな、さすが元警官、と乙葉は感心した。
「だけど、今日は編集者を連れて来ないからびっくりした、って。よほど大切な用事か、誰にも知られたくないんだろうって言ってました」
「なるほどねえ」
皆、一同にうなずき合った。
「いずれにしろ、白川先生の蔵書はそれだけ大切なものなんですね」
篠井がつぶやいた。
「いったい、どういうことなんだろうなあ」
乙葉は自分で尋ねながら、答えが返ってくるとは思わずに言った。
「こっから先は、私にはわかりません」
黒岩が、篠井の肩をぽんぽんと叩いた。
「たぶん、あなたたちの仕事です」
「まあ、そうですね」
「私は念のため、応接室の外に立っていますね」
「あ、そうですね、お願いします」
黒岩の後ろ姿を見送った。
「さあ、これから何時間かかるかわからないけど、普段の仕事に戻りましょ。私と樋口さんは蔵書整理、他の方はお客様がいらっしゃる準備」
亜子が言って、皆、のろのろとうなずき合い、自分たちの持ち場に戻った。
乙葉は亜子と蔵書整理室に入り、昨日の仕事の続きをした。慎重に蔵書印を押し、亜子は本の記録を取った。
こつこつ、という自分が発する音と、亜子がメモをしたり、パソコンを叩いたりする音だけが部屋に響いていた。だけど、それはとても落ち着いている時間で、悪くなかった。
ふと顔を上げると、田村と正子を部屋に置いてきてから一時間ほどが経っていた。
「どうしているかしらねえ」
乙葉が壁掛け時計を見上げているのに気がついて、亜子も言った。
「正子さん、怒られたりしてないですかねえ」
「まあ、あの人は多少怒られたくらいじゃへこまないから」
ふふふ、とお互いに声を合わせて笑った。
「亜子さんは、正子さんとは昔からのお知り合いなんですか」
「ううん。ここに来てから知り合ったの」
「え。そうなんですか。仲がいいから、てっきり長い付き合いのお友達なのかと思った」
「違うの。だって、正子さんは大きな図書館の図書館員だったし、あたしは逆。静岡の駅前の小さな書店の店員だったんだもの」
「ああ、そうなんですか」
「正子さんはね、ばりばりよ。いわゆる……キャリアウーマン、っていうの? だけど、あたしは……煙草や新聞や文房具も一緒に売っているような、ちっちゃい店」
「あ、でも、それだけいろいろ扱っていると、逆に近所の人の動向とか、全部わかるんじゃないですか」
「そう。ご名答。コンビニなんてない時代だからね。どこの家の旦那さんがなんの銘柄を吸っているとか、どこの家のお子さんが何年生になったのか、とか、もちろん、本の好みもわかっちゃうし」
「お店って、ご家族とやっていらしたんですか」
「そーよー」
それって、ご両親? それとも旦那さんですか、と聞きそうになって、乙葉は口をつぐんだ。なんだか、それはちょっと踏み込みすぎな気がしたのだ。いずれにしろ、今、亜子がここで寮に一人で入っている、ということは、店にも亜子にも何かがあったに違いない。
乙葉が小さく息を呑んだ時、整理室の入り口が開いた。
はっと顔を上げると、正子が立っていた。
「正子さん!」
「大丈夫ですか」
正子がかすかにうなずくと、手招きした。
「……田村先生がね、皆に応接室に集まって欲しい、って」
「え」
「安心して。お礼を言いたいって言っているから」
亜子と顔を見合わせて、「よかったあ」と言った。
「私は他の人たちを呼んでくるから、二人は応接室に行ってあげて」
亜子と並んで部屋に入っていくと、そこにはすでに篠井がいて、田村から激しく熱い握手を求められていた。
「ありがとう! 君、本当にありがとう!」
「いいえ、そんな、どうも」
英語のシェイクハンドという言葉そのままに、彼は激しく上下に握手を振っていた。まるで、政治家の握手みたいだ……と乙葉は思った。
「君たちも、本当にありがとう。申し訳ない。私の非礼を許してくれ!」
田村の頬には涙の跡があった。
非礼はいいけど……なんというか、そういう激しいやつは勘弁して欲しい……篠井の手を握りしめているのを見て、乙葉は自然、亜子の後ろに下がった。
「本当に、感謝だ! 感謝する!」
でも今度はこちらに向かってきた。ひゃっと首をすくめたところで、亜子がきっぱり、「ありがとうございます。先生のお気持ちだけで結構です」と言って乙葉と田村の間に割って入った。それはやんわりとしているけど、きっぱりとした拒絶だった。
「そうか……?」
「謝罪には及びません。あたしたちは当たり前のことをしただけですから……本当にもうお気遣いなく」
そうしているうちに、みなみ、渡海、徳田たちも入ってきた。
田村は同様に皆にお礼を言い、深々と頭を下げた。
――悪い人じゃないのかもしれないけど……なんというか、良くも悪くも、激しすぎるんだよなあ。だったらもうちょっと前に改心して欲しい。
「ああ、皆、集まったかな」
田村は応接室を見回しながら言った。
「今日は、いろいろすまないね。大騒ぎをしてしまって、申し訳ない。ただ、これもまた、私の文学に対する愛情と思って欲しい。ええと、お礼と言ってはなんだが、これからもこちらのことは応援するし、こちらの篠井君にはすでに伝えたが……」
田村が彼の方に目をやる。
「私の蔵書はもちろん、寄贈するつもりだし、毎年、些少だけれども、こちらに寄付をさせて欲しいとお願いした」
篠井は横で、小さくうなずいた。
「じゃあ、そういうことで、また、何かあったら遠慮なく相談してくれ……」
「できたら、先生がこちらに来た理由を話してあげたらいかがですか」
正子が穏やかだけどきっぱりした声で言った。
「いや、それは……」
「先生がお帰りになったら、なんらかの説明を私からしないわけにはいきません。こんな騒ぎになったのですから……だとしたら、ご自分の口から説明された方がいいんじゃないでしょうか」
「そうか……」
田村は一瞬、迷った顔をしたが、すぐに「それもそうだ」と気を取り直したらしく、話し始めた。
「知っているものはいるかもしれないが、この白川君というのは私の唯一のライバルだったんだ。すばらしい作品を書く青年で、昔は時々会って、仕事や小説の話をしたものだよ……私は彼が本当にうらやましかった。彼の才能がねたましかった。だけど、そんなことは関係ないくらい、優しくていい人で、私たちは何時間も何時間も、安い酒を飲みながら話した。あんなふうに話せたのは同業者で彼一人だ」
田村はその頃を懐かしむように、微笑んだ。
「だけど、ささいなことから袂を分かってしまってね。それからはずっと音信不通だったんだ。どうせあいつは、俺のことなんて馬鹿にしているんだろう、ってずっと思ってた、だけど」
彼はちらっと正子を見て、彼女の視線を交わし、小さくうなずいて、また話し出した。
「今日、ここに来たのは、彼の蔵書がここに寄贈された、と聞いたからだ。私はもう決着をつけたかったんだ。ずっと彼にコンプレックスを抱いていて、本当は彼の方がずっとすごい作家だったんじゃないか、ずっと私を馬鹿にしてたんじゃないかって思うのはやめにしよう、って思った。私の本は最初の数冊だけは彼に寄贈していた。サインも書いてね。仲が悪くなってからは一切送ってない。もしも、私の本が一冊もなかったら、あいつは小さなやつで、私のことをうらやんで本を処分したんだろう、って思うことにした」
「それで……?」
篠井が尋ねながら、正子の顔を見た。正子は首を振った。それは「先生から話してもらいましょう」にも「本はなかったの」にも見えた。
「……本はあった。それも、私の本は全部、贈った本だけじゃなくて、これまで出版した本、全部……ちゃんと読んでくれてたんだ」
先生は泣き出した。腕で顔を隠し、涙をごしごし拭いた。
「自分がいかに小さな人間か……悲しくなったよ。なんで、もう一度、こちらから声をかけなかったのか……」
部屋の中には、田村のすすり泣く声がしばらく響いていた。
田村が白川の本を見終わり、自動車に乗って帰って行ったのが、ちょうど夜の十時くらいだった。
「お疲れ様でした」
自動車が門を通り抜けていくと、篠井が皆を振り返って言った。
「お疲れ様です」
乙葉たちも次々と頭をさげた。
「ありがとうございました」
「皆、疲れたでしょ」
「いや、まいったよねー」
思い思いに、皆、お互いをねぎらった。
「皆さん、夜食のまかないを食べに行ってください。僕、受付に座っていますから」
「いえ、今夜は私たちが受付にいるわよ。篠井さんたち、倉庫に行ってくれた組から食べたら」
正子が提案した。
「いえ、僕はまだ大丈夫です。お二人こそ、休んでください」
篠井がきっぱりと断った。
「食べなさいよ、篠井さん。今夜は全体に食事が遅れているから、木下さん、きっとイライラしていると思う。あたしはお弁当、食べるし」
亜子がさらに勧めてくれて、篠井、渡海、徳田、そして、乙葉で食事を取ることにした。
「……篠井さんが皆とご飯食べるの、初めて見るかも」
二階に上がりながら、渡海がこそっと乙葉にささやいた。
「そうなんですか」
「とにかく、レアだよ。いつも一人で行動する人だから」
「正子さんたちが勧めてくれたから?」
「それもあるけど、たぶん、本当に疲れているのかも」
亜子が言った通り、木下がカリカリしながら待っていた。
「今日は『ままや』の日なのにさ、皆、早く来ないからご飯余っちゃって、どうしようかと思ったよ。炊きたてを食べてもらいたかったのに」
「ままや……?」
尋ねたつもりだったのに、木下は答えず、さっさと厨房に入っていった。
四人でテーブルに座って互いの顔を見ながら、なんだか、居酒屋に来たみたいだ、と思った。だけど、飲み会と違うのは、誰も話し出さないことだ。前に座る篠井の顔色が白いのを見て、たぶん、自分も同じような感じなんだろうな、と思った。
「さあ、お待たせ」
木下がトレイを一つずつ持ってきて、皆の前に置いた。そこにはスープにおかずが二品、そして、オレンジ色のご飯……?!
「これ、なんですか」
「人参ご飯だよ! お代わりは何杯でもオーケー」
確かに、人参しか見えないくらい、ぎっしり人参が入ったご飯なのだった。
まず、スープに口をつける。ジャガイモを粗く潰したポタージュスープだった。派手さはないが、しみじみとした旨味が身体に染み渡った。大きなため息が出た。それは田村を前にした時のようなものではなく、温かい満足のため息だった。
次に人参ご飯を手に取った。
「……ああ、おいしい」
一口頬張って、思わず声が出た。人参の甘み、醤油の香ばしさ。なんて優しくて、おいしいご飯だろう。
「『ままや』というのは向田邦子さんが妹さんにやらせていたお料理屋ですよ」
篠井が人参ご飯を食べながら、言った。
彼はごくごく小さい一口分を箸でつまみ、咀嚼していた。ほとんど、表情が変わらないくらいしか、口も顔も動かさない。上品というより、とにかくちまちましている。
「そうなんですか」
「樋口さん、向田邦子さんの著書は……?」
「エッセイをちょっと読んだくらいですね。私、戯曲、シナリオを読むのが苦手で……エッセイ、すごくおもしろくて、もっと読みたいと思ってたんだけど、なかなか機会がなくて」
「新刊書の書店員さんはそうかもしれませんね」
渡海が、しかたないよ、というようにうなずく。
「新しい本で読みたい本、読まなくちゃいけない本がどんどん出てくるし」
思わず、言い訳のような言葉が出てしまう。
「しかし、これは何度食べてもおいしいな」
徳田がぽつりとつぶやいた。
「本当に。人参と油揚げだけとは思えない旨味ですよね」
「身体にもいいし」
「疲れた時はいいね」
おかずは蓮根のきんぴらとぶりのあらの煮付け。どちらもあっさりとした味付けで、ご飯に合う。
口々に話していると、木下がやってきた。
「なんだか、ひどい客が来てたな」
苦笑交じりに言った。
「ここにも来て、いろいろ言ってたらしいですね」
ご迷惑掛けてすみません、と篠井が謝った。
「あいつ……本に出てくるメニューを作ってるカフェなのに、なんで、あれはないんだ、これはないんだ、っていちゃもんつけてきてさ」
「そうだったんですか」
「いや、たぶん、あれは、自分の本の中のメニューが採用されてなかったから、気にくわなかったんだろ」
「ああ」
「こんな古い本、古い作家ばっかりで、どうしようって言うんだ、誰も読んでないだろ、とか、言ってたよ」
「本当に、失礼なやつ」
「まあ、自分の店……喫茶店の頃の客だったら追い出すんだけどさ」
木下はぽつりと言った。
「まあ、今は違うから我慢したさ」
「本当にどうもどうも、すみません」
篠井が立ち上がって謝った。
「いいって、いいって、篠井さんが謝ることじゃないし」
それよりもさ、と木下が言った。
「今日はずいぶん、疲れたんだろう? 閉館まであと一時間ちょっとだし……おいしい地ビールがあるんだけど、良かったら一杯ずつ、飲んでいかない?」
いたずらっ子のような顔で微笑んだ。
「え」
渡海が驚きつつ、篠井を見る。
「知ってるか? 『ままや』のコンセプトは女が一人でおかず……蓮根のきんぴらや肉じゃがで一杯飲んで、仕上げに一口ライスカレーが食べられる、そんな店だったらしい」
「へえ」
「まあ、女が一人で食べ物屋に入る、それも酒を飲むなんてなかなかしにくい時代だったからな。というわけで、それを忠実に再現するためには、アルコール一杯が必要なんだよ」
皆が、篠井を見た。
「いいですよ」
彼は苦笑いしていた。
「僕は飲みませんけど……そんなに飲めないので。でも、今日は大変な一日だったし、たまにはいいでしょう」
「やった」
「ありがとうございます」
木下が奥から、「とっておきの」地ビールを持ってきた。茶色い小瓶でラベルが凝っている。
三つのグラスを持ってきてくれて、それを注いでくれた。
「このカフェのメニューの最後に、地ビール、いろいろ、時価って書いてあるの、気になってたんですよね」
乙葉が言った。
「そりゃ、夜の図書館だよ。カフェにビールくらい置いてなかったら、名折れだよ」
「なるほど」
「これは、日本海側の酒蔵で働く若い女性たちが自分たちも新しいお酒を造ってみたい、って自ら志願して作った地ビールだよ。まだ始めて数年なんだけど、なかなかうまいんだ」
「へえ、女の人が」
「ちょっと酸味がある味で、人参ご飯にぴったりだと思う」
ビールは薄い茶色で少し白濁している。泡はあまり大きくない。
「いただきます」
ぐっと飲み干すと、さっぱりとしているけど、ほろ苦さと酸味がある味が口に広がった。
「これまた、身体に染みる」
渡海が感に堪えぬようにうめいた。
「本当。おいしいですね」
「今日は疲れたんだから、このくらいいいだろう」
木下がうなずく。
「……僕もやっぱり、一杯いただこうかな」
篠井がつぶやいた。
「あれ、篠井さん、飲めないんじゃ」
「そんなに飲めない、と言ったんです。まったく飲めないわけじゃありません」
「そう来なくっちゃ」
木下がグラスとビールを取りに行った。
「今日はめちゃくちゃ疲れたけど」
いち早くビールを飲み干した渡海がつぶやいた。
「あの先生、ちょっとむかついたけど」
「ええ」
「だけど……悪い気はしなかったな」
「わかります」
篠井が大きくうなずいた。
「あの先生が泣いているのを見て、この仕事やってて良かった、と思いました」
「うん」
「こういう時のために、この仕事はあるんだ。こういうことのためにオーナーはここを作ったのかな、と思いました」
古い図書館……作家の蔵書だけを置いた図書館……それはあまりにも型破りで、不思議な場所だけど。
「ここをいつまでも続けられるかわからないけど……それまで頑張ってやっていきましょう」
まだ飲んでいないはずなのに、篠井の目の縁がもう赤かった。