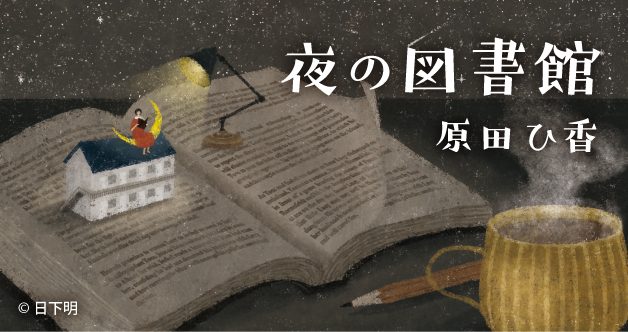樋口乙葉が「夜の図書館」に来てから、一ヶ月ほどが経った。
なんだか、ばたばたしてあっという間に過ぎたような気がする。だけど、仕事をしながら亜子や正子と話したり、食堂で徳田たちとご飯を食べたり、寮のみなみの部屋で映画を観たり……一つ一つの出来事がとても大きくて、自分がすでに長年、ここにいるかのような気もした。
映画は、亜子や正子も一緒に『若草物語』を原作にした『ストーリー・マイライフ』を配信で観た。皆、当然、『若草物語』も『続 若草物語』も読んでいるから、「ここ、原作と違う!」「こんなセリフ、あったっけ⁉」といちいちうるさかった。
「でも、『若草物語』の映像化の中では一番良かったかも」
さんざん文句を言ったわりに、正子は映画が終わるとそう褒めた。
その日は正子がコーヒーを、亜子が手作りのリンゴのケーキを持ってきた。みなみは部屋を提供してくれたので何も用意しなくていい、ということになった。乙葉も気を遣わないで、と言われたけど、ポテトチップスを買っていきたい、と申し出た。映画にはポテチだと思ったのだ。
そういう分担は正子と亜子がテキパキと決めてくれた。たぶん、二人は「女子会」をやり慣れているんだろうな、と乙葉は思った。女子会だけでなく、ママ友会や親戚の集まりも。女子会のベテランだ。そのくらい風格がある役割分担だった。
「一番と言うけど、正子さんが言うのは、あれでしょ。エイミーをエリザベス・テーラーがやったやつ」
亜子が笑った。
「あれとこれしかないか」
「そうよ。でも、確かに『続 若草物語』の部分の意訳はあの作品よりずっとよくできていたわね」
「子供の頃の気持ちを思い出した。初めて『若草物語』を読んだ時の気持ち。ジョーとローリーが結婚しなくて、すごく悲しかったの。あの二人に結婚して欲しかったから」
「わかるー!」
それには、乙葉とみなみも声をそろえた。
「なんで、結婚しないんだろう。私たちは二人が大好きなのに……二人の気持ちがよくわからなかったし、続の方で、ジョーがあの人を選んだ気持ちもよくわからなかった」
「そうね。でも、この映画であたしはちょっと納得できた」
「ええ、納得はできた……だけど、まだ、どこか心が痛むの。心がまた子供に戻ってしまった」
そう言いながら、正子が涙ぐんでいたので、びっくりしてしまった。いつもはどちらかというと何事にも現実的な正子の意外な一面を見た気がした。
「次は、『赤毛のアン』のドラマを観ませんか」
散々しゃべったあと、最後にみなみが提案した。
「『赤毛のアン』の映画は観たことがあるけど、あれとは違うの?」
正子が尋ねた。
「ええと……映画は二〇一五年に作られてますね……」
みなみがスマホを見ながら言う。
「いいえ、もっと前よ。あれ、すごく良かったのよね」
「あ、それ、もしかして一九八六年かな……」
「そうそう、そのくらいの時期だった」
正子たちはみなみが出した画面を見て、うなずきあった。
「これよ、これ。あたしなんか、劇場でアンが現れたとこ……駅のところでマシューを待っている、あの場面を観ただけで、胸がきゅーっと締め付けられて涙がぼろぼろ出てきちゃった。そのあとずっと泣きっぱなしよ。だって、あたしが想像していたアンの世界が目の前にそのまま現れたんですもの。本当によくできた映画だった」
ふっと、図書館に初めて登館した時、壊れたスーツケースを持っていたら、「赤毛のアン?」と篠井に言われたことを、乙葉は思い出した。
その時は一瞬驚いて、ろくな返事ができなかったけど、心の奥底で「この人は腹心の友かもしれない……」と少し安心したのだった。その後この図書館には腹心の友……つまり同じ本を読んで、同じような青春時代を過ごしてきたひとがたくさんいる、ということにすぐ気がついた。図書館員にも、お客様の中にも。
「それもきっといいと思うんですけど、新しく作られたドラマもすっごくいいんですよ。絶対、気に入ってもらえます。一度観てみてください」
じゃあ、来月はそれを観ましょう、ということでお開きになった。
友達にも会った。
幼なじみの佐藤愛菜は東京の大手町に勤める会社員なのだが、わざわざ電車とバスに乗ってやってきてくれた。
「へえ、あんがい、いいところに住んでるじゃん」
彼女は入ってすぐ、部屋を見回しながら言った。
「いいところ、って……いったい、どんなところに住んでると思ったの⁈」
乙葉は愛菜に、ポットのコーヒーを注ぎながら尋ねた。コーヒーは正子が淹れて、持ってきてくれたものだ。前日、仕事中に「明日、友達が来るけど、ろくな食器がなくて」とこぼしたら、正子が「じゃあ、私が差し入れるわよ。お礼はいいわよ」とマグカップとともに持ってきてくれた。
「このコーヒー、おいしい」
愛菜がそれをすすりながら褒めてくれたので、正子が用意してくれたことを説明した。
「……ちゃんとしてるんだ、職場」
「だから、どんなところに勤めていると思ってたの」
「だって、乙葉のおばさんがうちのママに『住み込みの夜の仕事だ。いったい、何をやってるのか』って泣いてたって聞いたからさ、てっきり」
「てっきり、じゃないよ」
「しかたないよ、うちらの実家のあたりで、住み込みって言ったらすぐにパチンコ屋を想像しちゃうもん。さらに夜の仕事とか言われたら」
「だから、図書館に勤めるってちゃんと言ったのに」
「たぶん、それ、信じてないと思う」
はあ、と深いため息が出た。
「心配してるんだよ、乙葉のおばさん。安心させてやりなよ」
「安心て。どうやって」
「ここに呼んで、東京見物でもさせたら」
「ここでどう東京見物するのよ! この山奥で!」
思わず、お互いに顔を見合わせて笑ってしまった。
「まあ、東京見物は無理でも、職場見学させればいいじゃん」
「……まあねえ」
しかし、あんなふうに言われた手前、「遊びに来なよ」とは素直に言いにくい。
「親孝行しなよ。一人娘なんだからさ」
「それは愛菜もそうでしょう」
彼女は地元の大学を出た後、東京の商社に勤めている。乙葉の地元ではエリート組の一人だ。だから、そんなふうに「親孝行しなよ」なんて、古くさいことを堂々と言えるのだ。
「次はうちの家にも来て」
彼女は住み込みなんかじゃなく、ちゃんとしたマンションを自分で借りて住んでいる。
「都会には恐れ多くて、なかなか行けませんわ」
冗談めかして答えたけど、引け目を感じたのは本当だった。
「何言ってるの? あたしが住んでる錦糸町をなんだと思ってんの。見に来たらわかるって。部屋の広さもほとんど変わんないし」
話しているうちにだんだん気持ちもほぐれて、結局、来月には愛菜の家に行くことを約束してしまった。
その翌日、蔵書整理室で正子と亜子とともに仕事をしていると、篠井が入ってきた。
「すみません。ちょっと、こんなものが……」
彼は手に文庫本を持っていた。
「なんですか」
正子と亜子は机でパソコンに向かって、本のデータを打ち込んでいた。乙葉は新しく来た本を段ボールから出して、二人の脇に積んでいたところだった。
三人で篠井の手元をのぞきこんだ。
「どうしたんですか」
「これ、見てください」
「あ」
彼が文庫本の裏表紙を広げると、思わず、三人からそろって同じ声が出た。
そこには何もなかった。真っ白だった。
「蔵書印は?」
正子が慌てて言った。
「それなんです。ないんです」
「これ、どこで?」
「今、お客様が持ってきてくださったんです。一階のどこかにはあったんだけど、どこから出したのか、いろいろ見ているうちにわからなくなってしまったって。棚に戻そうとした時に蔵書印がないことに気がついた」
「そのお客様は?」
「もう、帰られました。受付によると『これ、一階にあったよ。蔵書印がないよ』と言って、さっと帰られたそうです。榎田さんたちもびっくりしてしまって、それ以上話を聞けなかった、と」
「まあ」
「でも、一階なのは確かだと」
「どういうことでしょう。なんで蔵書印を押してないんでしょう」
乙葉は皆の顔を見回しながら尋ねた。
「……まったくわからない。ただ単に押し忘れたのかもしれないし」
「でも、蔵書は判を押す時、記録する時、本棚に並べる時と、少なくとも三回は別の人間が目を通すわけです」
篠井が首をかしげながら言った。
「普通、忘れることはあり得ないと思いますが」
「でも、人間のすることだからわからないわ」
「年に一回はこの図書館の中の蔵書整理があるし」
「ええ。まだ、一年を過ぎてない本なのかも」
「比較的新しいということですか」
「ええ」
「あと、これはあまり考えたくないことですが、もしかして、誰かが蔵書を盗っていって、その代わりに差しておいた、ということも……」
「ありえるわね」
正子がうなずいた。
「ここにあるものは、価値のない人にはただの古本だけど、ファンからしたら唯一無二のものだし」
「そうですね」
うなずいてから、乙葉は「あ」と気がついた。
「でも、ここの本は持ち出せないんじゃなかったですか⁈ 本を持って、一歩でも出たら、警報が鳴るって……出入口にも大きく書いてありますし」
すると、篠井と正子、亜子は困ったように顔を見合わせた。
「……あなた、まだ話してなかったの? 乙葉さんに」
「あ、ええ。でも別に隠していたわけじゃなくて、言い忘れていただけです」
「どういうことですか?」
「……実はそれは嘘なの」
「まさか」
「だって、ここの本は蔵書印を押しただけで、そのまま並べられているでしょう? 最近の図書館のように磁気テープを挿入してラミネート加工したりしていない」
「確かに」
「余計なことをしてしまうと、本の風情が失われてしまう……その作家が持っていた時の味わいがなくなってしまう、とオーナーが嫌がってね」
「それに、手間もお金もかかります」
篠井が現実的なことを言った。
「私もおかしいと思ってたんですよね。あれがないのに、どうやって管理しているのかと」
「だから、とりあえず看板を出して、さらに入口で重々、釘を刺しておき、図書館探偵さんに来ていただくことで様子をみましょう、さらに盗難が続いたら、別の方法を考えましょう、ということになって」
「そういうことだったんですね」
仕組みを今まで教えてもらえてなかったことには少しショックを受けたが、まあ納得できた。
「とにかく、なぜ、これがここにあるかを考えるのが先決ですよね」
「でも、盗まれたというのは考えすぎかもしれない。だって、盗んだんだとしたら、ただ持って行ったんじゃなくて、なんで別のものを置いていったのか、わからない」
亜子が本をじっくり見ながら言った。
「それに、普通の人なら、持ち出し不可だと思っているはずで、持ち出しても大丈夫だと知っていた人の可能性も……」
そう言いかけた亜子は途中でやめて首を振った。たぶん、ここにいる人間を疑いたくないのだろう。
「でも代わりがあれば、なくなったことに気がつきにくいですから」
「とはいえ蔵書整理やチェックでわかってしまうでしょ」
「でも、そういうことをしているって知ってるのは、一部の人間ですよ。ここにいる人だけ」
「いずれにしろ、どこから手をつけましょうか」
「まずは、チェックよね。同じものが何冊あるか。そして、どれが抜けているのか」
乙葉は本の表紙を見る。太宰治の『女生徒』だった。
「これ……かなりたくさんあるやつじゃないですか」
「正直、ほとんどの作家さんが一度は読んでいる、と言っても過言ではない」
「では、とにかく、ア行の作家さんから一つずつ探していきましょう。持っている作家さんはイントラネットで検索できますから一つずつ探していけばいい」
篠井が乙葉を見た。
「正子さんと樋口さんがやってもらえますか」
「私一人でもできますよ」
乙葉は言った。
「ええ、でも、二人で確認していただいた方が確かですから、念のため」
「了解です」
「あと、僕は図書館探偵の黒岩さんに連絡して、相談してみます。必要なら来てもらいますね」
「よろしくお願いします」
乙葉は正子とともに二階に上がった。
※ ※ ※
私は本が読めない。
正子は、乙葉の横で太宰治の『女生徒』を一冊ずつ確認しながら思う。
乙葉はノートパソコンを片手に『女生徒』を所持していた作家を探し、「次は鮎川夏夫先生です」とか言ってくれるので、正子はその作家の棚から『女生徒』を探すだけだ。ノートパソコンを持ったまま作業するのは大変だろう。何度か、交代を申し出ても、「大丈夫です!」と乙葉は笑顔を見せた。彼女はこういう時、少しでも負担の大きい仕事を進んでやってくれて、とても助かる。本当にいい人が来てくれてありがたい、と思う。
そんなことを感謝している間も、頭の片隅では考えてしまう。
わたしは、ほんが、よめない。
こうして働いている時ばかりではない。
朝起きた時、コーヒーを淹れている時、飲んでいる時、ここに来て若い人たちと話し思わず爆笑した時も。
わたしは、ほんが、よめない。わたしは、ほんが、よめない。もう、よめない。ずっと、よめない。
片時も忘れることができない。
自分がもう本を読めないこと。
ただただ、無心に本を読み、まわりの音が聞こえないほど熱中し、別の世界に連れて行かれ、そして、数時間後、すべてを読み終えた時には、ぽんっと世界から放り出されたようなあの……さみしくも充実したあの時を。
私はもう二度と味わうことができない。
字が読めない、ということではない。字は読める。ちゃんと読んで理解することもできる。ただ、以前のように熱中してすべてを捧げるようにして本を読むことができないのだ。読んでも最初の数ページだけ。
なんとか、何日もかけてやっと一冊を読むことはできなくはない。だけど、喜びはほとんどない。ただ、徒労感があるだけ。あと、私は頑張れば本を読むことができるのだという安心感だけだ。
読めない、と気がついたのは六十歳になった頃だった。今から十年あまり前だ。
最初は認められなかった、というか、気がつきさえしなかった。
長年、図書館員をしていて、図書館に山ほど本があると言っても、自分で本を買わないわけではない。いや、むしろ、他の人よりたくさん買った。手元に置きたい本はたくさんあったし、新しい本もたくさん読む。気に入った本をくり返し読むのも大好きだった。
だけど、ふと気がつくと、家に読んでいない本が溜まりだした。本屋に行ったり、人から聞いたり、テレビで観たりすると欲しくなって、すぐに買ってしまう。だけど、数ページ読むとなんとなく投げ出してしまって、それは部屋に積み上げられていく。
ただ疲れているのだ、時間がないのだ、忙しいのだ、と思っていた。だけど、数年かけて、やっと認めることができた。
これはもう、何かがおかしい。何か、前とは違うことが起こっている。いつか暇になれば、いつかまとまった時間ができれば読めるというものではないのだ。
私は本が読めないのだ、と。
正子は東京の下町に生まれた。父は普通の勤め人で、母は専業主婦という家だった。兄と妹がおり、兄は国立大学に入って正子と妹は短期大学に行った。正子は成績が良かったので四年制大学にも行けないことはなかったが、当時はそれが普通だった。短大に行かせてもらえただけでもありがたかった。図書館司書の資格を取って、試験を受け就職した。正子がいたのは東京都内の公立図書館だった。きちんと都の職員の図書館員として採用された。けれど、それはやはり「腰掛け」というようなイメージで、正子自身もまわりも、数年……遅くとも三十になるまでには結婚して退職するのだ、という気持ちで勤めていた。
父は堅物で家でも威張っていたけれど、昨今問題になっているような暴力や暴言を吐くような父親ではなかった。晩ご飯の時、父のメニューには一品、酒の肴……刺身や焼き物が多かったり、父には誰も口答えはできないような程度のことだった。無口で子供への気持ちを表すのが苦手な人でも、休みのたびに遊園地や繁華街、温泉なんかには連れて行ってくれた。時代的には、まあ、子煩悩と言われてもおかしくないかもしれない。
ところがその父が正子が就職する頃と前後して、突然、浮気をしたのだった。相手は飲み屋で知り合った人で、なぜ発覚したかというと、父がその女の家に入り浸って帰ってこなくなったからだ。そのこと自体も驚きだったが、さらに衝撃だったのがこのことで六十近い両親が離婚をしたことだった。父が多少、浮気をしても、母は我慢するだろうと勝手に思っていた。だけど、一年ほどで離婚した。父が離婚したいと主張したこともあったし、母もなぜか、あまり強く嫌がらなかった、らしい。ただ、こういうことも話し合いはほぼ二人だけで行われており、子供たちはあとから「離婚する」とだけ聞いたのだった。
当時、兄は役所に就職して結婚し、夫婦で地方勤務になっていた。自然、正子と妹が母と暮らし、兄はその後も地方を転々としていた。子供がいることもあり、母との同居は結局、母が七十で亡くなるまで続いた。
正子は母を養い、妹を短大にやって嫁がせ、気がついたら自分の婚期を逃していた。兄に多少は金銭的援助をしてもらったけれど、それ以上は期待できなかった。何より、それを母が嫌がった。母は離婚を恥じ、兄や嫁、嫁の実家に引け目を持っていた。自分が原因の離婚ではなかったはずなのに、離婚そのもので母は己を恥じていた。すぐに離婚に応じたのも、夫に気移りされた自分を恥じたためかもしれなかった。その気持ちがどこかわかるだけに、正子も兄への援助の求めを言い出しにくかった。
母が死んだ後、女と別れた父の介護も、結局、正子がした。あまりに理不尽だと思いながら、自分しかそれをする人はないのだ、という諦めがあった。それでも、勤めをやめずに済んだのは、まだ幸いだったと今は思っている。
死に際、父が「母さんがあの時もっと反対してくれたら」とぽつりと言った。きっと離婚のことだろうと思ったけれど、聞こえないふりをした。なんて、身勝手なことを言うんだろう、と内心あきれた。
正子が働いていたのは、都内の中心的な役割を担う図書館だった。就職当時はまだコンピューターは導入されておらず、紙のカードで本は整理され、分類されていた。
正子が配属され、人生のほとんどを過ごし、最後には主任まで務めたのは「相談係」……つまりリファレンスの係だった。
一番多い時には常時二十名の職員が配属されていて、朝から晩まで、利用者の質問に答えるのが、その仕事だった。窓口と電話というのが当時の主な手段だった。
質問の内容はさまざまで、電話口で突然、詩の一節をつぶやかれて「これの作者は誰?」と聞かれたり、「江戸時代、遊郭の避妊事情がわかる本はないか?」だとか、「一九二四年の五月十日は何曜日で天気は?」だとか、「昨年の経済白書はそちらにあるか?」だとか聞かれたりした。
そう、それはまさに現代のグーグルで、今だったら簡単に「ググれよ」と言われるようなことが図書館に大量に持ち込まれたのだ。それは、多い時には、窓口百件、電話二百件というような数で、一日が終わった時には頭の中がしびれるほど疲れた。
昭和八十年代半ばからはポツポツとコンピューター・システムが入り、デジタルで情報を処理し始めたが、正子が働き盛りの頃はその過渡期で、図書カードとパソコンを両方操って情報の海を泳いだ。
入館当時、先輩には「一人五千冊は覚えられる、ここの人間は一万冊覚えろ」と言われた。利用者に「なんのなにがしの本はどこ?」と聞かれたら、一瞬で「あそこにあります」と答えられるようにしろ、ということだった。
必死で働いたし、必死に覚えたし、必死に本を読んだ。
そして、やっとゆっくり本が読める、じっくり自分のために読める、と思った時……正子は読書を失っていた。
少し前、小説家の田村淳一郎が来て白川忠介の本を見たいと主張した時、白川の小説を読んでいる、と言ったのは嘘ではない。白川は寡作だったし、文芸誌に一年に一回くらい、百枚程度の小説を書くだけだったから、掲載された時はゆっくりと時間をかけて読んだ。それでも、昔のような、心が躍るような喜びはなかったけど。
人間失格……読書人間失格だ。ふっと、『女生徒』の隣にある本を見て思った。
「正子さん、どうですか? ありましたか?」
乙葉に話しかけられて、正子は我に返った。
「鮎川先生の『女生徒』はあったわ」
正子は『女生徒』の裏表紙の蔵書印を確かめながら言った。
「よかったです。次行きましょう……あの、私、ちょっと思ったんですけど」
乙葉はこわごわという感じで口にする。
「これ、本当にこの『女生徒』だけを調べればいいんでしょうか」
「え、どういうこと?」
「つまり、もしも、誰かの本を盗っていって、その代わりにこれを置いていったというのなら、まあ、ある意味簡単ですけど、じゃなくて、とりあえず、同じくらいの厚さ、同じくらいの同じ作家の本ならわからないだろう、ということで置いていったなら、すべての太宰の文庫本を調べる必要があります」
「……なるほど」
「あと、もっと恐ろしいのは、太宰でさえない、という可能性です。ここにあるものを何か盗っていって、代わりに差していったという……」
「でも、ただ単に、私たちの押し忘れかもしれないし、ただ単にいたずらかもしれない」
「そうですね。それにちょっと思ったのは、まったく悪意なく間違えたということもあるかと」
「ああ」
「たまたま、これを読もうと思って家から鞄に入れて持ってきていて、何か別の本をここで見て、取り違えて持って帰ってしまった……とか」
「それ、私も考えた。だって、盗るならただ持っていって、なんらかの方法でここから持ち出せばいいわけだから」
ここを出る時はバッグの中を調べる。でもバッグを開いて簡単に黒岩か北里が中を見るだけだから、本当に盗るつもりで下着の中に忍ばせたりすれば、絶対に盗られない、という保証はない。
ただ、有名作家の部屋……数年前に寄贈された海藤亮一などの場所は厳重に保管され、そこにはバッグやコートの持ち込みはできない。美術館と同じように必ず、一人は誰か図書館員が座っている。あそこから盗るのは少しむずかしい。
「でも、私はここというより、あの有名作家の部屋のところの方があやしいと思うの。ここなら、代わりの本を一冊入れなくても気がつかれない可能性もある」
「ですねえ」
「とはいえ、一度はちゃんと調べないとね」
「どこまでですか」
「……とにかく、今は『女生徒』よ」
乙葉は素直にうなずき、元の作業に戻った。
そういえば、あの頃だっただろうか。今の人間が一週間に浴びる情報量は、ヴィクトリア王朝時代の人間が一生関わる情報とほぼ同じだ、というような話を聞いたのは。この手の話というのは、いつもころころと変わる。一日の情報量が江戸時代の一年と同じ、または平安時代の一生と同じ、だとか……。
だとしたら、優れた小説を書くのに情報量なんてあまり必要ないと言える。いや、紫式部の情報量が今より少ないなんて、私たちが考えるのは傲慢だ。きっと彼女たちは中国文学をたくさん読んでいただろうし、御所の中であの人がどうしただとか、この人が前に詠んだ歌はどうだったとか、噂ばかりしていただろう。
情報量のことを教えてくれたのは誰だったっけ? ああ、そう、あの人だ。一時期、ほぼ毎週のように通ってきてくれた……。
最初は電話だった。戦前の家計調査に関する本について聞かれた。始終、イライラした調子で、私が「国会図書館にはお聞きになりましたか」と尋ねると、「調べたに決まってるでしょ、なかったから聞いている」と言い返された。正直、こちらもむかっ腹を立てながら、でも、口調は穏やかにうちが所蔵している資料について話していたら、だんだん落ち着かれて、最後には「ありがとう」と言われた。
翌日、直々に受付に来られて、名前を呼ばれお礼を言われた。質問した資料については、自分の担当教授に当たる人から探すように言われて焦っていたからつい、あんなふうに対応してしまったと謝られた。若い、社会学の研究者だった。それから、何度か窓口に来られて、そのたびに対応した。私が忙しそうにしていると近づかないで、私が空くと嬉しそうに寄ってきた。袖口のすり切れた、だけど、いつもきれいにアイロンのかかった青いシャツを着ていた。清潔そうな人だと思った。
一度だけ、「コーヒーでも飲みませんか」と言われた。いや、「お礼にコーヒーをごちそうします」だったかな。少し考えて、「いえ、結構です。仕事がありますから」と答えた。それから、あまり来なくなってしまった。
今でも時々、思い出す。あの時、コーヒーを飲みに行っていたら、自分の人生は変わっていたんだろうか。
コーヒーの人は一緒に棚のところで本を探している時に、人の情報量について教えてくれたのだった。こんな話がありますけど……と。あなたが一日に触れている情報量はいったい、平安時代の人の何人分なんでしょうか、とか言われたんだっけ。
コーヒーを断ってからぷっつり来なくなって、一年後、久しぶりに来てくれた時、嬉しかった。そして……。
「助教授になることになりました。あなたのおかげです」と言われた。嬉しくて、胸がいっぱいになって、「おめでとうございます」としか答えられなかった。
あの時、「よかったら、お祝いにコーヒーでもいかがですか」と言っていたら。
そう何度も考えた。それから何年も、何度も何度も。
それが私の人生の二回の後悔。二回のコーヒー。飲まなかったコーヒー。
図書館退職間際のことだった。「2ちゃんねる」の図書館に関するスレッドについ書いてしまったのだ。そのスレは図書館員ばかりが集まっていて、比較的穏やかだった。深夜だったし、過疎化した場所でもあった。
自分は本が読めなくなっていること、自分のようなものが図書館の仕事に携わっていいものか迷っていること、そして、今後の人生が不安なことを……。すると、不思議な返事が書き込まれた。
――拝啓、いつもあなたのレスを拝見しております。わたくし、ハンドルネーム、スリーカラーストーン、と申します。このたびの本に関するあなたの一連のレスも読み、感銘を受けました。あなたのような方に手伝っていただきたい仕事があります。よろしければ、ご連絡いただけないでしょうか。
そこに書かれたメールアドレスは使い捨てで、「夜が明けたら消去します」と記してあった。
あの時、何事にも慎重だった自分がなぜあのあやしいメールに従って返事をし、さらにスカイプで面接を受け、さらに、顔もわからない彼(か彼女かわからない)の勧める「仕事」についたのか……ただただ、驚くことばかりだ。
だけど、今も自分はここにいる。
「……正子さん、ない本はないみたいですね」
乙葉がつぶやいて、またはっとする。
ない本はない……なんだか、不思議なパラドックスのように聞こえた。
※ ※ ※
「じゃあ、やっぱり、有名作家のところに行かないと」
本棚の前にしゃがみ込んでいた正子が言った。
「あそこは厳重だから盗って行くのはなかなかむずかしいと思います。お客様は一階だったと言ってたらしいですし」
「ええ、私もそう思うけど、一応、調べないとね」
有名作家の部屋……それはこの図書館ができて、海藤亮一の本が最初に入った時、作られたそうだ。
それまで、作家ごとにあいうえお順に並べられていたのを、一階の一角に個室を作り、「海藤亮一」だけを別にした。その後、人気の高い作家さんの本棚が少しずつ増えていって、さらにそれらを二階の広い一室に移し、入口に必ず誰かが座っているようにした。
「ちょっと疑問だったんですけど、有名作家の部屋と一般の書棚との差ってなんなんですか。何を基準に分けているんですか」
「まあ、基本的には賞を取っているか取ってないかくらいだと思うけど、あとは人気と実績よね。だいたい、篠井さんが決めている。たぶん、篠井さんはオーナーと話し合っているんじゃないかしら。でも、それで特に困ったことはないし、お客様からも苦情みたいのはないから、そのあたりの判断は今のところ当たっているんじゃない」
正子がオーナーという単語をさらりと出したので、乙葉はそれに乗じて尋ねた。
「でも、篠井さんはオーナーとは会ったことないって」
「会ったことはないかもしれないけど、電話やメールで話しているんじゃない?」
「ああ、そうですね」
そして、少し遠慮がちに尋ねた。
「……正子さんは会ったことあるんですか? オーナー」
「ないっ」
彼女の答えは少し早すぎるような気がした。これがミステリー小説なら、嘘の可能性が高いのだが……果たして正子の場合はどうなのか。
「正子さんでも会ったことはないんですか」
「入館した時はメールが来て、スカイプで話しただけ」
「私と同じです。私はzoomでしたけど。正子さん、スカイプ使えるんですか」
「もちろん。私は前の図書館で、インターネットに関わったのよ。普通の人より、わりにパソコンに触ったのは早いほうよ」
「すごっ」
「ふふふ。若い人って、年寄りはパソコンは使えないものだと決めつけてる」
「すみませんでした!」
階段の途中で頭を下げてしまった。
「冗談、冗談」
二階に上がって、食堂や応接室とは反対側の部屋に入った。
入口のところに徳田が座っていた。
「あ、正子さん、樋口さん」
「太宰の本を調べにきたんだけど……」
「聞いてます。だから、自分も一応、調べてみたんですけど……」
徳田は部屋の中を見回した。
「今のところ、なくなっている太宰の本はないです」
「そう……私たちにも、もう一度確認させてもらえる?」
徳田が一瞬、不満そうな顔をした気がした。唇を引き締めて、何かを言い返そうと。だけど、相手が正子だからか、何も言わなかった。
「こういうことは複数で確認した方が確実だからね。徳田さんを信用していないということじゃないのよ。ごめんなさいね」
正子はにこにこしながら、徳田に謝った。
「もちろん、わかってます」
「じゃあ、調べるわね」
乙葉と正子は太宰の本を持っている作家を端から調べていったが、どの本もそろっていた。
「本当にないわね」
「でしょう?」
徳田は得意げに言った。
客がいなかったからか、徳田はずっと二人の後ろについてきていた。正直、かなり彼の「圧」を感じたし、ちょっとウザいなと思ってしまった。
「さすが、徳田さん」
でも、正子は振り返って、すぐにそう褒めたので、徳田も不意をつかれたのか、思わず笑顔になった。
正子さんてすごいなあ、ちょっと気難しい徳田さんの扱いも心得てる……乙葉は感心してしまった。
「さあ、どうしようか」
有名作家の部屋から出たあと、正子がつぶやいた。
「とりあえず、なくなった『女生徒』はなかった、ということで篠井さんには報告しておくね」
「はい」
結局、篠井と正子が話し合って、その『女生徒』は忘れ物として、しばらく、受付の後ろの棚の『お忘れ物箱』に入ることになった。
『女生徒』を探したあと、乙葉は食堂に行った。
「今日の夜食は何ですか?」
乙葉は席に座りながら尋ねた。他の人とは時間がずれてしまったので、カウンターに一人で座った。
「今夜は『赤毛のアン』ナイト」
「あ、いいですね。でも、『赤毛のアン』の中に食べ物の話って、意外とあるような、ないような?」
乙葉は首をひねった。
「アンがバニラ・エッセンスと間違えて痛みどめの薬を入れてしまったのは、ゼリーをはさんだレヤー・ケーキだし、ダイアナが学校に持って行ったのはきいちごのパイでしたよね? スイーツのイメージはたくさんあるけど」
木下はすぐに奥に引っ込んで、平らな一皿を持ってやって来た。白い皿を乙葉の前に置く。
「サンドイッチ!」
そこにあるのは、一見、ごく普通に見えるサンドイッチだった。きちんとパンの耳を落としたもので、とても品が良い。
「そうだよ。赤毛のアン・シリーズに出てくる食事も作って欲しいって言われてさ、俺は『赤毛のアン』と『アンの青春』と『アンの愛情』なんかを読まされたんだよ。それから、オーナーから『赤毛のアン』の料理に関する本がどっさり送られてきた」
「へえ」
「『赤毛のアンのお料理ノート』『赤毛のアンのクックブック』『「赤毛のアン」の生活事典』『赤毛のアンの世界へ』……原作以外に六、七冊読んだんじゃないだろうか」
「うわあ」
「大変だったよ。それでも、これっていう料理はなかった、というのが本当だ。焼き鶏(やきどり)や塩漬けの豚肉を野菜と煮込んだ料理とか、レタスのサラダとか……シンプルな料理ばかりだった。原作にはほとんど作り方なんて書いてないしな」
「で、どうしたんです?」
「『アンの青春』の中に変な話があるんだよ。知ってる? アンの家に有名な作家が訪ねてくることになって、皆でごちそうを作って待っているんだけど、結局現れなくて……」
「ありましたね! ごちそうはぐちゃぐちゃになっちゃうし、人から借りたお皿は割れちゃうし」
「そうそう。それで同じ皿を持っている人の家に行って譲ってもらおうとすると、その人は外出していて……」
「さらに大変なことになるんですよね」
「ああ。だけど、家主が帰って来て、お茶を淹れてくれて、『パンとバタときうりしかないんですが』って言われて……でも、そのパンとバターときゅうりは、アンもダイアナもお腹を空かしていたからとてもおいしかった、って。実際、本当においしそうなんだよな。俺、あんまり、『赤毛のアン』に詳しいわけじゃないし、小説ってものがわかるわけじゃないが、あのシーンがあの小説で唯一と言っていいほど、素直においしさを表した場面……特に食事についての喜びを表した場面じゃないかと思う」
「なるほど。確かにそうかもしれません」
「いろいろ考えたんだよ。もしかしたら、あのきゅうり、本当はピクルスのようなものじゃないかとも思った。だけど、他の訳を読んだりしても、あそこはパンとバタと、キューカンバーとしか書いてないようだ。生のきゅうりをがりがりかじったとも思えないんだが……というわけで、自分なりに考えたのが、これ。パンとバターときゅうりのサンドイッチ。それから、さすがにそれじゃ、寂しいんで、ローストチキンを使ったサンドイッチも作ってみた。きっと、彼女たちも食べただろうからね。さあ、どうぞ」
「ありがとうございます。いただきます」
柔らかくて白いパンに緑色のものがはさんであった。一口食べると、確かに、きゅうりの味と、バターの味が口の中に飛び込んできて、シンプルながら味わい深い。
「木下さん、これ、本当においしい。パンとバターときゅうりだけとは思えないくらいおいしい」「ありがとう。きゅうりは薄切りにしたものを塩もみしただけではさんだよ」
次にローストチキンのサンドイッチを頬張る。
「これもおいしいなあ。チキンがしっとりしてる」
「チキンは鶏胸肉をシンプルに塩と胡椒でローストして、フレンチドレッシングで軽く和えてはさみました」
「どれも素朴なお味ですね。でも、素材の旨味が感じられる」
「たぶん、あの時代はそういうものだったと思うよ。あと、きっと質素な牧師の妻だったモンゴメリは今の小説家みたいに、ながながと食べ物の味を書き込むようなことは好きじゃなかったのかもしれない」
「なるほど」
サンドイッチの皿には小皿がのっていて、そこにはグリーンピースが添えられていた。
口に入れると柔らかく茹でられたグリーンピースで、バターの風味がする。
「それはグリーンピースのバターソテー。仕上げに砂糖を一さじ入れてみた。ほら、モーガン夫人をグリーン・ゲーブルズに呼んだ時、アンたちが砂糖を入れすぎて、台無しになったの覚えている?」
「木下さん、ほんと、よく読んでますね。私より、じっくり読んでる」
「いや、食べ物が出てくるところだけ。メニューを作らなきゃならないから、必死で読んだ」
いつものように、食後にコーヒーを淹れてくれて、それにはまた小皿にのったものが添えられていた。茶色で少し大きめのサイコロの形だ。
「木下さん、これ……?」
「チョコレートキャラメル」
「え。これが? アンのチョコレートキャラメルですか⁉ 彼女がずっと食べたいと思っていた?」
「そう」
「いや。子供の頃、いったい、どういう味なんだろう? ってずっと思ってたんですよ。森永のチョコボールのキャラメル味を食べた時に、これがチョコレートキャラメルかなあ? でも、日本にあるものとは違うだろうなあ、って」
乙葉はそのチョコレート色の四角いものをつまんで口に入れた。
口に入れたそれはほろほろと崩れつつ、後味にねっとりとしたキャラメルとチョコレートの風味が残った。少し前に流行った生キャラメルのチョコレート味に近いが、ミルクの匂いがとてもよかった。
「おいしいっ!」
乙葉は思わず、木下の方を向き直った。
「木下さん、これ、売りましょうよ! ここで! 『赤毛のアンのチョコレートキャラメル』って名前で! いや、ネットで売ってもいいな。絶対、売れますよ!」
「やだねえ。それ、どれだけ手間がかかると思う? 俺、今日は普段より一時間前に来て、ずっと鍋をかき回していたんだから」
木下は手首をぐるぐる回しながら言った。
「え。そんなに手間のかかるものなんですねえ」
「そう。結構大変なんだよ」
「でも、また、時々、作ってくださいね」
「そんなに気に入ったかい」
「はい」
すると、木下はもう三つ、皿に入れて出してくれた。
「あ、ありがとうございます。これ、二つ残して、正子さんと亜子さんにもあげていいですか。きっと二人も喜ぶと思う」
すると、木下はさらに二つ、足してくれた。
蔵書整理室に戻って、正子と亜子に、二つずつ、チョコレートキャラメルを渡した。木下の話を伝えながら。
「甘くておいしいわね」
「本当」
二人とも嬉しそうに、それを頬張り、亜子は温かい緑茶をわざわざ淹れ直してくれた。
「実はあたしも作ったことがあるの、チョコレートキャラメル。二回」
亜子が言った。
「え? そうなの?」
「最初はずいぶん昔よ。もしかしたら、木下さんのこれと同じレシピかもしれないわ。あたしも『赤毛のアンのお料理ノート』っていう本を見ながら作ったから。確か、四十年以上前の本よ」
「え、そんな前に?」
「まずはタフィを作るの。大変だったわ。材料もいろいろそろえなくちゃならなくて……コンデンスミルク、バター、砂糖、水飴なんかをね」
「木下さんも大変だったって言ってました」
「それを量って、鍋で煮てね、一時間くらい煮詰めていくの。茶色くなるまで。ほら、『赤毛のアン』の中にもアンとダイアナが作って、焦がしたっていう記述があるじゃない? あれよ」
「はい」
「台所中がコンデンスミルクと水飴でべたべたになってねえ。だけど、できあがったのはとんでもなく、おいしかった。そのタフィに溶かしたチョコレートを加えたのがチョコレートキャラメルなの」
「そういう作り方だったんですね」
「二回目はここに来る少し前。生キャラメルってちょっと流行ったじゃない? 覚えてる?」
「あ、ありましたよね。北海道の牧場が作ったやつ」
「そう。あの時ふと気がついたの。この生キャラメルって、あのタフィじゃないかしら、って。それでね、また、家で作ってみたの。同じ本を使って同じレシピで……」
「大変でしたね」
「それがそうでもなかったのよ。昔は水飴や練乳なんかの粘りの強いものをいちいち秤で量って、鍋に移して……ってやってたけど、今はデジタルのいい秤があるじゃない? あれの上に鍋を直接置いて、どんどん材料を足していくだけで正確に量れちゃう。鍋もテフロン加工の良いものがあったし。びっくりしたわ。台所をそう汚すこともなく、あっという間にできあがった」
「でも、木下さんは大変と言ってましたが」
「それはもちろんかき回すのは大変なんだけど、昔と比べると、たいしたことない、っていう意味」
「そうですよねえ」
「だけどね……なんだか、昔と違ったのよね」
「違った?」
「……あんなにおいしかったから、ものすごく楽しみにして、丁寧に作って、バットに流し込んで、ゆっくり冷やして……温めた包丁で一つ一つ切って、やっとできあがって、口の中に放り込んだら」
「放り込んだら?」
「……あまりおいしくなかった」
「え」
「そこそこおいしかったけど、昔ほどおいしくなかった。あんなに天にも昇るようなおいしさじゃなかった。皆で大騒ぎして、取り合いになるくらいおいしかったのにね」
最後の方は小さな声でつぶやくように言った。
「……それはあれね、時代が違ったからじゃない」
正子さんが言った。
「今はおいしいものがたくさんあるから」
そんなことだろうか。乙葉は首をひねりたくなった。
亜子はもっと大切なことを今、言ったような気がしたけど。
でも、口を開こうとすると、正子と目が合って、彼女は小さく首を振った。それで口をつぐんでしまった。
「ええ。たぶんそうだわね」
亜子は微笑んだ。
「ねえ、今度、作ってよ。チョコレートキャラメル。タフィでもいいわ。みなみさんの部屋で『赤毛のアン』のドラマを観る時にね……あ、もちろん、その気があって亜子が大変じゃなければ、だけど」
そうね、と小さく亜子は笑った。
なんとなく、乙葉はもう、亜子の作るキャラメルは食べられないような気がした。
持ち主がわからないままの『女生徒』はそのまま、お忘れ物箱の中に置かれた。皆、なんとなく、そこに座って客が来ない時などに回し読みした。
「この本、いいよねえ」
特にみなみが気に入って、よく読んでいた。
「たぶん、高校生くらいの時に、一度読んだはずなんだけど、その時は特になんとも思わず、忘れちゃってた」
「そうだったんですか」
「うん。たぶん、あの時はまだわかってなくて、わびしい女の話ばっかりだなあ、いやだなあ、なんて思ってたんだけど、今読むと染みるよね」
うん、うん、とうなずいた。
「こういう気持ちってわかるなあ、って思う話がいっぱいある。昔はちょっと恥ずかしかったんだよね。これ読むと、自分の恥ずかしいところをむき出しにされるような気がして。だけど、今は、妙に染みるよ」
「みなみさんが太宰の作品で好きなのってなんだったんですか」
「『お伽草紙』とかかな」
「あー、なるほど、わかります。みなみさん陽キャだから」
「そんなことないよ!」
みなみの否定の言葉が大きくて、乙葉はびっくりしてしまった。
「あ、なんか、すみません」
「ごめんごめん、そんなこと言われたことなかったから、驚いちゃってさ」
彼女はすぐに謝ったけど、乙葉にはしばらく違和感が残った。
不思議な依頼が「夜の図書館」に舞い込んだのは、それからまた、数週間後くらいのことだった。
――話し合いたいことができましたので、明日、会議を開きたいと思います。四時から一階会議室にお集まりください。
そんなメールが篠井から図書館員全員に届いた。
乙葉が四時に会議室に入っていくと、丸く並べられた会議用の机と椅子に、篠井、渡海がいた。一番入口に近い端の席に荷物を置いていると、徳田、正子、亜子、みなみが続いて入ってきた。特に席が決まっているわけではないが、年齢と入った順番で、なんとなく奥から座っていった。
一階の会議室は簡素な作りで、椅子とテーブルが並んでいるだけだった。時々、客が多い時に少し大きめの応接室として使うこともある。今は、白川忠介の本が部屋の片隅に段ボールに入ったまま並べられていた。あれから二ヶ月弱、倉庫に戻す機会がなく、そのままになっていた。
「こういうの、あまりしないんですが、今日はちょっと皆さんの意見を聞きたくて」
皆が座るのを待って、篠井が話し始めた。
「会議と言いましたが、ざっくばらんに意見を聞かせてください」
「何? 篠井さんがそんなことを言うと、逆にちょっと緊張するよ」
渡海が笑いながら言って、皆もそれに同調するようにうなずいた。
「それはすみません」
謝ってはいたけど、篠井の表情はあまり変わらなかった。
「でも、本当に、あまりかしこまらずに、皆さんの話を聞きたかったんです。僕一人では判断しかねることがあって」
いつも落ち着いて物事を処理している篠井が「判断しかねる」ようなことってなんだろう……? 乙葉はさらに不安な気持ちになった。
「で、なんなんですか」
徳田がちょっとイライラしたように言った。
「すみません。では事実関係から話しますね。実は当館に、高城柚希さんの生前の蔵書を寄贈したい、というお話がありました」
「え」
「あの高城柚希⁉」
「まじ? 高城柚希が?」
皆がさまざまな声を上げた。でも、どちらかというと、反応が激しいのは若い図書館員の方で、正子と亜子は「あら、そう」というような静かなものだった。
乙葉も何か言いたかった。だけど、声が喉に詰まったようで、なかなか出ない。
「こりゃ、すごいことになりそうですね。海藤亮一以来の大物と言ってもいいんじゃないですか」
渡海が興奮した口調になった。
「俺自身、純粋にあの人の蔵書を見たいと思いますからね」
「あら、海藤以来なんてさすがに大げさよ。高城さんはまだお若かったし、ノーベル文学賞候補者と同じにするのは……」
「いや、人気という面ではあれ以上かもしれませんよ。若い人たちには熱狂的に読まれていたし。人気だけじゃなくて実力もある。芥川賞と直木賞の両方にノミネートされて、さらに海外の賞も取っているでしょう。俺はそれこそ将来、高城さんが次の日本のノーベル文学賞作家になると思っていたくらいで……作風も、SFやミステリー、ホラーから、純文学もなんでも上手で」
「ええ」
皆が盛り上がっている間も、乙葉は声が出なかった。そのうち、涙が盛り上がって、そして、ほろりと頬に落ちた。その時やっと声が出た。
「ちょっと待ってください……」
その声で皆、初めて乙葉の方を見た。そして、涙を流しているのに気がつき、驚いたように眺めた。
「泣いてるの……樋口さん? どうしたの?」
亜子が尋ねた。
「もしかして、そんなに好きだったの? 高城柚希が……」
乙葉はまだうまく声にできなくて、ばたばたと手を振った。
「……違うんです、違うんです。私はただ……」
あふれる涙を指で拭った。
「つまり、高城柚希さんは亡くなった、ということですか」
「……知らなかったの? 三ヶ月くらい前に、ニュースになったじゃない」
みなみが言って、隣からハンカチを渡してくれた。乙葉はそれを素直に受け取って目に当てた。
「わかってます。それはもちろん、知ってます。だけど、私、信じられなくて。というか、本当とは思えなくて」
乙葉は洟を盛大にすすった。すると今度は反対側の亜子から、ティッシュが差し入れられた。人前も気にせず、洟をかむ。
「きっとそれはあの人の……私たち、ゆずぽんって呼んでたんで、ゆずぽんでいいですか。ゆずぽん流の冗談じゃないかって思ってたんです。もしくは次の作品のための転生? きっと何か、深いわけがあるって思ってた」
「作品のために自分の死亡説を流すってこと? 高城柚希先生でもそれはないんじゃないかしら? 大手の新聞でも訃報が出たし」
正子がまっとうな意見を言った。
高城柚希は覆面作家だった。
年齢も性別も非公開、写真は一枚もなく、もちろん、人前に出たことはない。授賞式にもパーティにも出てこない。小説以外はエッセイやインタビュー、SNS等、一切なし。一つの会社からしか出版しておらず、担当編集者もずっと同じ人間が付いている、と聞いていた。
作風から、たぶん、三十代の男性だろうという意見が大半だったが、女性目線の作品も結構あり、著名な中年女性作家が「高城は女性だと思う、でなければ書けない部分がいくつかある」と強く主張してニュースになったりした。
「だって、ゆずぽんのお葬式出たとか、そういう人に実際会ったという人もいないし、死因も明らかにされてないし、担当編集者の名前さえ誰も知りません。普通の人ならともかく、私は書店員だったわけです。それなのに、一つも噂が届いてないっておかしくないですか」
皆が少しあきれてこちらを見ているのはわかった。乙葉は、感情をもう少し抑えないと、と思いながら、言葉があとからあとから湧き出てきて、止まらなかった。
「ゆずぽんは覆面作家で、自分の情報は一切出してなかったけど、ファンに対しては優しい人でした。作品を読めばわかります。こんなふうに逝ってしまう人とは違うと思う……」
そして、やっと最後に言った。
「本当に死んだなんて……まだ信じられない」
「なんか、すみません」
篠井が軽く頭を下げた。
「いえ。私こそ、取り乱して」
「樋口さんがそんなにファンだったとは知らなかったなあ……」
渡海が少し苦笑交じりに、でも、優しい声で言った。
「そんなファンじゃありません。ただ、ゆずぽんのデビュー日には、愛読者で生誕祭やる程度です!」
「……わかりました」
篠井が重々しく言って、その口調に、思わず他の人たちも笑った。乙葉も泣き笑いしてしまった。
「乙葉さんのおかげで、高城柚希の人気が私にもよくわかったわ」
正子さんが言った。
「本当にすごい作家だったのね」
「ええ、あたしたちにはそこまでわかってなかった」
亜子もうなずいた。
「……そして、ご相談したいというのは他でもないんです。高城柚希の蔵書が来るのはもちろんありがたいことなんですが、亡くなってからわずか数ヶ月で、公開していいものかどうか」
「実際には、受け取って整理して……なんだかんだ、亡くなってから最低でも半年くらいにはなると思うけどね。今、混んでるし」
正子さんが言った。
「ええ、もちろんです。でも、それでも早くないですか。いや、先ほどの樋口さんの様子を見ていたらおわかりになる通り、あの方はすごい人気作家でした。そして、いろいろな謎を残したまま、亡くなられた。公開すれば、かなりの人がここに来てくれるでしょう……でも、逆に大変な騒ぎになるかも。もちろん、盗難もあり得ますし」
「なるほどね。そういうことを心配しているわけだ」
渡海がうなずいた。
「それは、ある程度防げるだろう。部屋を用意して、出入りを厳しくし、入室する時には私物は一切持ち込まないようにする、とか。もちろん、誰かがずっと監視しているようにする」
「ええ。盗難についてはある程度、防げます。だけど、それ以上に迷っているのは、本当に蔵書を公開していいのか、という問題です。蔵書というのは究極の個人情報です」
「あ」
乙葉は思わず、声が出た。
「いろいろわかってしまう……?」
「はい。男女の性別とか、年齢など、本来、高城先生が公開していなかった情報が漏れる可能性があります。もちろん、当たり前のことですが、どんな本を好まれていたかも。今まで秘密のベールにつつまれていたことが」
「だけど、遺族が公開してもいいと言っているんでしょう? それとも高城先生の遺志なのか」
渡海が尋ねた。
「当館に連絡してくださったのは、妹さんなんです。実はそれもなかなか微妙でして……」
「微妙?」
篠井にしてはめずらしい言葉だ、と乙葉は思った。文字通り、「微妙」のようにあいまいな言葉を使うのは。
「連絡を受けたのは僕なのですが、電話で話しただけではかなり興奮された様子で……とにかく、本を処分して欲しい、と。めざわりだから、と」
「めざわり!」
乙葉は篠井の言葉をくり返しただけだったが、そこには「めざわりと言うなんてなんて、失礼な。ゆずぽんの妹といえど許せない」という言葉が言外に含まれていたし、それは皆にも伝わった様子だった。
「いえ……実は、まずは高城先生とお付き合いのあった出版社から連絡があったんです。高城先生が急に亡くなって、遺族が家の中のものを処分したがっている。このままだと今日明日のうちにも業者を呼んですべて売っぱらってしまいそうだと。どうしたらいいのか、その人も今すぐには判断がつかないが、高城先生ほどの作家の蔵書が散逸してしまうのは惜しい気がする、とにかく、一度、こちらで引き取っていただけないか、と」
「そういうことだったんですか」
「出版社の方も少し混乱している様子です。蔵書が散逸するのは嫌だけど本を置いておく場所もないし、今までにそのような例もないのでどうしたらいいのかわからない、と」
乙葉は高城柚希の版元が、比較的小さな出版社で、だからこそ、ずっと同じ編集者が付き、完全に秘密が守られるというようなことができたのだ、ということを思い出した。
「で、僕自身が妹さんともお話ししました。まあ、こういうことはめずらしいパターンですが、高城先生の家に取りに来て欲しいと言われました。僕たちが本を箱詰めして持って行ってくれるならあげてもいい、と。それから……」
篠井は少し迷いながら付け加えた。
「……こんなことを言ってはなんですが……なんというか……その妹さんは……ちょっと……エキセントリックな方で」
彼が電話を一本しただけでここまで言うのは、かなりのものなのだろう、と乙葉は思った。
「本当に、やると言ったら数日のうちにも処分してしまいそうな気がしました」
「で、篠井さんは何を迷っているんですか?」
これまで黙っていた徳田が尋ねた。
「迷っているというか、皆さんの意見を聞きたくて。うちにとっても影響が大き過ぎるかもしれません。実際、どこから聞きつけたのか、いくつかのマスコミから、『公開されたらすぐにでも取材させて欲しい』というような連絡がありました。中には、公開前に見せてくれ、というフリーライターの方からも。皆、蔵書から先生の性別や年齢、趣味なんかがわからないか、興味を持っているようです」
「その妹さんに直接聞けばいいのに。取材は入ってないのでしょうか」
徳田が首をひねりながら尋ねた。
「出版社が止めているようです」
篠井はちょっと困ったように笑った。
「妹さんには、高城柚希は謎のままの方がいい、その方がこれからも本が売れるから、と説得して、マスコミに触れさせないようにしているそうです。一応、それで納得はしていると。だけど、もう、家や資産は処分したいと言って、それは止めようもない。ものを処分して家を売りたいそうです」
「なかなか、ヤバそうですね」
渡海は笑った。
「古書店に勤めていると、そういう蔵書処分の場にも時々顔を出すので、なんとなくわかります」
「ああ、渡海さんは元古本屋さんだったからね」
正子が気がついて、つぶやいた。
「はい。結構、ありますよ。遺族がその価値を知らずに、すべてを適当に売っぱらうとか。本に限らず、コレクションものは皆そうですが」
渡海は篠井に向き直った。
「三ヶ月と言ったら、普通ならまだ、やっと四十九日が済んで、お墓をどうしようか、遺産は? という状況だと思います。例えば、亡くなった人に借金などあれば、相続放棄できるのがそのくらいの時期ですし、遺産や遺品について考えるのはまだこれから、という時ですよね」
「ええ」
「高城先生の相続人は他にいないのですか。妹さん以外に」
「と、聞いております」
「その辺、一応、ちゃんと調べておかないと、あとあと面倒なことになる可能性もありますよね。別の遺族が出てきて本を返してくれ、などと言われると大変です。すでに蔵書印を捺印後だったりしたら」
「あ。先生がいないなら、蔵書印のデザインもその妹さんと話し合わないといけないわね」
亜子さんが蔵書整理係らしいことを気がつく。
「なんだろう……めちゃくちゃ、面倒な気がしてきた!」
みなみは両手でこめかみのあたりを押さえるように、軽く頭を抱えた。
「でも、引き取りましょうよ! それだけは、絶対やった方がいいと思います!」
乙葉はたまらず、声を上げた。何があろうと、それだけは死守したかった。先生が亡くなったことはショックだが、本当だとしたら、関わるのは自分たちが一番いいと思った。
「この図書館に来て、まだ二月ほどですが、ここには蔵書を扱うノウハウがあるし、何より、皆、作家と本を愛していますから! 私、ファンとしても、皆さんに扱って欲しいです。皆さんは信頼できますから!」
正子や亜子を始め、そこにいた乙葉以外の全員がお互いに目を合わせて、微笑んだ。場の雰囲気がふっと和んだ気がした。
「それはお褒めいただき、ありがとう」
正子さんが言った。
「ええ、もちろん、あたしもそれは異存がない。面倒だけど、高城先生の本はうちの価値になりそう」
みなみも先ほどの仕草ほどは反対ではない口調で言った。
「で、オーナーはなんと言ってるの?」
正子が尋ねた。今度は、小さいけれど確実な緊張感が皆に走った。
「オーナーは基本的に賛成だけど、いろいろ手間のかかることでもあるし、皆さんの意見も聞きたい、ということでした。だから、こういう形をとったわけです。終わってから皆さんの意見を僕から報告します」
篠井は少し改まって、ぐるりと周囲を見回してから言った。
「では、とりあえず、本を引き取る、というところは皆さん、賛成ということでいいですか」
皆、首を縦に振った。その振り方はさまざまで、大きくうなずいた乙葉のような人もいれば、ごくごくわずかで機嫌が悪そうにさえ見える徳田のような振り方もあった。
「前の白川先生のように問題が起きるかもしれないし、こちらで家に直接行って引き取るというのはほぼ初めての経験です。そして、まだその量もわからないので、なんとも言えないのです……でも、妹さんはとにかく『たくさん』だと言ってました」
「それだけじゃわからないわね。本を読む人の『たくさん』と読まない人の『たくさん』はまるで違うから」
亜子の言葉に、こちらは皆、大きくうなずいた。
「公開をどうするか、いつ、どのような形でするのか、というのはまた話し合いましょう。たぶん、出版社の方とも相談することになりそうですし」
「本はいつ取りに行くの?」
「とにかく、早い方がいいと思います。あの感じだと、下手すると急に気が変わることもあるかもしれません。できたら今日か、少なくとも明日、明後日中に。あとで妹さんに電話しますが、今日はすでに夕方ですから、たぶん、明日の昼間ということになると思います」
篠井は渡海の方を見た。
「渡海さんにはぜひ一緒に行っていただきたいのです。こういうことに一番慣れているのは渡海さんだと思います」
渡海は「もちろん、かまわないよ」と言った。
「私にも行かせてください!」
乙葉はここぞとばかりに声を張り上げた。ゆずぽんが亡くなったのが本当なら悲しい。だけど、それが本当なら、ここで行かなかったら必ず後悔すると思った。
「そうですか……」
篠井は口を濁した。
「できたら、男性の方がいいかな、と思ってたんです。力仕事になりますから。本がどれくらいあるかわかりませんしね」
それは嘘だと思った。現に白川の本を取りに行く時、篠井は自分に行かせたじゃないか。
渡海が静かな声で言った。
「……つらい仕事ですよ。遺品というものには、我々が思っている以上に生前の持ち主が宿っています。ファン……それも、そこまで大泣きするほどのファンなら、取り乱してしまう可能性もあります。今回の場合、遺族の方がどういうスタンスなのかわかりませんし、あまり刺激したくない」
「しませんから! 絶対、取り乱したりしませんから。それに、女が一人入っていた方がよくないですか⁈ 今、ゆずぽんの家がどうなっているかわかりませんが、その妹さん一人なら、男ばっかりでずかずか入っていくのってもしかしたら怖がられるかもしれませんし! あと、女性じゃないと入れない場所もあるかも」
乙葉は必死に言葉をつないだ。
「なるほど。一理ありますね」
篠井はうなずいた。
「じゃあ、絶対、泣かないって約束してください。泣いたら、すぐに部屋を出て行ってもらって、ドアから車まで段ボールを運ぶ係になってもらいますからね」
「わかりました」
「それから、やっぱり、徳田さんも行ってもらえますか。男性の方が荷物が運べますから」
篠井が徳田の方を見た。
「……いいですよ」
徳田は無表情でうなずいた。
「あと、できたら、図書館探偵の黒岩さんに一緒に行ってもらおうかと思って。あの方、そういう法律的なことにも詳しいから。何かあった時用に車の中で待っててもらおうかと」
「天気が良かったら、一台は軽トラにしませんか。本の量がわからないので。俺、古本屋時代の友達に借りられないか、聞いてみます」
「お願いします」
会議のあと、篠井が高城柚希の妹に連絡し、翌日の昼間に取りに行くことになった。
昼過ぎに図書館の前に行くと、昨日決めたメンバー……篠井、渡海、徳田、黒岩が待っていた。そして、前にも使ったハイエースと、古い軽トラが駐まっていた。
「じゃあ、行きますか」
篠井が言うと、渡海が乙葉の方を見た。
「今日は樋口さん、軽トラの方に乗りませんか。軽トラ、乗るの、結構楽しいですよ。それに先生の家に行く前に話したいこともありますし」
「わかりました」
話しておくことってなんだろう、と思いながら乙葉は渡海の隣に乗り込んだ。
「今日はよろしくお願いします」
「はい。こちらこそー」
昨夜は、乙葉に少し厳しいことを言った渡海だったけど、今日は打って変わって穏やかで、軽い調子だった。
「あの、話しておくことってなんですか」
車が走り出して国道に入ったところで、乙葉は尋ねた。
「あ、昨日はごめんね。ちょっと厳しいことを言っちゃって」
渡海はこちらを見て、にっと笑った。
「大丈夫です。私も、取り乱してしまって……恥ずかしいです」
「いや、しょうがないよ。そんなにファンの作家なら……」
「もちろん、死んだって、ちゃんとわかってるし、その時ちゃんと悲しんだから大丈夫なんですよ。ただ、昨日は急に名前が出たから、不意打ちみたいで」
「そうだよね」
「死因も何も発表されてないですしね……自分で思っていた以上に、気持ちの整理がついていなかったのかもしれない」
「ああ」
二人の間に、ほんの少し沈黙が流れた。若い人の急な死……それも作家となると、どうしても考えてしまう。自分でそれを選んだのではないかと。
「いや、まあ、話したかったのは、今日、これからあちらの家に行ってからの注意点ね」
渡海は明るい調子で話を変えた。
「あ。ありがとうございます」
「もちろん、他の人にもさっき言ったんだけどね、樋口さんには特に言っておきたくてね」
「ファンだったから?」
「ええ、それもあるしね。妹さんという人はたぶん、樋口さんと同じくらいの年代の可能性があるでしょ。特に女性のそのくらいの年齢というのは意識し合うものだしね」
「あ、確かにそういうことはありますね」
「本当にわからんのよ。あちらがどう出てくるか。同じ世代だから気楽に話せていいかもしれないし、逆になるかもしれないし」
「はい。私、どうしたらいいでしょう」
「とにかく、フラットにね。あちらがどういう態度でも淡々と仕事して欲しい」
「わかりました」
「それから、こういうのって、他の人の家に仕事で行く時の注意点なんだけど、視線に気をつけてね」
「視線……ですか」
「そう。視線。きょろきょろ部屋の中を見回したり、じろじろ見たりしないように」
「そんなことしませんよ!」
思わず、笑ってしまう。
「樋口さんがそんな人だと思ってないけど、意外に家の人って、そういうの敏感に察するんだよ。妹さんはたぶん、同居してなかったようだけど、部屋の中が今どんな状態かわからないからね。何度も言って悪いけど、樋口さんは同年代の女性だから特に気をつけて。部屋の中をとにかく見回さない。慣れないうちは伏し目がちに行動して」
「伏し目がち、ですね」
「そう」
乙葉はため息をついてしまった。
「ごめんね。そんなに緊張させるつもりじゃなかったんだけど」
「はい」
「……しかし、これから行く家っていうのは、どんなところなんだろう……住所からすると、神奈川県川崎市……」
軽トラにはナビがついていなかった。渡海は前の、篠井が運転する車のあとを追いつつ、メモされた住所を見た。
「武蔵小杉のあたりでしょうか。タワマンかな」
「住所からするとその可能性もありそう。ただ、駅から離れると、あのあたり結構、古い家やマンションもまだあるよ」
「ゆずぽんがタワマンに住んでいるのも、古い家に住んでいるのも、どちらも普通にありそうな気がします」
「そうなんだ。俺はデビュー作くらいしか読んでないんだよね」
そう話しているうちに、篠井の車とともに、乙葉たちは武蔵小杉のタワーマンション群に近づいていった。
「こりゃ、やっぱりタワマンだね」
篠井の車が一棟のタワーマンションの地下駐車場に吸い込まれていくのを見て、渡海は言った。マンションだが、一階にカフェやレストランなどの店舗が入っていて、一般人も使える駐車場があるらしい。
やはり、黒岩はとりあえず車の中で待機することになった。
「高城先生はなかなか稼いでいたんだなあ」
マンション棟の入口で、コンシェルジュに案内されてエレベーターに乗ったとたん、渡海が笑いながら軽口を叩いた。最上階ではなかったが、上から数えて三階が指定された階だった。
「こういうところは上の方が高いって本当でしょうか」
徳田が神経質そうに目をしばたたかせながら言った。彼も少し緊張しているらしい。
エレベーターから降りると、すぐ前が高城柚希の部屋だった。同じエレベーターは同じ階の二つの部屋しか使えない作りになっていた。
「じゃあ、行きますね」
篠井がそう言って、呼び鈴を鳴らした。すぐに「はい」という女性の声が聞こえた。これがあの妹だろうか。
重そうなドアが開いて、若い女性が顔を出した。ジャージを着ていて、すっぴん、ぼんやりとした表情だった。
「……昨日、お電話した篠井です」
下から連絡が入っているはずだが、篠井はもう一度、そう挨拶した。
「あ。入って」
彼女はそれだけ言って、奥に入っていった。篠井が慌てて閉まりそうになったドアを押さえた。挨拶がそっけないのは、彼女が無愛想で無礼だからか、それともこういう形で人と会うのに慣れていないからだろうか、と乙葉は考えた。
中に入ってすぐに、渡海からいろいろ注意を受けていてよかった、と思った。彼女がぼんやりしている理由もわかった。
彼女は片手に、見てすぐわかるようなアルコール飲料の缶を持っていた。