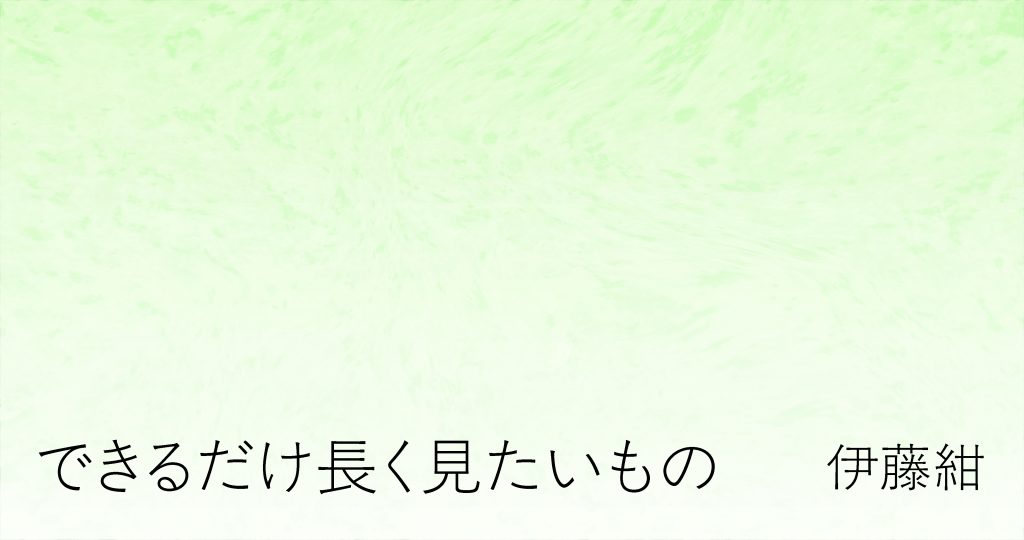
朝、散歩をする。起きてすぐ、スマホをひらかず、何かを考える間もなく家を出る。よく眠れた日は目も頭の中も雪がふったみたいにまっしろだから、その白さでSNSとかを見ると、なんだか1日中、画面にうつしだされた映像や言葉がうっすら頭に残ってしまう気がする。朝は木や花、それぞれのかたちの家々、散歩中の犬なんかと出会っておく。風や土のにおいを吸い込んでおく。するとこの土地に生きているひとりの人間としての自分が際立ってくる。
散歩をするようになったきっかけのひとつに、新しい歌のモチーフに出会いたいという少々打算的な目論見があった。モチーフとは歌に出てくるもの、題材のことだ。もともとかなりの出不精なので、家から一歩も出ずに5日くらい平気で過ごせてしまうのだけど、作品にはふだん見ているものが絶対に影響するので、実験的に視界を変えてみようと思った。
しかし外に出て、「お、今日見つけたこの花のこの感じ。よしこれを歌にしよう」とかいって、いい歌ができるわけではなかった。考えてみれば当然のことなのだが、短歌にしたいことはすごく限られている。自分が抱えている大きな気分、つまり人生のテーマのようなものを引き出してくれるモチーフと、そんな1回や2回の散歩で都合よく出会えるわけがない。それでも、散歩は続いた。ゆっくりといい変化が出てきたのだ。
大学生の頃、先生に言われてずっと心に残っている言葉に「人間は一度見たものを忘れない」というのがある。ちょっと乱暴だとは思う。めちゃくちゃ忘れるから。でも、先生が言っているのは「思い出せない≠忘れる」ということなんだろう。
たとえ意識の中からは抜けて、思い出せなくなっても、一度見たものは無意識のデータの一部になっている。幼い頃から見てきた、親の顔、部屋の雰囲気、住んでいる街のかんじ、絵本やアニメの世界、そしてだんだんと自分で選んでいく、本や雑誌、映画、友達の立ち振る舞い、好きな店……。
いまの自分の在り方や、話し方、思想やセンスは、普段の生活で、見ているもの、見てきたものの膨大なデータから生まれたものだ。これまで見てきたものをいまから動かすことはできない。でも、新しいデータを足すことはできる。先の言葉の真意は、「つまりこれから、何を見るのか考えなさい」ということだろうと理解している。
料理をすれば、肉や植物の色、その繊維や脂肪の模様を必ず見る。散歩をすれば、住んでいる街の空や建物や木の雰囲気、空気の匂いが自分の中に入ってくる。それが100回、1000回と重なって、溶け込み、人は瞬間瞬間あらたに生まれ続けている。散歩が日常の一部になってきた頃、モチーフの質がぐっと上がったように思う。
モチーフは、人生の無数の光景や瞬間からなる無意識の畑から、ある日、新芽のようににょきっと出てくるのだ。頭の中で生まれることもあれば、目に映って「はっ」とその存在に気づくときもある。「頭上から降ってくる」という感覚の人もいるらしいけど、個人的には畑から芽が出るというほうが、そこにかかる時間も含めて実感に近い。
夏の柳の木、お造りの皿にのっている魚の頭、燃えるゴミ、真珠、イヤフォン、歯、氷……。それまでべつになんとも思わなかったものが、ある日突然わたしと、わたしの人生のテーマを引き合わせてくれる。そうやってやっとひとつの歌が生まれる。その「テーマ」がなんなのかは、正直まだ自分でもわからない。モチーフがあって、はじめてその存在をほのかに感じるだけなのだ。
心がふっと反応するものを見る。見に行く。可能なら回数を重ねる。毎日新しい発見があるわけでは決してない。愚鈍なので何にも気づかない日のほうが多い。でも、人と共有するための、あるいはすぐに役にたつ発見より、気になる気分にぼーっと浸っているほうが、新しい芽との出会いにつながっているようだ。
伊藤 紺(いとう・こん)
歌人。1993年生まれ。歌集に『気がする朝』(ナナロク社)、『肌に流れる透明な気持ち』、『満ちる腕』(ともに短歌研究社)。








