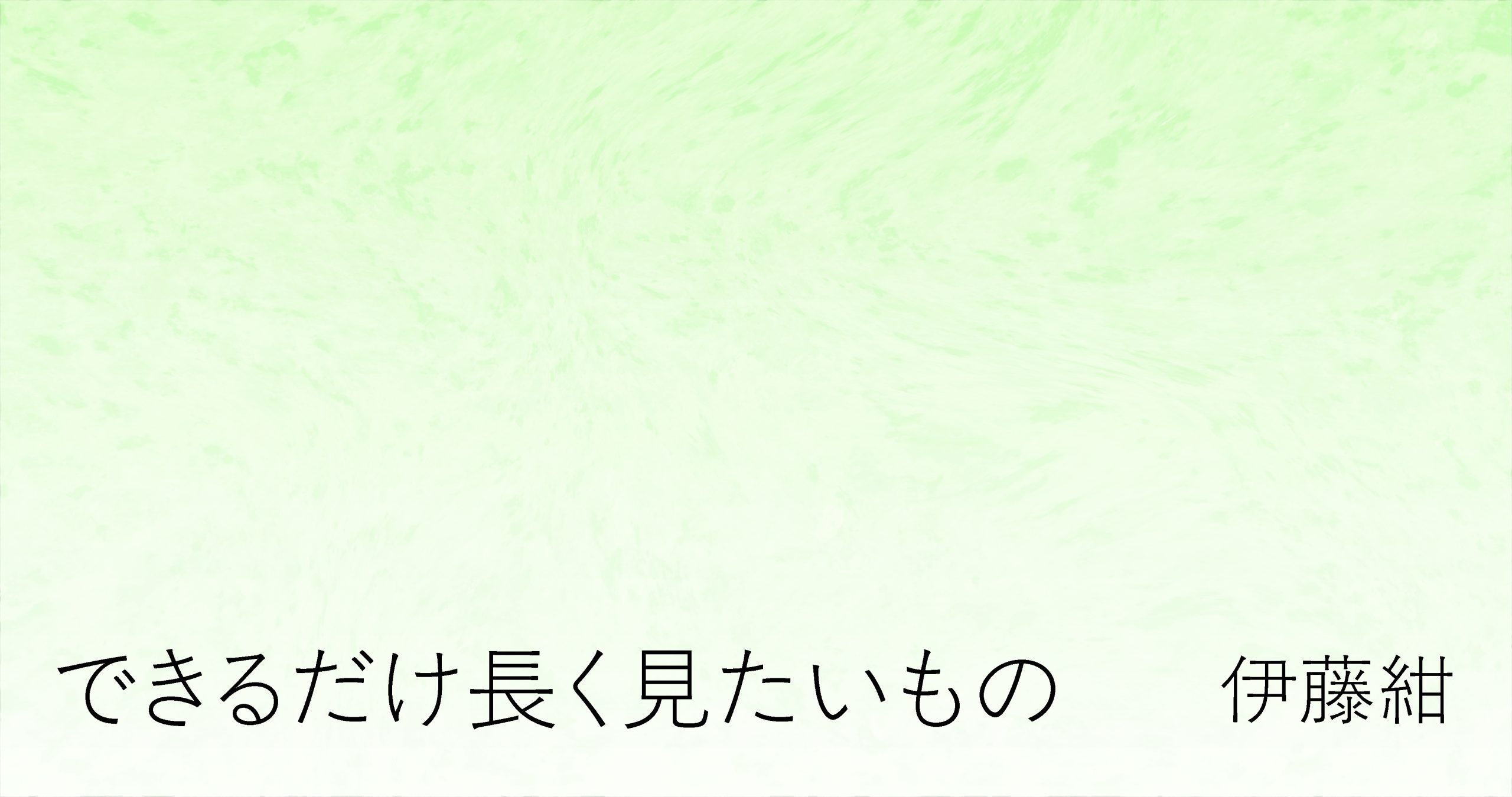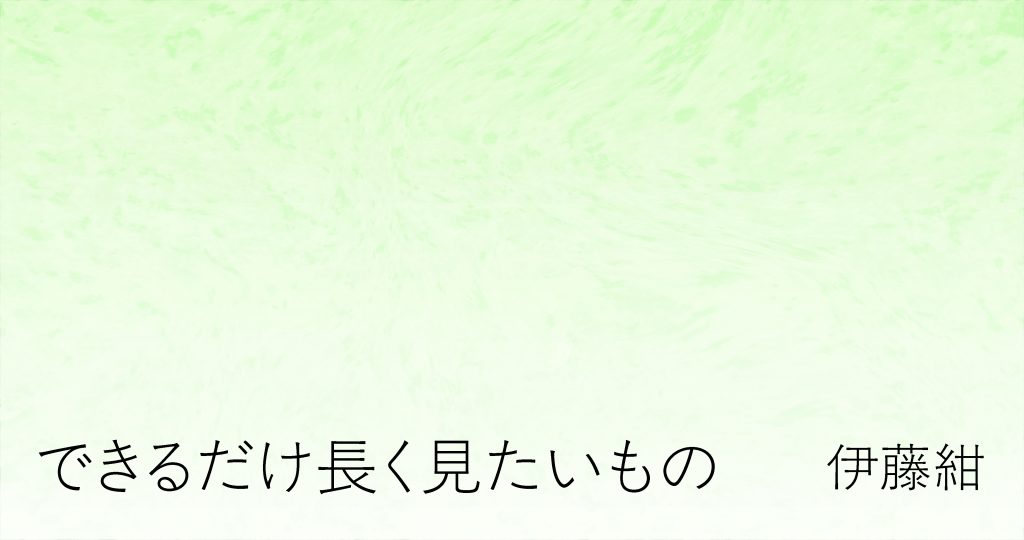
エッセイがむずかしい。短歌を書く時間に比べて、あまりにもつらい。得意ではないだろうと予想はしていたが、想像の倍むずかしい。というか葛藤が多い。
歌人としてわたしが思う、エッセイのやばさNo.1は、「わたし」という言葉が自分自身を指してしまうところである。
何をいまさら、と思うかもしれない。でも歌の歌詞に出てくる「わたし」が必ずしも歌手本人ではないように、詩の言葉において「わたし」は書き手“そのもの”ではない。
伊藤紺の短歌に登場する「わたし」は、伊藤紺本人として読んでもらっても全然いいけど、読者の脳内に自由に生まれる誰かでもあり、またその歌に強く共感できるときには、読者自身にもなりうる。
詩歌における「わたし」という語はボディを限定しない自由な器なのだ。
そもそも書き言葉というのは、話し言葉に比べて、声や口調、容姿といったボディから書き手を解放してくれるものだ。エッセイも話し言葉に比べたらずいぶんと解放されている。
でも、たとえば小説において「わたし」は主人公と結ばれ、書き手のボディ、年齢や職業などの属性はその外に解放されている。あるいは戯曲を演じる際、役者は舞台の上で自分のボディを提供しているが、「わたし=役」であり、同じように役者本人の属性やバックグラウンドからは解放されている。
創作において「わたし≠自分自身」であることは、単に自分を遠ざけ、自分と関係ないことを表現する逃避の役割を担っているだけではない。むしろ、自分のボディや属性、バックグラウンドから解放され、自分の中にある燃える魂をさらけ出すための装置になっているのだ。
ところが、エッセイにはこの装置が働かない。「わたし」は自分自身にぴったりと縫い付けられ、身動きが取れなくなっている。なので、その「わたし」を外から見るもうひとつの視点が鍵になってくるのだ。
心の中にある感情は、いつだってひとつではない。ある失敗について反省しながら、その失敗を少し誇らしく感じていたり、大したことじゃないと思っている自分も同時に存在していたりする。
その部分が本題なら全て書けばいいけど、「反省」が情報として必要なだけの場合には、ノイズになる部分の感情をカットしたほうがいい。
そりゃそうだろう。反省の途中で突然「でも、その失敗を本当は誇らしいとも思っていて、かつ大したことじゃないとも思っている自分もいるんですよ……」とか言い出して、最後まで回収しなければ、「あれはなんだったんだろう」と読者を無意味に困惑させてしまう。それをやるなら、相当なバランス感覚が必要だ。
自分の感情を、物語に必要な部分だけ抽出すること。これが相当なストレスなのだ。正直な話、物語と自分の感情を天秤にかけると、いつでも自分の感情のほうがちょっとかわいい。
自分自身を提供しているのだから、自分に正確でありたいと思うのはなんらおかしなことではないだろう。
書きながら、これは感情を抽出しすぎてさすがに嘘じゃないか、と手が止まる。嘘にならないように何度も抽出をやり直す。本当にめんどくさくなって堂々と都合のいい嘘を書き、いかんいかんとそれを消す。
短歌を書くときも似たような過程はあるけど、短歌の制作時に避けるべき「嘘」=「表現の精度の甘さ」であり、自分の事実は問題ではない。真実のために、事実に嘘をつく。主語が自由な器なのだから、それは嘘であって、嘘にならない。
エッセイを書き始める前から、エッセイやエピソードトークがうまい人は場の空気を読むのがうまいのかも、というようなことを漠然と感じていた。
彼らは、世の中や人間関係、自分自身を、ある程度俯瞰することができ、一定の距離を保てる。文体がドラマティックか独白的であるかによらず、そこで何を言うべきかを見抜き、必要な要素を抽出し、言葉そのものとカメラワークを巧みに使って寄り添ったり、逆に裏切ったりする。
意識的にせよ、無意識的にせよ、そんな“監督”の視点がエッセイには大きく関わっているような気がするのだ。
わたしの監督はといえば、あまり仕事が得意ではないようだ。
何かを伝える・おもしろく表現するために、自分の中で監督が燃えている気配をほとんど感じない。
「自分自身の心がたしかに感じたんだからさ、誰かにうまく伝えなくてもいいじゃない」となぜか鷹揚に構えているのだ。勘弁して。もっとがんばって。やる気のあるわたしが「いやいや、監督! ちゃんと伝えていきましょうよ! これ、ちゃんと書いたら絶対おもしろいですって!」と鼓舞しながら書くことになる。
非常に、骨が折れるのである。
伊藤紺さんの連載「できるだけ長く見たいもの」はこれで終了となります。お読みいただきありがとうございました。今後は、単行本刊行の準備にとりかかります。2026年春頃の刊行を予定しております。楽しみにお待ちいただけますと幸いです!(ポプラ社編集部)
伊藤 紺(いとう・こん)
歌人。1993年生まれ。歌集に『気がする朝』(ナナロク社)、『肌に流れる透明な気持ち』、『満ちる腕』(ともに短歌研究社)。