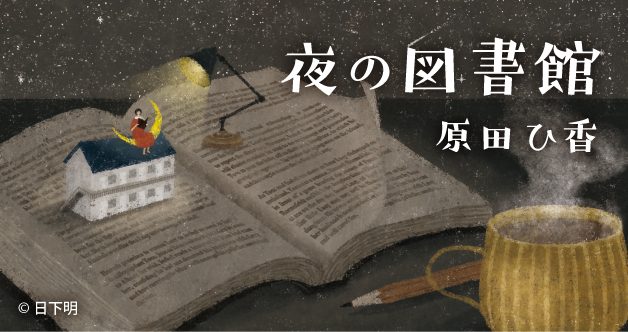覆面作家、高城柚希の部屋はまず長い廊下があって、そこを抜けると広いリビングとなっていた。そして、部屋の一面がガラス張りで明るい日の光がさんさんと入ってきていた。
高城の妹は大きなアルコール飲料の缶を片手に、目をしばしばさせながらこちらを見ていた。たぶん、自分たちが来る直前まで、どこか別の、暗い部屋で飲んでいたのだろう、と乙葉は思った。
せっかくの最上階なのに……これほど、「宝の持ち腐れ」という言葉が似合うこともない。
「では、お部屋の本を箱詰めしてよろしいですか」
篠井が尋ねると、彼女は黙ってうなずいた。
本棚の場所は聞くまでもなかった。そのリビングの片面が天井までびっしりと本で覆われていたからだ。素敵な空間だった。こんな場所に住むことができるなんてうらやましい。日の光がさんさんと降り込む中での読書も、深夜、夜景を眺めながらの読書もどちらも良さそうだった。
「他にも本棚はありますか」
「……あるよ。仕事場にも寝室にも……トイレの中も本が並んでる」
篠井が驚いた顔をすると、彼女はちょっと笑った。
「だから、たくさん、って言ったじゃん」
「わかりました。段ボール箱はできるだけ持ってきているので、大丈夫だと思いますが、少しお時間をください」
「お好きに、どうぞ」
そして、彼女はリビングのソファに座った。ソファは低くて大きく、やはり低いテーブルをぐるりと囲うように置いてあった。とても過ごしやすそうな場所だった。しかし、彼女は座ったと思ったらごろりと横になった。
「終わったら言って」
視線に気をつけろ、部屋を見回すな、と渡海に教えられたのは最初だけ役に立ったが、今となってはあまり意味はないかもしれない、と乙葉は思った。高城の妹は目をつぶっている。
「……私、トイレの本を詰めますね」
篠井たちに小声で言うと、うなずいてくれた。
とりあえず、小さめの段ボール箱を持ってトイレを探す。たぶん、玄関から入って最初のドアじゃないか、と思ったらやっぱりそうだった。
乙葉がトイレを志願したのは、そこに置いてある本なんて、きっとファンである自分にしか扱えないだろうと思ったのだ。それからもう一つ……。
「わ」
声を抑えたけど、それはやはり漏れてしまった。
高城家のトイレは三畳くらいの広さがあった。そして、やはりそこにも天井までびっしりと薄い本棚が備え付けられていて、主に漫画本と文庫本が入っていた。
それなりに広さがあるので、思ったほど不潔には思えなかった。この本はトイレの中で読むように置いてあるのか、それとも、本で部屋が侵食されすぎて、しかたなく、ここにも作ったのか、と考えた。まあ、たぶん、両方だろう。
トイレの上方には、普通の民家のトイレと同じような扉のついた棚もあった。トイレットペーパーなどを入れておく場所だ。
乙葉は気になりながらもそこには手を触れずにいた。
漫画本はほとんどが有名な作品ばかりで『ONE PIECE』『ジョジョの奇妙な冒険』『鬼滅の刃』『ガラスの仮面』『ちびまる子ちゃん』などが全巻そろっていた。そのラインナップからは性別や年齢を判断できるものはなかった。
持ってきた小さい段ボール箱はすぐにいっぱいになってしまったので、さらに取りに行った。
リビングでは篠井と渡海が棚から本を下ろしていた。
「……ねえ、その本、どうするの?」
ソファに寝転んだまま、妹が二人に尋ねていた。
「図書館に持って帰って、整理し、公開します」
「それは知ってるわよ。持って帰って最初はどうするの?」
「まず、蔵書印を押して、どのような本があるのか記録します」
「ふーん」
何か意図があって尋ねたわけではないようだった。
トイレに戻ってまた本を詰める。
そして、もう少しで終わりそうになった時、乙葉はどうしてもたまらず、上の棚を開けてしまった。
そこには予備のトイレットペーパーとティッシュペーパーのボックスが数個置いてあるだけだった。
ふっと肩の力が抜けた。高城柚希はやはり男性かもしれない、と思った。
また、本を入れ始めたとたん、トイレのドアが開いた。
「うわっ」
ぎょっとして見ると、そこには高城の妹が立っていた。
「……驚きすぎじゃない?」
「すみません! 使いますか?」
「ううん……何してるのかな、って見に来ただけ。向こうを見てるのは飽きちゃったから」
「じゃ、続けていいですか」
「どうぞ」
乙葉が本を箱に詰めている間、妹は壁に寄りかかって後ろに立っていた。
「……女だから?」
「へ?」
急に話しかけられてまた驚いた。
「女だから、トイレの仕事に立候補したの?」
「いえ、そういうわけじゃないですけど」
「トイレとか掃除するのは女って、どこか、強迫観念? 無意識のあれがあるんじゃないの?」
「いえ……」
ここを担当したのはファンだからだ、そして、それ以上に好奇心があったからだ……しかし、それは言えなかったし、そして、聞かれれば聞かれるほど、自分でもわからなくなってきた。もしかしたら、そういう気持ちもあったのかも……。
「そういえばさ、無差別テロの犯人が捕まった時、彼らにトイレ掃除をさせて、それがひどい屈辱で虐待行為だって一部の人たちが騒いでたよね」
「え」
「知らない?」
「知りませんでした」
「あちらの国の人は、男にはトイレ掃除なんてさせないんだって。宗教上でもね。それは奴隷か女の仕事なんだって。だから、それをテロの犯人といえども捕虜にさせるなんて虐待だってさ」
「そうなんですか」
「ひどい話だよ。あたしらはテロ犯人以下の仕事をさせられてるっていうことかよ」
吐き出すように言うと、彼女はぷいっとそのまま行ってしまった。
妙な胸騒ぎがした。
自分は何か大切なことを忘れているような……気がした。
トイレの中の本をすべて詰めたあと、リビングに戻った。
そこにはまだ篠井と渡海がいて、壁面の本を箱に詰めていた。
「手伝いますか」
せっせと働いている二人に声をかけた。
「いや、他の部屋の箱詰め、頼める? 徳田さんが仕事部屋の箱詰めしているけど、たぶんそこだけじゃなくて……」
篠井が答えながら、乙葉の後ろを見つめているのに気づき、振り返ると、妹がいた。「他の部屋にもあるよ」
彼女はしぶしぶというふうにうなずいた。
「他の部屋、一つ一つチェックしながら本を集めてくれる? すみません、いいですか、あの……高城さん」
高城はペンネームだということはわかっていても、他に呼びようがない。
案の定、妹は片方の眉をぎゅっと引き上げた。
「あたしは高城じゃないよ」
「すみません、なんてお呼びしていいか、わからなくて」
「……もね、でいいよ」
乙葉は心の中に「たかしろもね」と自然に刻みつけた。
「もねさんですか。漢字は」
「それ今、必要ある? どうせ本名じゃないし」
「すみません」
「……じゃあ、部屋を回ってもいいですね? 入って欲しくない場所とかありますか」
篠井が謝り続けているのが見てられなくて、思わず、割って入った。
「いいよ。便所まで見られたんだ。もう、どうでもいいさ」
乙葉は小さめの段ボール箱を組み立てて、それを片手に持ちながら部屋を回ることにした。
まずはトイレ……もねの言葉を借りると「便所」の隣の戸を開ける。奥が曇りガラス張りのバスルームで、手前が洗面台、その向かいに大型洗濯乾燥機と棚があった。
さすがにこんな場所に本はないだろうとドアを閉めかけると、もねの声がした。
「ここだよ」
彼女が洗面台の下の棚を開けると、予備の歯ブラシや歯磨き粉、シャンプーなどの備蓄の脇に本がぎっしり詰まっていた。よく見ると、須賀敦子の全集だった。文庫でなくて、箱入りの単行本だ。全九冊が縦横にぎっしり詰まっていた。
「なるほど、須賀敦子か」
声がこぼれ出た。
「知ってるの?」
「須賀敦子さんですか?」
彼女はうなずいた。
「はい。大好きなので」
「ふーん」
あまり興味なさそうにうなずいた。
「これ、本当に持って行っちゃっていいんですか」
「なんで?」
「いや……いい本だから」
「何言ってんの? 持って行ってもらうために、来てもらったのに」
「そうですね」
そこに手をかけようとすると、彼女はさらに言った。
「あと、ここ」
それは洗濯機の上の棚で、扉がついている。彼女が開くと、フェイスタオルとバスタオルが二枚ずつ置いてある横に、また本が並んでいた。
こちらは田辺聖子全集だった。十冊ほどがまた、縦横にぎっしり詰め込まれている。「これ、他にもまだありますかね」
「なんで?」
「田辺聖子さんの全集がこれだけとは思えません」
「さあねえ、他の部屋にあるんじゃないの?」
「そうですか」
全集を詰め込むと、小さな段ボール箱はすぐにほぼいっぱいになり、ずっしりと重くなった。
――いや、これはなかなか大変な仕事になるぞ。
乙葉は改めて思った。詰めるだけじゃない。これを下に運ぶのだって……いったい、どれだけ時間がかかるのだろう。
先のことはあまり考えないようにしようと思いながら、バスルームの廊下をはさんで向かいの部屋を開ける。そこは仕事部屋で、まさに徳田が悪戦苦闘している場所だった。
「徳田さん、大丈夫ですか?」
「うん」
彼は本棚に向かっていて、こちらを見ようともしなかった。
「何かあったら言ってくださいね」
「あ」
やっとこちらを向いた。
「もし、リビングに行くことあったら、もういくつか、段ボール箱、届けて」
「了解です」
仕事部屋の隣は八畳ほどの寝室と、作り付けのクローゼットになっていた。
ダブルベッドには白いシーツと濃い茶色の掛け布団がかかっている。それが部屋のかなりの部分を塞いでいて、他にはほとんど何もない。
ダブルベッドということ以外は、あまり特徴のない部屋だ。アロマキャンドルもないし、花の絵もない。たぶん、電気を消して、厚いカーテンを引き、ドアを閉めれば真っ暗になるだろう。だけど、それだけにリラックスできそうだった。高城は執筆の合間に、ここで身体を休めたのだろうか。
――ダブルベッドか……いや、ダブルの方が眠りやすいし、一人でもそちらを選ぶ人もいる。
「クローゼットの中に本があるよ」
また、後ろから妹、もねに声をかけられてドキリとする。
じゃあ、と手をかけようとすると、「ちょっと待って」と言われた。
彼女は乙葉の前に立ちはだかり、手首を使って手を振った。あっちに行け、というふうに。乙葉は一メートルくらい下がった。
「こっちは見ていいわ。あんたがやって」
手前のクローゼットを大きく開いた。ハンガーパイプが備え付けられているだけの簡素な作りだった。ただ服が吊してあるのは半分だけで、ほとんどが白いシャツに黒いパンツだ。もう半分の部分に、パイプの下くらいまでの高さでクローゼットと同じ奥行きの本棚がきっちり入っていた。測ったようにできていたから、もしかしたら、オーダーかもしれない。
「すごいですね。こんなところにまで」
声がもれた。
「何が」
「ものを徹底的に少なくして、代わりに本を入れている」
「どうだろ。もともとものの少ない人だったから。本以外は。そんなに無理に苦労してやっていたんじゃないと思う」
初めて、彼女の口から出た、高城柚希の姿だった。思わず振り返る。彼女も同じことに気づいたみたいで、目をそらした。
乙葉はそれ以上何も言わず段ボール箱に本を詰めた。高城のことは聞きたかったが、これ以上よけいなことを言って、彼女の気が変わるのも怖かった。
ここの本棚は幅がある分、写真集や画集などが多かった。写真集はさまざまな人の姿や風景が撮られたもので、画集も同じようなものが多かった。いわゆる女性の写真集は二冊だけ。薬師丸ひろ子と原田知世のもので、どちらも十代の頃のものだった。高城のことがまたわからなくなる。
乙葉がそれを詰めている間、もねは隣のクローゼットを開けていた。ちらりと見ると、背の高さくらいまでの引き出しが入っていて、その上が棚になっているクローゼットだった。棚にはもちろん本が並んでいたが、引き出しの方にも本がないか、一つずつ調べてくれているのだった。
ありがとうございます、と言おうとして、口を閉じた。
引き出しにはたぶん、下着が入っている。それを見たら、高城の何かがさらにわかってしまうから、もねは自分で調べているのだろう。
いろいろあっても、彼女なりに気を遣っているのかもしれないと思った。
※ ※ ※
こうして、人の家で本を整理していると、昔のことを思い出す。
俺はもう十年以上、古本屋だし、今もまだ古本屋だと思う。正直、自分が図書館員だと思ったことは一度もない。
最初に仕事をしたのは今まで同業者やここの誰にも言ったことはないが、いわゆるチェーン系の古本屋……新古書店と呼ばれるような店だった。
高校時代に、地元のロードサイドにある大型店でアルバイトを始めた。本だけじゃなくて、CDや映像ソフト、ゲームソフトなんかも扱っている店だ。きっとどこの街にもあるだろう。
ああいうところじゃ、本の買い取りの知識や技術なんていらない。本はただ、その新しさやきれいさ、人気で判断される。あまりに売れすぎて、数が多すぎるのもダメだけど。古い本は汚れた上の部分……業界では「天」と呼ばれる部分を削ってクリーニングして売るくらい。稀少本とか、専門書に対する知識は皆無。(新潮文庫や岩波文庫の「天」を削っていたなんて、今では震える。)神田の古書店街で稀少本として高く取引されるようなものも、ただの「ボロい本」として扱われ、買い取りを拒否したり、時には破棄したりする。うすうす「これは価値があるんじゃないか?」と疑っていたとしても。
「まあ、ノイズ、だよね」
当時、三十代半ばだった店長は言った。
俺が「こういうの、高く売れるんじゃないですか」と今は大人気の小説家の、デビュー作の初版本にサインが入っているのを見せた時のことだ。
「ああ、いいや。捨てちゃって」
「いいんですか」
店長が捨てて、と言ったのは、本のカバーがなくなっていたからだ。そして、言ったのだ、まあノイズだよね、と。
「え?」
「こういう本さ。古いけど価値があるってやつ。ノイズじゃなかったら、バグって言うかさ」
「バグ、ですか」
古い本が、コンピューターのプログラミングを狂わせるバグと同じだというのはどういう意味だろう。
「こういうのあると、調子が狂うわけよ。判断に迷うっていうかさ。本はただ、古さと状態で判断したいわけ、俺は。それを阻害するものは……」
彼は首を振った。何かよい言葉が思い浮かばなかったようだった。
本当は「好きじゃない」とか「許さない」とか「ぶっ殺してやる」とか言いたかったのかもしれない。だけど、あまりにも強い言葉過ぎて、口にしなかったのだろう。
店長は結婚して、子供が二人いた。駅からは遠いけど、ロードサイドには近い、このあたりでは一等地とされる場所に、結婚と同時に新築の3LDKの家を買っていて、新車のミニバンに乗っていた。どちらもローンだ。時々、店に子供を連れて遊びに来る、若くてきれいな奥さんはブランドもののバッグを持っていたけど、それもローンに違いない。自分の故郷の人たちは結婚と同時に新築を建てる。土地は東京に比べればただのようなものでも大きな家は二千万や三千万くらいはする。でも、それをしないと一人前だと思われない。当然、離婚して、中古で売り出される家も多い。そういうのは安いのに、皆、見向きもせずに新築を建てる。数年前、風習や土地柄が珍しがられて、全国放送のバラエティ番組で紹介されたことさえあるくらいだ。でも何が珍しいのか、地元の人たちはよくわからなかったと聞いた。
稀少本をゴミ箱に捨てる店長を、都会の文化人たちは野蛮人だと笑うかもしれない。それは違う。その気持ちを語る言葉や意識をあの人はちゃんと持っていたし、高校生だった自分に説明してくれた。あそこには、いや、東京にだって、自分の言葉を持っていない人はたくさんいるんだから。
それに、バグやノイズが自分を狂わせるというのは、店長の中にきっとどこか、価値がありそうな本を捨てることへの罪悪感があったのだろう。
「好きじゃない。ああいうの」
店長はまだぶつぶつ言っていた。
「なんで、本はこうも複雑なのか。わかんね、俺。古い方が価値が出る冷蔵庫とか、あるか? いや、あってもいいよ、だけど、うちの店はそういうのやらないから」
「わかりました」
「作家のサインなんてね、汚れみたいなもんなんだから」
でも、俺は店長が嫌いじゃなかった。ちゃんと時間通り来て、挨拶さえすれば、髪型や服装にうるさくなかったし、傷物ならどんな本も自分のチェックなしで持って帰っていいと言ってくれていた。
俺がその店を選んだのは、まさにそのためだった。買い取りできません、と断った本を「こちらで処分しましょうか」と言うと、客はほぼ百パーセント、置いて帰る。表紙や中身が汚れていたり、カバーがない本や漫画本、あまりにも売れすぎて在庫があふれている本などは自由に持って帰っていいのだ、と高校の先輩から教えてもらった。
俺は本や漫画を読むのが好きだった。だけど、たくさん買ってもらえるほど裕福ではなかったし、学校の図書館に行くのも面倒くさい。
廃棄処分の本は段ボール箱や紙袋にあふれるほど入って、店のバックヤードの片隅に置かれていた。俺は仕事をしながらめぼしいものをチェックしたり、帰りにじっくり選んだりした。俺は若くて、本の状態なんて気にしなかった。ただ、読めればそれでよかった。
そして、密かに店長がノイズと呼ぶ本……作家のサイン本や初版本、古そうな文庫本も持って帰った。たいした意味はない。子供がきれいな石ころや木の実を集めるのと一緒の気持ちだ。もしかしたら価値があるかも、と思えるようなものを捨てられなかった。
高校二年の夏、数人の友達と三泊四日で東京に遊びに行こうということになった。北陸新幹線で二時間半ほどの旅だった。洋服が好きな友達が原宿に行きたいと言い、ちょっとオタク趣味な友達が秋葉原に行きたいと言った。そして、共通認識で渋谷に行くことを決めた。最後の日の午前中だけ、自由行動をしようということも決めた。
ふとその時、自分が集めてきた本を東京の古本屋で売ったらどうだろう、と思いついた。他の友達は皆、なんらかの趣味があり、各自行きたいところがあるらしい。だけど、正直自分は一人でどうしても行きたいような場所はなかった。だったら、神田に行ってみよう、と。
四日間、一緒に持ち歩いた重い十冊の本を抱えて、俺は神保町の駅で降りた。どこの店に入ったらいいのかわからず、とりあえず、大通りで目に付いた、一番大きな店に入った。入口のあたりにはさまざまな全集や専門書が積み上がっている店だ。自分は若くて怖いもの知らずだった。逆に今だったら、絶対に入れなかったに違いない。
店の奥に座っていた、高齢の店主は俺が持ってきた本を一通り見ると、「百円」と言った。
「え」と俺は言った。思わず、声が出てしまった。
「百円なら買う」
「全部で?」
彼はうなずいた。
「どうするの、置いてくの、持ってくの?」
「あ、置いてきます」
安くてもなんでも、これ以上、本を持ってこの東京を歩く気にはならなかった。初めて、店で価値がないと言われた本を置いていく客の気持ちがわかった。
あーあ、やっぱり安いのか。店長の言った通りだな。
店主は後ろを向いて、自分の背中のところにあった引き出しから金を出し、俺の手のひらに百円玉をぽんと載せた。
「ありがとうございます」
がっかりして、そのまま下を向きながら店を出ようとして、ふっと気がついた。この店で高値で売られている本を見てやろうと思った。こういう店がどんな本を売っているのかを……。
「お兄ちゃん、お兄ちゃん」
本を見ていると、今、百円をくれた店主が自分のことを呼んだ。
「なんですか」
「お兄ちゃん、ちょっと」
「はい」
もう一度、レジに近づいた。
「お兄ちゃん、何。こういうこと、やりたいの?」
「こういうこと?」
「こういうふうに、本を売ること」
「いや、そういうわけではないんですが」
自分は問わず語りに、この本の出所や故郷の店のことを話した。
「ふーん、まあ、そんなことだと思ったよ」
「はあ、すみません」
「お兄ちゃんが持ってきた本ね」
店主は俺が持ってきた本の文庫の一冊を指さした。それはまだレジの横に置いてあり、彼が指さしたのはカバーのない本だった。
「これが百円、あとはゼロ」
「そうなんですか」
「この作家のサインはね」と、彼は大人気作家のサイン入りデビュー作を指さした。自分では一番高く売れるかと思っていた本だ。
「たくさんありすぎるからダメ。本自体もたくさん売れた本だからね。でも、この文庫は絶版で、好事家には人気がある作者なんだ。カバーが付いてればもっと出したよ。でも、カバーなしで百円は悪くない」
「そうですか」
「あんた、筋は悪くないよ」
「本当ですか!」
「地方の新古書店のゴミ箱から拾ってきた本が、痩せても枯れても、神田の一興堂で一冊売れたんだ。まぐれ当たりとしても結構なもんだ」
「ありがとうございます」
思わず、丁寧にお辞儀していた。
「それに今の若い者にしたら、口の利き方も知ってるようだしね」
店主はもう一度、後ろを見て、引き出しから千円札を二枚出して自分の手のひらにまたぽんと載せた。
「これやるから」
「え」
「これはあんたに払う、未来の駄賃。また、なんかこれという本があったら、持ってきてよ。いい物だったら買うし」
「いえ、そんな。いただくわけにはいきません」
慌てて差し出したけど、店主は受け取らずに、にやっと笑った。
「いいって、また東京に来た時、うちの店に一番に売りに来てよ。それだけでいいから。これでうまいもんでも食って帰りなよ。この角のカレー屋は有名だから」
「……わかりました。ありがとうございます」
俺はもう一度、店の中を見て回ってから帰った。どんな本が置いてあるのか、どんな本が高く売れるのか、ざっと見ただけではあまりわからなかった。その様子を店主はやっぱり、にやにや笑いながら見ていた。
それから俺は長い休み……冬休みや春休み、夏休みのたびに東京に来て、本を売りに行った。ほとんどは店の廃棄処分になったものだ。最初はほとんど売れなかった。時には一冊も買い取ってくれないことも。一興堂以外の店も見て回った。少しずつ、売れる本が増え、廃棄処分の本だけじゃなく、店に並んでいるものでも、神田の方が高く売れそうだと思ったら買い取るようになった。これはさらに自分のスキルを磨いたと思う。ただのものを売るのと、自分の金を出して買い取ってもらうのはまったく違う。自分の金を、「この本は高く売れる」という自分の知識に賭けるのだ。そして、これを始めてから、古本に対する興味はさらに高まった。これは「セドリ」と呼ばれる行為だということは一興堂の店主に教えてもらった。俺はこの「博打」に夢中になった。そして、東京への進学を決めた。もっと古本のことを勉強したかった。一応、親には地元の高校教師になるために、国文科に入りたいと言って進学した。しかし、本当はもう少し上の偏差値の学校に入れるはずだったのに、神田にある大学を選んだ。古本にはまったし、セドリにはまった。そして、そういう地元とは違う価値観や有象無象が謳歌している東京や神田に夢中になっていたのかもしれない。
「渡海はこのままセドリ屋になるのか」
大学生として、最初に一興堂に行った時、店主から聞かれた。
「さあ。どうでしょう。これからは地元の古本屋から仕入れるわけには行かないし」
でも、東京の郊外店などを回ってみるつもりではいた。ネット上での売買も盛んになってきた頃だし、いくらでもやりようはあると。
「イッキョウさんはどう思いますか」
度重なるごとに、お互いの名前を呼び合う仲になっていた。イッキョウというのは店の名前から付けられた、この町での彼のあだ名だった。
「セドリもいいけどさ……一度、ちゃんとした古本屋に勤めて勉強した方がいいぞ」
「そうですか」
「うちの店で働かないか。バイトで」
願ってもない申し出だったし、ほんの少し期待していたことでもあった。
イッキョウさんには息子がいて、彼が店を継ぐことは決まっていたけど、その人でさえ、俺の親くらいの歳だった。孫ほどの年齢で、一人、店に本を持ち込んだ自分をかわいく思ってくれるのはわかっていた。
お前にはうちのにはない、根性がある、とつぶやいているのを聞いたこともある。
そして、俺は古本屋になった。四年間アルバイトして、卒業後はやっぱり、イッキョウさんが紹介してくれた他の店に社員として勤め、二十代半ばに自分の店を持った。秋葉原寄りの神田にある、ごくごく小さい店だ。主に、漫画やラノベを中心とした、初版本を扱っている。実店舗に置いてあるものは少なめにして、主にネット上での販売で利益を上げている。神田では少しめずらしい品揃えと、秋葉原から来てくれる客のおかげでなんとか食っていけた。業界の中で、この独立は若くて早いほうだと思う。
この「夜の図書館」に来た理由は、図書館で働く他の人たちとは違う。自分は、自分からオーナーに近づいたのだ。
作家の蔵書を引き取って図書館にする、奇妙な人がいる、という噂は世の中で「夜の図書館」がニュースになるより先に聞いていた。
古本屋からしたら死活問題になりかねない事態だった。亡くなった作家の蔵書というのは宝の山だ。持っている稀少本はもちろんのこと、サイン本などが含まれている可能性も高い。有名作家なら、その人への「○○様へ」というため書きがあって、二重の価値が生まれる。
とはいえ、自分のような小さな店に、有名作家や遺族が蔵書を預けてくれるというようなコネもないし、作家の蔵書が散逸するよりいいかもしれないとは思っていた。神田界隈の古本屋の店主たちも一部を除いて、同様の意見だった。
ただ、業界で有名なラノベ作家の「トリコロールみつみ」が急逝し、その蔵書が「夜の図書館」に寄贈されたと聞いた時は心がざわめいた。
トリコロールみつみは渡海の店に、まだ売れていない頃から出入りした作家だった。同人作家だった時は「三海」という本名で領収書を切っていたが、ある時から「(株)トリコロール」で切るようになった。
何年も付き合い、本を取り置くために連絡先を聞くようになった頃、やっと尋ねた。「もしかして、トリコロールみつみ先生ですか」と。彼女はしばらく迷ってから小さくうなずいた。余計なことを聞いてしまったかと後悔した。次に彼女が来てくれた時にはどれだけ嬉しかったことか。
そういう繊細な関係を積み上げた果てに「自分が死んだら、渡海さんに本を処分してもらいたいなあ。他の誰にも価値なんかわからないだろうし」と言われるまでになった。
それなのに、彼女はあっさり亡くなり、それはこの図書館に入った。
文句はない。
彼女の蔵書は、うちに預けてもらえば一年くらい遊んで暮らせたかもしれない(これは比喩だ。実際にはそれを分類し、値段をつけて売るのはそこそこ大変だから遊べはしない)けれど、それだけで小さな「ラノベの歴史図書館」ができるほどのコレクションだったし、夜の図書館にあった方がいいかもしれないと思おうとした。
だけど、ここにあると、逆に人の目にほとんど触れずに本が死んでいくような気もする。比較的歴史が新しいラノベ本は、本当に欲しい人、読みたい人の手に渡った方が幸せな気もした。
とにかく、トリコロールみつみの死後、渡海は「夜の図書館」のオーナーを必死に捜した。神田の古書店街の店主たちに尋ね回って、やっと、ある作家の妻が、亡夫の蔵書を預けたことから連絡先を知っているという話を聞きつけた。
そこから連絡を取り、渡海はオーナーとスカイプで面談するところまでこぎ着けた。そして、理由を話し、自分を売り込んだ。
――トリコロールみつみ先生の蔵書整理を手伝わせて欲しい……。もしも、必要がない本があったら、譲って欲しい。
オーナーの返事は、こちらの条件を呑むなら、という限定的なものだった。
「最低、三年はうちの図書館で働くこと」
渡海はそれを呑んだ。今、店の方は当時、アルバイトとして店を手伝ってくれていた人に一時的にやってもらっている。結局、みつみの蔵書は一冊も手に入らなかった。
ここの誰にも話したことはないが、その期限は半年後に迫っていた。
※ ※ ※
皆、ぐったりと疲れて帰途についた。
高城のタワーマンションから車に乗る前、篠井が渡海、徳田、乙葉に向かって「今日はもうお休みされていいですよ、他でなんとか回しますから」と言った。
「でも、篠井さんは出勤するんでしょ?」
渡海がにこにこ笑いながら言った。
「僕は、まあ、オーナーへの報告もありますし」
「じゃあ、俺らも休むわけにはいかないよ」
「僕は休ませてもらいます、ちょっと腰に違和感があるんです」
徳田が言った。
「それはよくないね。腰は早めに治した方がいい」
渡海が徳田にうなずいた。
「私は……ちょっと休んで、様子を見てから出勤します。もしかしたら、お休みするかも……だとしたら、篠井さんに連絡入れます」
乙葉もかなり疲れを感じた。
「じゃあ、俺も様子を見て、これからよく眠れたら出勤します」
渡海は言った。
「では、そういうことで。車は図書館の前に駐めておいてください。荷物の運び出しは他の方たちとやっておきますから。
「……いや、そちらのハイエースはともかく、軽トラの段ボールだけは下ろした方がよくないですか。この方の本は取り扱いに注意した方がいいような気がします。私も手伝いますので」
ここまで黙っていた黒岩がつぶやいた。
「なるほど」
「黒岩さんも、高城柚希、好きなんですか⁉」
乙葉は思わず尋ねた。
「いえ。正直、昨日、篠井さんから初めて名前を聞きました。でも、それからネットを探って、なんとなくこの人を巡るファンや業界の雰囲気はわかった気がします」
「さすがですね」
「じゃあ、軽トラの荷物だけは下ろして、図書館の入口までだけ運びましょう。お手数お掛けしますが、よろしくお願いします」
篠井さんが言って、皆、行きと同じように車に乗り込んだ。
「……どうでした? 初めて故人の家に行った経験は」
軽トラの助手席に黙って座っていた乙葉に、渡海が尋ねた。
「……なんと言っていいのか」
そこからしばらく声が出なかった。時間は夕刻に差し掛かり、まぶしいくらい夕日が車の中にも差し込んでいた。
「疲れたでしょ。寝てもいいからね」
それ以上何も言わない乙葉に、渡海は篠井と同じような声をかけてくれた。
「いえ。大丈夫です」
「そう?」
「すみません。なんか、いろいろ考えちゃって」
「そりゃ、大ファンの作家が亡くなって、その家に行ったら、誰だってそうなるよ」
渡海の声は自分自身に言い聞かせているようだ、と思った。
「いえ……私が思ったのは……」
乙葉はため息をついてから言った。
「逆です」
「逆?」
「なんか、私、思ったんです。高城柚希、死んだ感じがしないなって」
「おうちに行っても、死んだ実感がわかないってこと?」
「まあ、それもありますが。そういうことじゃなくて……」
乙葉は首をひねった。
「うまく言えないんですけど……すみません」
「まあ、いいよ。これから高城先生の本を片付けなくてはならないし、ゆっくり考えたらいいよ」
「はあ」
「俺らの図書館のいいところはさ、考える時間がたくさんあることだよ」
「考える時間……?」
「給料も安いし、待遇もまあまあだし、仕事もちょっと退屈なこともあるけどさ。考える時間だけはたくさんある。そんな気、しない?」
「そんなこと、初めて思いました。でも確かに」
「売り上げとか求められないし、古い本は逃げていかないからね」
「はい」
「ゆっくり考えなよ」
そして、結局、図書館に着くまで特に何も話さずに帰った。
同日、始業時間ではなくて、開館時間に出社させてもらった。
すでに、他の館員によって高城柚希の蔵書は会議室兼応接室に運ばれていた。一応、見に行くと、前から置いてある白川忠介と高城、二人の蔵書で部屋は半分以上埋まっており、しばらく使えそうもなかった。
「……すごい数ね。ご苦労様でした」
後ろから話しかけられて振り返ると、正子が立っていた。
「いえ。玄関から運ぶのだけでも大変だったでしょう?」
「まあねえ。でも、家から箱詰めして出すのとは比べものにならないわよ」
そのまま、二人で並んで歩きながら蔵書整理室に向かった。
「白川忠介先生の本もそろそろ整理しないとですね」
「ええ。もう、向こうに持って行くより、このまま整理しちゃおうかって亜子さんとも話してたの。他の人を飛び越すことになるけど」
「そうですね」
「ねえ、どうだった? 高城柚希の家は?」
皆、心配してくれているんだな、と思いながら正子の顔を見ると、もちろん、心配もしているが、どこかおもしろそうな、興味が含まれた表情でこちらを見ている。
「渡海さんにも言ったんですが……」
「うん」
「なんか、不思議でしたね」
「不思議?」
「はい。高城先生が生きている気がしたんです。というか、生きて、すぐ近くにいるような」
「蔵書ってそういう力があるのよね」
正子はうなずく。
「いえ、そういうことではなくて……」
乙葉は言いかけて、その言葉を吞み込んだ。
まだ、その違和感を言語化するところまで行っていないと感じたし、それを言ってしまったら、何かが壊れてしまうような気がしたからだ。
いつもの通り、蔵書の整理をしたあと、食堂で食事をした。
カフェの片隅にはみなみと渡海がいた。いつもこの時間にいる徳田は今日は休んでいるんだろう。二人はすでに食べ始めていた。
店の奥にいる店主の木下と目が合ったので、軽くうなずく。「まかないでいいです」という合図のつもりだった。
「今、受付は篠井さんですか」
二人の横に座りながら尋ねた。
「そう」とみなみが答えた。
篠井はあの後、また、ここではご飯を食べなくなった。食べるとしても誰もいない時間にすませているようだった。
「大丈夫? 疲れてない?」
渡海が優しく話しかけてくれた。
「意外と大丈夫です。あまりに疲れていたら、休もうと思っていたんですが、一眠りしたら、元気になりました」
「若いなあ」
そう話しているうちにトレーにのった定食風の食事を木下が運んできてくれた。
「今夜は田辺聖子ナイトでしたっけ」
「そう」
毎週、金曜日は田辺聖子の日だった。ただ、彼女の日は他の作家と違って、「お好み焼きの日」「大阪風おでんの日」などがあって、メニューが一つではない。
目の前に置かれたのは、一見、普通の定食である。しかも茶色が多い、地味なメニューだ。
「今日は鰯を炊いたものが主菜、そのお汁でおからを炊いたやつが副菜。この組み合わせは彼女の小説に何回か出てくるんだよ。たぶん、お気に入りだったんだろうな。それから、けんちん汁。これもエッセイや小説に何度か出てくる。ご飯は普通の白いご飯に半分は手作りのゆかりを混ぜた、ゆかりご飯にした」
「前から聞こうと思ってたんだけど、木下さんはここに来る前から田辺聖子さんのファンだったんですか? 田辺先生だけ、妙にメニューが多いけど」
「いや。正直、この人もぜんぜん知らなかった。オーナーに『田辺聖子の味三昧』っていう生前、彼女が出した料理本を渡されて、その中の何品かを作るつもりだったんだけど、そのレシピには料理の出典が出ていて、それならせっかくだから本の方も読んでみるかって読んだら、料理の話が多くてはまっちゃって」
「そうだったんですか」
「一つに絞れなくてさ。いろいろ出しちゃうんだよなあ」
乙葉はけんちん汁を一口すすった。醤油の香りに、根菜の旨味が口いっぱい広がる。「ああ、染みるなあ」
そして、ごぼうと人参を食べる。
「おいしい。ここのカフェがなかったら、私の食生活、かなりやばいものになっていると思う」
「そりゃ、よかった」
木下は褒めると途端にぶっきらぼうになることがあった。照れているのだろう。
「……あたし、ここに来るまで、けんちん汁ってほとんど食べたことがなかった。名前は知ってたけど」
みなみもけんちん汁をすすりながら言う。
「けんちん汁って不思議ですよね。名前はポピュラーだけど、確かに、地域によって作る作らない、結構、差がある。年代的なものもあるかもしれないけど」
渡海さんが説明してくれた。
「けんちん汁は鎌倉の建長寺が作った精進料理が発祥と言われています。その建長汁がなまって、けんちん汁となった。だけど、現在は茨城や栃木などの北関東の方が食べてるみたいです。材料の根菜やこんにゃくがたくさん採れるし。ここにうどんを入れる、けんちんうどんも人気らしいですよ」
「渡海さんはいつも物知りだなあ」
木下が感心した。
「いえ、この間、テレビでやってたんです」
「なーんだ」
「でも、田辺聖子さんが作っているということは関西にもかなり広まっているってことですよね」
「ただ、田辺さんの作り方で北関東と一番違うのは、こんにゃくの代わりに豆腐を入れることなんだ。大根、人参、ごぼう、さといもなんかを切って、ゴマ油で炒めたあと出汁で煮て、醤油で味付け、くずした豆腐を最後に加える」
「あ、豆腐か。だから、優しくていいんですね」
「茨城のけんちん汁は大鍋にたくさんつくって、何日か食べた後、うどんやそばを入れたり、ご飯を入れておじや風にしたりするから、豆腐はあまり入れないのかな」
「かもしれない」
「こういう定食が一番好きです」
乙葉が言った。
「カレーを作った時も、同じことを言ってたよな」
木下はそう言いながら、厨房に入っていった。
鰯は甘辛く煮てあり、ご飯に合う。だけど、その少し生臭くなった口に、ゆかりご飯を入れるとまたさっぱりしておいしい。白いご飯とゆかりご飯、交互に永久に食べられそうだ。おからはその鰯の旨みがたっぷり入った汁を吸って、こってりとうまい。中に入っている、人参や干し椎茸がアクセントになっている。
「おからって、こんなにおいしいものだったんだなあ」
「そう。子供の頃はそんなに食べなかったけど、今はおいしいよね」
渡海が同調する。
「あたしの家は、けんちんだけじゃなくて、おからもあまり食べませんでした」
「みなみさんちって、どちらかと言うと、洋風?」
「まあ、そうですね。シチューとか、ハンバーグ的なおかずが多かった。父がそういうのが好きな人で」
「若いなあ」
「でも、まあ五十代ですからね。子供の頃から、そういう食事だったんじゃないですか」
「そういえば、高城先生の家にも田辺聖子全集がありました」
「そうなの?」
「ちょっと意外でした。田辺先生って亡くなられていますし、かなり年上の方の女性が読む小説って感じがしていたので」
「いや、そうとも言えないかも」
渡海が首を振った。
「前に、十代で芥川賞を取った小説家が田辺聖子が好きだってどこかに書いてあったの、読んだことがある」
「そうなんですか。じゃあ、年齢関係ないのかな」
「こんなに美味しい食べ物も書いてくれるし、いい先生だねえ」
そんな、どうでもいいことをだらだら話しながら食べる食事は、気楽でよかった。乙葉はゆっくりと体と心の疲れが取れていく気がした。
高城柚希の家に行ってから数週間しても、その蔵書の整理はされておらず、そのまま会議室兼応接室に置いてあった。一度は、いつもの場所……東京郊外の古家に持って行こうという計画も出たが、あれだけ人気のある人だから、鍵さえ壊せば誰でも入れる場所に置くのはどうか、という意見もあって、結局、そのまま図書館に留め置かれた。会議室はほとんど倉庫になってしまった。
蔵書についてはいまだぽつぽつと取材依頼や問い合わせがあった。それでも、逝去後すぐよりは少なくなり、乙葉たちは人々の興味の移り変わりの儚さを知った。ただ、地方の書店から、高城の著書のフェアをやりたいので写真を撮らせてくれないか、という依頼があった時は少し議論になった。フェアの背景に蔵書を並べた本棚の写真のパネルを飾りたいとのことだった。
乙葉たちは話し合い……高城の蔵書でかなり狭くなった会議室の一角で机もなしに椅子だけ並べて……今すぐ本を出すことは物理的にもむずかしく、まだ、それは早急じゃないかという理由で断った。乙葉たち、元書店員だった人たちは、できたら協力してあげたいという立場だったが、総合的に考えても無理だと判断した。しかし、高城柚希の膨大な蔵書の脇で、身を寄せ合うように話し合っているのはなんだかおかしかった。
「……私たち、この本のしもべね」と正子さんが言って、皆、苦笑いした。
「まあ、それが私たち、図書館員の正しい姿だけど。本のしもべというのが」
正子さんの声は小さく、自分に言い聞かせているように聞こえた。
その日、食事をして一階に下りてくると、受付のところで篠井が一冊の本を持ってみなみと話していた。
彼らが二人とも眉をひそめているのを見て、すぐに気がついた。
「乙葉ちゃん、また見つかったよ」
近づいていくと、みなみが思った通りのことを言った。
「またですか」
篠井は黙って、持っていた本の裏表紙を開いた。そこには何も押してなかった。
「あらま」
蔵書印が押してない本は、あれからちょくちょく見つかっていた。最初は週に一度くらい、そして、最近は数日に一回。本当は一冊一冊確認したらもっとあるかもしれない。
「どうして、気がついたんですか」
「ほら、これ、新刊書、それも発売して間もないでしょ」
みなみが言って、篠井が背表紙を見せた。
「ほんとだ」
本はエッセイで有名な老作家のもので、彼が太極拳を始めてから体調が劇的に変わったという体験談だった。数ヶ月前に出て、今もベストセラーになっている。
「背表紙、見ただけでなんかピンときた。こんなに新しい本、それも小説じゃない本がここにあるなんてめずらしいし、記憶になかったから」
「なるほど」
なんとなく、三人一緒にため息をついた。
こんなにたくさんの本が紛れているとなると、犯人はおのずと限られてくる。そうたびたびここに来る人は多くない。
まずは図書館員。あまり考えたくない可能性だけど、まったくないとは言えない。そして、月間パスポートや年間パスポートを持っている人……。
月間パスポートについては、ないわけではないが、この蔵書印がないものが見つかるようになってから、数ヶ月にわたって買っている人はいない。
今、年間パスポートは五、六人の人が持っている。
高木幸之助の愛人の二宮公子さん、他は大学の教授や大学院生、卒論を書いている学生、夭折の詩人、安藤光泰についてのノンフィクションを書いているフリーライター、そのくらいだ。
「七度探して人を疑え、とは言いますが」
篠井がつぶやいた。
「何、それ」
みなみが尋ねる。
「例えばですが、何か物がなくなった時なんかに、七回探してから、泥棒を疑えということです」
「なるほど」
「だから、本来なら内部を探さなくてはならないわけですけど」
実際、少し前の会議ではこのことも議題に出た。篠井が言いにくそうに「決して皆さんを疑っているわけではないのですが、誰か、この件について知っていることや心当たりがある方は申し出てくださいませんか。ここで言いにくければ個人的にでも」と言った。皆、顔を見合わせて、首を振った。そして、その後も篠井のもとに誰からの申し出もないらしい。
「……一応、僕、聞いてみようかと思うんですよね」
「誰に?」
「年間パスポートを持ってきていて、ここ最近、出入りしている方に。最後の棚卸しをしたのが四ヶ月前ですから、そのあと、こちらに頻繁に出入りしている人に」
「何を?」
みなみの質問はぽんぽんと勢いがよかった。
「そうですね。疑っているとかではなくて……実際、誰のことも疑いたくないので……こういうことがあるんだけど、何か、知りませんか、というような感じで」
「それを聞いて、犯人がわかるかな? 犯人が言う? 私だよって」
「いえ、それはまあ、たぶんないですが……でも、こちらが注意喚起をうながすというか、私たちも知っているよ、ということであれば、やめるかもしれません。あと、元警察官の黒岩さんにも相談していると言えば」
「なるほどねえ」
「それでもやめなければ、あまりやりたくなかったことですが、蔵書整理の日程を早めましょう! それをすれば、その後、見つかった場合、それ以降、来館されたお客様だということだけはわかります」
「うわあ」
みなみが顔をしかめる。
「しょうがないことです」
「わかってます。ただ、蔵書整理ってめちゃくちゃ大変だから!」
乙葉は思わず、口をはさんだ。
「蔵書整理ってそんなに大変なんですか」
「書店でも棚卸しをやるでしょ。あれといっしょですから」
「ですよね」
「図書館はさらに大変です。一週間は閉めなければなりません」
「今、白川先生、高城先生とか、どんどん蔵書が増えてて、ただでさえ滞っているのに。新たに蔵書整理なんて」
「でも、仕方ありません」
「ですよね」
「……あたし、あのちょっと……」
みなみが声をひそめる。
「あんまりこんなこと言ってはいけませんが……さんがあやしいとずっと思っていて」
名前のところが聞こえなかった。
「え?」
聞き返して、みなみがもう一度それを言おうと息を吸ったところで。
「ちょっと、中に入りましょう」
篠井がめずらしく、強い調子でみなみの腕のあたりを取って、受付の裏のスタッフルームへ入っていった。乙葉も客がまわりにいないことを確認し、受付の上にあるベル……お客様の来館時やこの場所を離れなくてはならない時に鳴らすもの……を二回「チン、チン」と押して篠井たちの跡を追った。
「あそこでお客様の名前を出すのはまずいです」
「すみません」
「今は誰も来てないとはいえ……」
「……なんで今まで気がつかなかったんだろう」
乙葉は二人の様子を見ながら声が出た。
「何をですか」
篠井が振り向く。
「外のチケット売り場です。北里舞依さんが入る時と出る時、ざっとお客様の荷物検査しているじゃないですか」
「ええ」
「だから、本を持ち込んでいる人はすぐわかります。出て行く時はなくなっているのだから」
「それはもう調べたじゃないですか。そういう人はいない、と北里さんが言っていました」
篠井が答える。
「そうです。でも、これまでは文庫本でしたから。例えば、大きめのポーチなんかに入っていたら、女性のポーチは同性でも開けて見たりはしないでしょ。それに、文庫本なら服にも隠せるってちょっと諦めてたし……」
「あー」
乙葉の言葉の途中くらいで、篠井が声を上げながら自分が持っている本を掲げた。
「単行本、しかも、新刊書」
「それなら、北里さんも気がついているかも」
「確かに」
「すぐ聞いてみましょう」
三人でチケット売り場に向かった。スタッフルームを出ると、受付には渡海が座っていた。
「あ、渡海さん、ご苦労様です」
「なんかあったの?」
スタッフルームから三人が続けて出てきたからか、彼は少し驚いた様子で尋ねた。
「あ、あとで説明します!」
さらにめずらしく、三人は走った。篠井もここでは「レディは走らない」とは言わなかった。
乙葉は売り場に向かいながら、みなみがつぶやいた名前が聞こえたような気がしていた。それはほとんど毎日ここにくる、老女の名前だった。
なぜなら、乙葉も密かにその人を疑っていたから。
北里はその新刊書を見、篠井の説明を聞いて首をかしげた。いつもと同じようにさらさらの髪がそれに合わせて落ちた。
「……二宮公子さんの本ですね」
「間違いないですか」
「間違いないです。あの人、こういう本も読むんだなあ、と思いましたから。ああいう人でも健康に気を遣っているんだなあって」
「そうですか」
篠井がため息をつくと、「肩を落とす」という表現がぴったりの様子になった。
「……できたら、あの方だと思いたくなかったんですけど」
ということは、彼もまた、彼女を疑っていたのかもしれない。
「ああいう人でも、というのはどういう意味ですか」
乙葉は北里に尋ねた。
「ああいう人?」
「二宮さんのことをああいう人、と」
「ああ。二宮さんとはここを通る時、時々話をするのですが」
北里が自分から客に、必要以上に話しかけている様子はあまり思い浮かばなかった。もしかしたら、二宮が一方的に話しかけているのかもしれない。
「早く死にたい、とか、ぽっくり逝きたい、というのが口癖で」
「えー、そんなことを」
「どこまで本心かわかりませんよ」
「冗談かもしれませんよね」
「そうそう。もう一つ、その時、気になったことがあります」
北里が言って、篠井から本を取り上げた。
「あったかなあ」
独り言を言いながら、本をぱらぱらとめくった。すると、そこには短冊状の紙がはさんであった。
「売り上げスリップ!」
乙葉は思わず、叫んだ。
「……その時、あれ、スリップがそのままだな、と思ったんです」
「じゃあ、これ、万引きした本ってこと?」
みなみがずけずけと言った。
「あ、今の大型書店はデジタル管理しているので、スリップがあるからと言って、一概に万引きとは言えません」
「ネット書店で取り寄せた本なら、そのままだしね」
「でも、このあたりの書店でデジタル管理しているほどの規模の店は新宿か池袋、八王子、所沢あたりまでいかないとないかも」
「微妙ですね」
「まあ、万引きについてはこの際、二の次三の次です。まずは、この本についてお尋ねしなくては……」
「すみませんでした」
北里が謝った。
「私、ぜんぜん気がつかなくて……二宮さんの本が入ってきた時はあったのに、出て行く時はなかったこと、気がつきませんでした。いつも、ここの本が出ていくことばかりを気にしていたので」
「入り鉄砲に出女、みたいな話。入ってくる女には気がつかなかった」
みなみが慰めるためなのか、少し茶化した。
「その比喩はちょっと違いませんか」
乙葉が言って、二人で笑った。
「……僕はこれから二宮さんにお尋ねしなくてはならないのか……」
二人の様子とは対照的に、篠井はもう一度ため息をついた。
「私も行きましょうか」
その様子を見て、乙葉は思わず申し出た。篠井があまりにも憂鬱そうで、気が重そうに見えたからだ。いつもはテキパキ仕事をこなしている人だが、こういう件……怒ったり、注意したりすることは苦手なのかもしれない。
「いいんですか」
「私、前の書店で何度か万引き犯を捕まえたり、話したことあるし。あ、実際はそういうのって、うちの店はショッピングビルの中にあったんで、ビルが頼んでる万引きGメンの人に頼んでいるんですが、一緒に処理したことがあるから、なんとなくわかりますし」
「いや、今回の場合、万引きじゃないし」
みなみがまた茶化した口調で、口をはさむ。彼女はすでに問題解決したような感じで、少し楽しそうにさえ見えた。
「むしろ、本、増えているし」
「確かに」
「だからこそ、話しにくいんですよ。なんて、ご注意したらいいのか……」
「黒岩さんに同席してもらうとか。でも、女がいた方がよくないですか」
「はい。黒岩さんに来てもらうと、ちょっと大げさになってしまって、二宮さんもお気の毒ですし」
篠井はまた、はあ、とため息をついた。
「だから、私が行ってあげますって」
乙葉はいつもしっかりした篠井があまりにもつらそうで、もう少しで彼の背中を叩いてしまいそうになった。
たぶん、彼のような人は、人の悪意……今回の場合、二宮公子がなんのためにこんなことをしたのかはわからないが……に弱いのだろうと思った。
「ああ、あたくし」
「え」
あまりにもすんなりそう言ってうなずいたので、篠井が聞き返した。
「それは、あたくし」
「……二宮さんが置かれたということですか?」
「はい」
「……何か、間違われたのですか。忘れて置いていった、とか」
「いいえ」
二宮公子は首を振った。
「あたくしが自分で置いていったの。蔵書印がない本を」
ものすごくはっきりした自白だった。
今夜も彼女は赤いコートを着ていた。
すんなりとした体形に、それはとてもよく似合っていた。白い髪はきれいに結い上げられて、首にはパステルカラーの大きなビーズでできたネックレスが巻かれていた。高いものではなさそうなのに、いや、だからこそ、彼女にしっくり似合っていて、センスのいい人だと強く印象づけた。
場所は高木幸之助の本棚の前だった。本当は会議室兼応接室を使うつもりだったのだが、その前の椅子に座って本を読んでいる二宮を見た時、篠井が小さな声で「ここでお話を聞きましょう」と言った。
確かに、他の客はいなかったし、もしかしたら、故人の本の前の方が、素直に本当のことを言うんじゃないか、と乙葉も思った。
「ええと……」
篠井は視線を泳がせていた。白状させようとここに乗り込んだ本人が一番戸惑っている様子なので、代わりに乙葉が尋ねた。
「今までも、こういう本が見つかっていたんです、ここ数ヶ月……それも二宮さんの犯行ですか」
すると彼女はちゃんと処理している、細い眉をきりりと引き上げた。
この眉、どこかで見たことあるなあ、と乙葉は思った。ああ、確か、古い映画で見たスカーレット・オハラの眉だ。
「犯行? まあそうね……あたくし以外に、こんなことをしている人がいなければね」
思わず、乙葉と篠井は顔を見合わせた。
「前のは、太宰の文庫本とかでしたけど」
「ああ、じゃあ、やっぱりあたくしだわ」
「なるほど」
篠井が重々しくうなずく。
「どうしてそんなことを?」
すると、二宮は自分が持っていた本を膝の上にのせて……それは高木の蔵書で、ロバート・B・パーカーの『初秋』だった……目をつぶり、じっと考えた上で言った。
「他に置くところがなくてね」
「置くところ?」
乙葉と篠井は同時に言ってしまった。
「あたくしの部屋は狭いものだから、本を置くところがないのよ」
「あ、そういうことですか」
篠井は小さくため息をついた。ちょっとほっとしたみたいだった。彼女の行動が犯罪や悪意ではなく、一応、説明ができる……自分の家が狭いからと言って、うちの図書館に置くことが正常なことかはわからないが……ことがわかって。こちらを混乱させるために蔵書印がない本を置くような悪意より、少し困ったおばあちゃんが本を置く行為の方が、篠井には受け入れやすいらしい。
「それでしたら、先にお話ししてくださればよかったです。本を寄贈してくださるとおっしゃれば、こちらでも対処できましたから」
「じゃあ、高木パパの本の隣に置いてくださるの? あたくしの本を」
「いえ、それは……いいえ。申し訳ないですが、こちらの図書館では置けませんので。でも引取先や処分先をお手伝いしますから」
「でしょ。ここでないどこかに持って行ってしまうんでしょ。そんなの嫌よ」
「そうですか……でも」
「あたくしの本だって、ずっとここにいたいもの」
これはまた、困ったことになったぞ、と乙葉は密かに思った。ここには作家の蔵書しか置けない。ただの老女の蔵書を置くわけにはいかない。それを吞み込ませるのは、至難の業かもしれない。
篠井が黙ってしまったので、乙葉はまた尋ねた。
「二宮さんのおたくには本がそんなにたくさんあるんですか? 読書家なんですね」
あまり深く考えず、話題の一つとして。
「……とんでもない、あたくしは読書家なんかじゃないわ。高木パパに比べたら。ただ、ちょっと本を読むだけ。だけど、本屋からとってきた本がたくさんたまってしまって」
とってきた?
乙葉と篠井は顔を見合わせた。
とってきた、というのはどういう字を書くのだろう、と乙葉は思った。「取ってきた」だろうか、「盗ってきた」だろうか。
「盗ってきた」なら、売り上げスリップが入っていたことの説明もつく。
「あの本は、本屋さんからとってきたものなんですか?」
「そうよ」
二宮はすまして言う。
乙葉と篠井が驚いて声もでないでいると、二人の顔を見て、二宮はあはははは、と高らかに笑った。
「何、驚いているの? 本の万引きは犯罪にならないのよ。花泥棒に罪はない、って言うでしょ。あれと一緒。本はね、皆の回り物なの。あたくしたちが本を読んで物事を学び、それを社会に変換するんだから、かまわないの」
あきれて声も出なかった。
そういう考えの人がいる、昔の人……いわゆる、戦前のエリートの中にはそういう意識がある人がいた、というのは、昔、勤めていた書店の人にちょっと聞いたことがあった。昔の小説にも、どうどうとエリート学生たちが万引きする様子が書いてあったのだそうだ。
時代につれて価値観は変わる。それでもショックだった。こんなにあっけらかんと万引きをまるでいいこと……自分たちの特権のように言われてしまうと。
二宮はなおも笑った。
「あら、若い人には強烈過ぎたかしら。でも、本当よ。だって、高木パパが言ってたんだもの」
「高木幸之助が……いや、高木幸之助先生がそんなことを言ってたんですか?」
彼が生きていた時は、一度ならず、フェアをやったり、彼の本を店頭に並べたりしたことがある……あの時、自分が作ったポップを今すぐ破り捨てたくなった。
「そうよ。昔っから、高木パパみたいな才能ある人たちはそう言ってたのよ」
書店をなんだと思ってんだ。その一冊の売り上げを取り返すために、こっちは何冊の本を売らなくてはならないと思ってるんだ。怒鳴りつけるために息を吸い、口を開きかけたところで、篠井が乙葉の腕を軽く取った。顔を上げると、小さく左右に振る。ここは我慢してください、という合図だろうと思い、気を鎮めてやっと息を吐いた。でも、その代わりに涙がにじんできた。
「……本の中には、というか、この一冊以外は古本でしたよね。それも盗ってきた本なんですか?」
「そうよ。前はこのあたりの古本屋で盗ってたの。昔、高木パパが生きていた頃は一緒に行ったこともあったわよ。だけど、最近、どこも店に入れてくれなくなってね。それで、新しい本屋さんに変えたの」
古本屋の方で気がついて、出禁にしたのか……乙葉はそこではっと気がついて、おそるおそる尋ねた。
「……もしかして、うちからも本を盗っていたんですか」
こんなに本を盗ることに罪悪感がないなら、ここから盗んでいてもおかしくはない。見つかってないだけで、盗られていたのかもしれない。
「盗るわけないじゃない」
二宮はきっぱりと否定した。
「だって、大切な高木パパの本だもの。それを盗ってしまったら、ファンの方が困ってしまうじゃない。ファンは大切なんだから」
篠井が隣でほっと息を吐いていた。安心したんだろう。
「でも、他の人の本は?」
「……他の人? 他の作家の蔵書ってこと? 盗りゃしないわよ。高木パパの本以外はなんの興味も価値もない」
「よかった」
思わず、声が出た。
もちろん、嘘をついているのかもしれないが(実際、古本屋や新刊書店で他の人の本を盗っているわけだから)、今のきっぱりした否定の仕方はある程度信じてもいいような気がした。
「他の作家なんて、糞よ。他の作家の印鑑が押してある本なんて、老いたりといえども二宮公子が盗るわけないじゃない。気持ち悪い」
ぶつぶつと一人ごとのように続けた。
筋が通っているような、いないような主張だと思った。
いずれにしろ、この人をこれ以上、ここに入れるわけにはいかない。でもそれをどうやって伝え、どうやって行えばいいのか、わからなかった。正子や亜子にも相談して……この図書館の人たち、北里や黒岩も含め、皆で話し合えば大丈夫、できる。
そう考えたら、ちょっと元気が出てきた。
「……あの、二宮さんは高木先生の……恋人だったんですよね」
愛人と言ったらさすがに申し訳ないかと思って、そういう言葉を使ってみた。
「そうよ」
「それで、この図書館に通っていらっしゃると前に聞きました。他の者から……」
「だからどうしたの?」
二宮は肩を怒らせ、好戦的と言ってもいいくらいの調子で答えた。
「高木先生の本の近くにいたいっておっしゃっていると聞きました。いつも高木先生の本だけを読んでお過ごしですか? 他には?」
そう尋ねたのは彼女の気をなだめるために少し話を変えたかったのと、ここで彼女がどのように過ごしているのか知っておけば、蔵書印のない本を探しやすくなるかもしれないと思ったからだった。
「……そうよ」
あまり深い意味もない質問だったけど、二宮は一瞬、本当に一瞬だけど、黙ってまぶしそうに目を瞬かせてこちらを見た。
なんだろう、この違和感は……。何かわからないけど、彼女を困らせた感覚があった。
「……違いますよね」
篠井が小さな声で言った。
「え」
そこで篠井が口を挟んだことに、二宮よりも乙葉の方が驚いてしまって、声を上げた。
「違いますよね。ただ、本の近くにいたいとか、それだけの理由ではないはずだ」
「何を言っているの?」
「もちろん、本の近くにもいたいでしょう。でも、そんな純粋な理由だけではない。僕はわかっていました。ずっと。でも、それは別にかまわないと黙っていたんです」
「篠井さん、どういうことですか?」
乙葉が尋ねた。
「プライバシーの問題だから、と思って誰にも言わずにきました。だけど、この図書館をこんなふうに汚されるのは許せません。蔵書印のない、それも盗品をここに置くなんて」
篠井は乙葉の方をちらっと見た。
「ここにいるのは図書館員の樋口さんだけだから言いますね。いいですよね? あなたはずっと本を捜してましたね。高木さんの、ある一冊の本を」
二宮は目を伏せていた。それはイエスにもノーにも見えた。言い返したり、抵抗はしてこず、ただ、その体が一回り、小さくなったように見えた。
「僕、気がついたんです。ここにいる時、あなたはいつも隠れて手紙を見ながら本を捜していた。古い手紙です。でも、誰かがこの部屋に入ってくると慌ててしまってしまう。何か、大切な秘密の手紙じゃないかと予測していました。あなたに気がつかれないように、時々、遠くから見ていました。でも、手紙を読むというより、いつも本と見比べている。それで、これはきっと書籍暗号を、その鍵になる本を捜しているのではないかと思いました」
二宮は何も答えなかった。
「書籍暗号って?」
乙葉は尋ねた。
「書籍や文章を鍵とした暗号です。それを交わす人はお互いに、同じ書籍の同じ版の本を持たないといけないけど、それ以外の人は膨大な本の中から捜さなくてはならないし、たとえ、鍵をなくしても本によってはまた手に入れることができます。古典的だけど、意外と利便性が高いものなんですよ」
「へえ。知りませんでした」
「手紙の方には数字が書いてあって、ページ数や行数、上から何番目の言葉や文字なのか、ということがわかるようになっています」
「では、知らない人から見ると数字だけの手紙なんですね」
「そうです。二宮さんはなんらかの形で、誰かの……まあ普通に考えたら高木さんに関係する人の書籍暗号で書かれた手紙を手に入れたんですよね? そして、それを解くためにここに来た。まあ、普通に考えたら、相手は奥様じゃないですよね。一緒に住んでいた奥様なら、暗号を交わすような必要はない」
二宮はやはり、何も言わず、じっと下を向いていた。
「手紙のお相手は誰ですか」
答えなかった。
「まあ、いいです。そのこと自体は正直、僕たちには関係ありません。でも、僕は思っているんです。その書籍暗号、もう解けているんじゃないかって」
ずっと反応のなかった二宮がここで初めて、はっと顔を上げた。
「どうして?」
「だって、もうあなたがここに通うようになって数年です。高木先生のすべての本を見なければいけなくたって、さすがに調べられたでしょう? あなたが愛人で高木先生の近くにいた人ならある程度、予想はついただろうし。鍵は高木先生が好きだったり、愛読していたり、なんらかの思い入れのある本にするでしょうから」
彼女はしばらく黙っていたが、急に笑い出した。篠井と乙葉は顔を見合わせた。ついに、この人は頭がおかしくなってしまったのかもしれないと少し怖くなった。
「……それがそうじゃなかったの」
でも、高笑いした後、二宮は答えた。
「そうじゃない?」
「すごく時間がかかってしまった。最後に調べた本だったから」
「最後だったんですか」
「この本だけは違うだろうって、後回しにしてた本だったの。だからなかなか見つからなかった」
「そうだったんですか。高木さんが好きな本じゃなかった?」
「いいえ、逆。一番好きで、一番愛した本だと思っていた……あたくしがプレゼントした本。いえ、あたくしが教えてあげた、と言うか。いい本だから読んでみてって。それが鍵だった」
「なんの本ですか」
乙葉は尋問というより、むしろ興味をひかれて尋ねた。
「……武者小路実篤の『愛と死』」
「ああ」
篠井はすぐにうなずいたけど、乙葉は読んだことがなかった。
「あんな短い本だったんですか」
「ええ。だって、愛してるとか、君のためなら死ねる、とか、その程度の手紙だったから、十分だったんでしょう。あたくし、我慢できなくてあの本を持って帰って捨てました。そしてその代わりに」
「太宰の本を置いておいたのですね」
「ええ。ちょうど持っていたし、同じくらいの厚さだったから」
置き本はそこから始まったのか。
「やっぱり、ここの本を盗っていたんじゃないですか」
「違うわよ、だって、あの本はあたくしがあげたんだもの。あたくしの本だもの」
「どういうことですか」
「相手は彼の新しい愛人でね……高木パパの奥さんが亡くなったあと、あたくしはパパと半同棲するようになったんだけど」
仮にも愛人からもらった本を他の愛人との恋文の暗号の鍵にするなんて、高木もひどい男だ。いや、だからこそ、使ったのだろうか。気がつかれないために。
「それより、どうして、暗号が解けたあともここに来ていたんですか。もう必要ないでしょう?」
今夜の篠井はどこまでも残酷なようだった。見事なまでに、彼女の言葉をさえぎった。二宮の方はもっと話したそうに口を開いていたのに。
もしかしたら、彼女は私たちに話を聞いてもらいたかったのかもしれない、と思った。愚痴や思い出話を。でも、篠井はそれを許さなかった。
「……他に行くところがないから。寂しくて。ここに来たら、本があって若い人がいる」
乙葉は思わず、目をそらした。
そう。彼女には他に行くところがないのだ。長い夜の時間を潰すための。
長いこと、妻がいる人の愛人をし、万引きをし、家族もいない。
そして、その場所も、たぶん今夜、永遠に失うのだ。