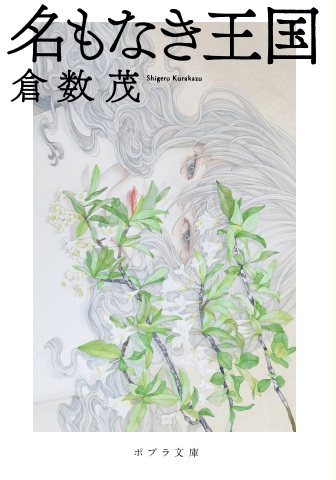巻頭に、作中人物の「私」が記した「序」がある。最初の一行は、〈これは物語という病に憑かれた人間たちの物語である〉。倉数茂『名もなき王国』は、読み進めるうちに、作中人物だけでなく読者もが物語という病に憑かれてしまう、不思議な小説である。
主人公は無名の小説家である「私」、四十九歳。彼はある時、同じくマイナーな三十代の作家、澤田瞬と出会う。初対面ながら意気投合した彼と好きな作家や小説について語り合ううちに、「私」は驚きの事実に行き当たる。かねて敬愛していた女性作家、沢渡晶が、瞬の伯母だと判明するのだ。
すでに故人である晶は、一九六〇年代から七〇年代にかけて短篇集を二冊出しただけの幻想小説作家で、今はすっかり世間から忘れ去られている。「私」は瞬から、これまで入手が難しかった彼女の作品や、存在すら知らなかった掌編のPDFを送ってもらう。世の中の片隅でひっそりと小説を書いていた優れた作家がいた、という設定は本好きとしては垂涎ものであり、これは「私」が彼女を再発掘するために書いた体の一冊だろう、と最初は思う。だが、本作は彼女の生涯と作品を追うだけの内容ではなかった。
第一章の「王国」では、「私」と瞬の邂逅や、瞬が明かす沢渡晶の略歴や幼い頃の瞬から見た伯母の思い出などが語られる。澤田家は代々続いた医者の家で、晩年の晶は元診療所だった古く広い屋敷に一人で暮らし、家や庭をこどもたちに開放していた。その敷地のことを、彼女は「王国」と呼んでいたという。 第二章で主に語られるのは、瞬と妻が離婚に至るまでの経緯だ。第三章では瞬が書いた中篇「かつてアルカディアに」が紹介される。これはディストピア小説風で、奇病が蔓延したために外部から遮断された町に暮らす少女が主人公。突然現れるドッペルゲンガー、昏睡状態のまま老いることのない祖母、そして外部からやってきた老人……奇妙なことが次々起きる。瞬は前章で、この作品の主題は「わたしがわたしであることの不思議」と語っているため、作者のその思いがどのように反映されているかを探りながら読むこともできる。
第四章は晶による中篇「燃える森」だ。一九六〇年代頃と思われる時代が舞台。病院を経営する長兄、結核を患っていた次男らと暮らす女性、寧子の日常が綴られ、晶自身の実体験が投影されていると思わせる。
第五章では晶による掌編「少年果」「螺旋の恋」「海硝子」「塔(王国の)」が並ぶ。どれも幻想的な味わいで、非常に美しく、そして危うい。
そして第六章「幻の庭」では、再び「私」の物語へと戻る。中国の大学で教えていたが首になり、四十代で日本に戻って無職となり、デリヘルで働く女性たちのドライバーの職に就いてからの日常や、当時大学院生だった妻との出会いなどが明かされながら、再び現在の瞬との会話が立ち現れ、彼に語ったプロットが小説として挿入されていく。
どの作中作も、三人の作者の人生や考え方が事前に明かされているため、読み手は創作の裏側を感じ取りながら読み進める醍醐味もある。ただ、本作は、「架空の作家と、彼らの創作が作中作として登場する長篇」という言葉だけで片づけられるものではない。それだけだったら、著者が書き溜めた短篇を体よく長篇の形にしただけの作品に思えてしまうだろう。そうではないのだ。
第一章や最終章で「私」と瞬が何度も書くことやフィクションについての議論を交わしているため、読み手は次第に、虚構とは一体何か、現実とは何か、という思いにとらわれ、翻弄されていく。そもそも、先述のように巻頭の「序」が「私」が書いたものという時点で、そこからすでに、虚構という迷宮にはまりこんでいるのだ。そして最終章の最後の最後で、読者ははっとする――いや、ぎょっとすることになる。
タイトルにある「王国」という言葉は、最初は沢渡晶にとっての「王国」を指しているだけの印象だ。だが次第に、この作品の中には、さまざまな形で「王国」が遍在していることに気づく。誰かの記憶の中の大切な場所であり、誰かが作り出す物語という虚構、喪失を抱える人間たちが探し求めるここではないどこか、それらすべてが「王国」なのだ。そして小説家だけでなく、私たち誰もが、自分というフィルターを通して世界を見ることによって、一人一人異なる虚構、一人一人異なる「名もなき王国」を持っているのではないか、という気持ちにさせられる。
著者は以前インタビューで、「現実と物語の関係に興味がある」と語っていた。人が現実の自分の物語を語る時、そこに虚構は紛れ込むだろうし、人が何かしらの虚構を語る時、そこにはきっと、語り手の実人生の欠片が紛れ込む。そんな現実と虚構の境界線上には、いったい何が横たわっているのか。そこに関心を寄せる著者の特性がよく表れているのが本作だといえる。倉数茂という作家を知るためにも、重要な一冊である。
Profile
瀧井朝世(たきい・あさよ)
ライター。さまざまな媒体で、作家インタビュー、書評などを担当。著書に、『偏愛読書トライアングル』(新潮社)、『あの人とあの本の話』(小学館)、『ほんのよもやま話 作家対談集』(文藝春秋)、監修に、「恋の絵本」シリーズ(岩崎書店)などがある。