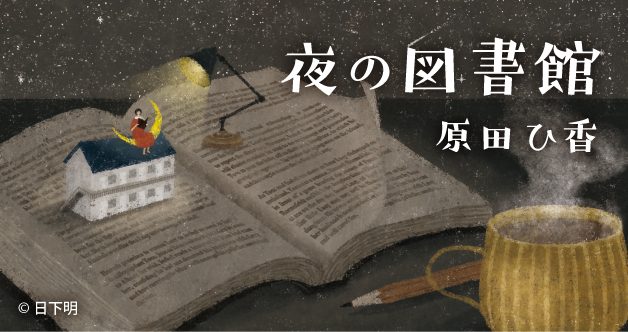二宮公子の事件のあと、夜の図書館は長いお休みに入った。
篠井の提案を元に何度か館員たちで話し合い、まず、最初の三週間を使って蔵書整理とチェックを行い、あとの一週間を図書館員の長期有給休暇とすることにした。
夜の図書館は静かに、世間から門を閉じた……。
乙葉にはそんな感じがした。
研究者やライターさんからは引き続き使わせてほしいという要望は当然あった。篠井は一ヶ月フリーパスの代金の全額返金、必要な情報についてはメール等で丁寧に対応する、という条件で急な閉館を呑んでもらった。説明を尽くせば、皆、快く了承してくれた。
蔵書整理の間も、普段と同じように午後四時から深夜一時までの勤務にする、というのも話し合いで決まった。お客様が来ないのだから、九時から五時にしてもいいのではないか、という意見もあったが、一度夜型に慣れた身体を一ヶ月ほど普通にし、また夜型に戻すのはむずかしいという正子の意見が通った。
図書館探偵の黒岩や受付の北里舞依、食堂の木下たちは出勤も休暇も自由だ、ということになった。黒岩と木下は一ヶ月間、休みを取ることを選んだ。
「退職してからもこんなに休みをもらったことはないので、妻と旅行でもします。息子が北海道に住んでいるので遊びに行こうかな」
会議に呼ばれた黒岩がそう言った時、小さなざわめきが立った。乙葉は心の中で「黒岩さん、奥さんいるんだ」「家族いるんだ」と思ったが、たぶん、他の館員の驚きも多かれ少なかれ同じようなものだっただろう。
木下は特に理由は言わなかった。これまた、木下らしかった。
北里は出勤を選んだ。
「わたくしはよろしければ、基本的には皆さんと同じように出勤します。出入口の施錠をしなければならないし、蔵書整理も手伝えることは手伝いますので」
他の人がどう考えるかわからなかったが、乙葉は少し意外に思った。いつもクールな彼女が図書館員たちと仕事をともにする、とは考えていなかったからだ。
図書館員としてのキャリアが長い正子が、今回の責任者になることに全会一致で決まった。正子の指名もあって、みなみが副責任者に任命された。正子の指揮と指導の下、蔵書整理が始まった。今までも行われていたことだが、乙葉と徳田には初めての経験だったので丁寧に説明された。
「どの図書館でも一年に一度くらいはすることですからね」と彼女は蔵書整理の一日目、皆を前にして言った。
「特別なことではありません。でも、大切な仕事です。図書館の本がお客様の求めに応じて迅速丁寧、確実に提供されるためには、本が正しい場所に置かれていなければなりません。今回は紛失したり、よけいなものが入ってる可能性もあります」
正子は皆を見回した。
「正直、紛失はそうむずかしいことではないのです。所蔵データと資料を突き合わせればおのずと見えることなので……だけど、よけいなものが入っているというのは普通の図書館ではあまりないことで、少し注意が必要です」
「そのために作家さんお一人お一人の担当を二人ずつ決め、資料の突き合わせを行うことにしました。終わったあとは改めて、各作家さんごとに蔵書の数を数え、データと突き合わせます」
みなみが正子の横で声を張り上げた。緊張しているのか、声が裏返り、彼女は顔を赤らめた。
「……ええと、この資料数の確認だけは担当とは別に複数の館員が関わるようにしてください」
みなみは軽く咳をして声を整えてから続けた。
「よろしくお願いします」
説明が終わると、二人は皆に頭を下げ、皆、軽く拍手した。
始まってしまえば、この期間は悪くない時間だった。少なくとも乙葉はそう思った。 午後四時に出勤して、二人一組で蔵書を確認し、数を数えた。その組み方も、最初は正子と亜子、みなみと乙葉、篠井と徳田、そして、渡海と北里のペアだったが、数日で別の人に変わった。
「ずっと同じ人と組んでいると、慣れが出てきて、間違いにつながりますから」と正子は説明した。
蔵書印以外、請求記号やバーコードなどは付けていない本を整理するのは、普通の図書館の倍の時間がかかるだろう、というのが正子たちの見立てだった。
「普通の図書館でも、閉架書庫の整理を含めると、一年一回でだいたい三回分の蔵書整理期間、つまり三年ですべての蔵書をチェックするくらいのスケジュールを組みます。それを今回はいっぺんにやってしまうのですから」
休日はみなみの部屋に集まって、『赤毛のアン』のドラマの続きを観た。こんな時間がいつまでも続けばいいな、と乙葉は思った。
期間中、乙葉と篠井だけは図書館の外で人に会った。
高城柚希の妹と話し合って、蔵書印のデザインを決めなくてはならなくなったのだ。あのマンションから引っ越し、処分するのでその前に来て欲しい、という連絡があった。明言したわけではないけれど、彼女は関東を離れるのではないか、と篠井は言った。
妹が指定してきた日の昼間、篠井とともにマンションを訪れた。本を運ぶ必要はないので、二人で電車を乗り継いで、武蔵小杉のタワーマンションまで行った。
電車の中で必要最小限のことしか話さなかったが、特に気詰まりだったり、落ち着かなかったりすることはなかった。同僚と言えばもちろんそうだが、そこを超えた、家族とも兄弟ともつかない、妙な連帯感があるような気がした。
ただ、それは自分一人が感じているだけかもしれない、と思うと乙葉は少し寂しくなった。
高城柚希の部屋は相変わらず散らかっていて、もねと呼んで欲しいと言っていた妹はジャージ姿でぼんやりしていた。前と同じようにリビングに通された。
蔵書を取り払った本棚はがらんとしていた。ものがなければ少しは片付いたふうに見えてもいいのに、大型の本棚に一冊も本がなく部屋が汚れていると、まるで泥棒が入ったあとのようだった。
篠井が用意してきた蔵書印のデザイン表を見せた。何か特別な希望がなければ、フルネームを入れる形でいくつかのひな形がある。選ぶのは、陰陽(文字が白く浮き出るか、線で浮き出るか)と、縦書きと横書き、書体はどうするかくらいだった。
「あんまりぱっとしないね」
一目見て、彼女は言った。
「これは一番、シンプルな形です。何かご希望の案や絵などがあれば、入れることはできます。例えば、故人の好きなものなどのイラストを加えることも」
すかさず篠井が申し出ると、彼女は首をかしげた。
「別にないけど……」
それまで黙っていた乙葉もつい口をはさんでしまった。
「蔵書印は一度押してしまうと変えることができません。後悔のないように……」
「後悔?」
案の定、もねはこちらをいぶかしげに見た。眉と眉の間に深くシワが刻まれていて、その表情に気持ちがひるんだけれど、勇気を出して付け加えた。
「いらっしゃるお客様は本を手に取って、次に裏を広げて印を見られることが多いです。結構、本や作家の印象を左右するんです。蔵書印が……」
関係ないよ、興味ないよ、と言い返されると思ったけど、意外と彼女は素直にうなずいた。
「なるほどね」
「生前の作家さんを偲べるような印だと、皆さん、喜ばれます」
「……本が好きだったんだよね……でも、それは普通だよね、作家だったし」
「本のデザインをモチーフにして名前と組み合わせることもできます」
篠井が説明した。
「そうなの?」
彼はシンプルな蔵書印の隣に、鉛筆でささっと本の絵を描いた。表紙の部分に「高城柚希」と書き入れた。
「下手な絵ですけど、だいたいこんなふうなイメージです」
「ふーん」
もねはじっと見ていた。
「いかがでしょう? 他に好きな花や果物、動物なんかがあれば、それを使うことができます」
「猫は好きだった……アレルギーで飼えなかったけど」
「猫? もちろん、猫を入れてデザインすることもできます。そうなると、デザイナーに確認しなければならないので、一度持ち帰って、デザインしたものをメールなどで送りましょうか……?」
「あ、夏目漱石の本みたいにできる?」
「『吾輩は猫である』の初版本ですか……?」
「いえ、有名な裸の猫人間みたいのじゃなくて、カバーの下の金箔とオレンジの絵だけど……」
「ああ、あれ、きれいでかわいいですよね」
篠井ともねの間で会話が進んでいるので、乙葉はすぐにスマートフォンで該当の『吾輩は猫である』の初版本を検索し、画像を出した。
「ああ、こういう感じ」
もねは乙葉が差し出したスマホの画像にうなずいた。
「書体もこれに近づけますか」
『吾輩は猫である』の丸みを帯びた書体を指さした。
「そうね……いいかもね」
「じゃあ、ちょっとこのイメージで、デザイナーに聞いてみましょう」
彼女は嬉しそうにうなずいた。これまでで一番、良い顔をしていた。
篠井と乙葉は一緒に家を後にした。タワーマンションのエレベーターの中で、乙葉は言った。
「あの人、本当に、ゆずぽんと仲が悪かったんでしょうか。とても、そんな気がしない……気がしないような時があって」
「ん?」
篠井は不意を突かれたようで、首をひねった。
「そうですか?」
「すごく仲が良かったか、でなければ、近い考え方を持っていたような気がします」
「へえ……?」
「ゆずぽんは作品以外には、エッセイやSNSなどで一切自分の考えを述べるようなことはしていません。だけど、初期の頃、ネット上で作品を書いていた、本当に初期の初期、わずかな時間だけ、ネット小説と連動したブログを書いていたんです。ネット小説ではそうやって人を引きつけてアクセス数を稼ぐことがあるので……でも、すぐに人気が出てやめちゃったんですが」
「ほお」
「本当に数週間です。でも、それを全部、スクショしていた人がいて、一部がネットに出回っているんです」
「ええ」
「そこに出ていたことを、あの人に言われたんです。あの妹さんに」
それはトイレの掃除についてだった。女だから、トイレの仕事に立候補したの? ともねに聞かれた時に言っていたことと同じだった。イスラム社会ではトイレ掃除は女や奴隷の仕事だと。
高城柚希は憤っていた。そんなことおかしい、女がテロ犯人以下なんて、と。
「それは妹さんだから、同じような考えを持っていたり、話をしていたのかもしれませんね。もしくは妹さんもそれを読んで賛同していたとか」
篠井はどこか慰めるように言った。
「ええ。でも、小説の中に出てくるようなことならともかく、そんなちょっとしたところの考えまで似るでしょうか。あの人のものはすぐに処分して、お金にしたい、というほど嫌がっている人が」
「人は近くにいるほど、複雑な感情を抱くものですよ」
「……ですよね。でも」
そこで、マンションのエレベーターが一階に着いた。
二人でそろって外に出てからも、乙葉はやめられなかった。
「すみません。でも、どうしても信じられなくて。本当に高城柚希は死んだんですよね?」
「と、思います。僕がその死に顔を確かめたり、死亡診断書を確認したりできたわけではないですけど、でなければ、大手の新聞社が死亡記事書いたり、出版社がそれを発表したりできるでしょうか」
「そうですよね……」
「それに、なんで死を偽装するような理由があるでしょう。小説家をやめたかったら一時期だけ休むとか、引退することもできますよ」
「わかってます」
乙葉は頭をがっくり下げて、篠井のあとについていった。
「樋口さんご自身は本当のところどう考えているんですか……高城柚希とあの妹さんの関係」
しばらくして武蔵小杉駅に向かう途中、篠井が尋ねてくれた。
その声は優しくて、質問と言うより、乙葉の気持ちを聞いて整理してくれようとしているみたいだった。
「……もしかして、高城柚希というものそのものがあの妹さんなのかな、とも思ってたんですが」
「はい」
篠井は肯定も否定もせずにうなずいた。
「でも、篠井さんが言うように、誰も死んでいないのに死亡発表をすることはさすがにできない気もします。その辺の仕組みはわかりませんが、万が一、生きていたのに死亡情報を流していたら、バレた時ご本人だけでなく出版社も非難されるでしょうし」
「ですね」
「だけど、例えば、二人の作家が一つのペンネームで書いていたら……? 何か役割分担があるとか……そうでなくても、高城柚希はさまざまなジャンルの小説を書けることで有名でしたから」
「なるほど」
「で、片方が亡くなったので、死亡記事を出して、一度、高城柚希の作家生命は終わりにしたのかも」
「……まあ、可能性はなくはないですけどね。でも、せっかくの高城ブランドというか、そういう名前を捨ててしまうのはもったいないような気がします。まあ、僕のような凡人と先生のような天才では考え方が違うでしょうが」
「まあ」
「蔵書をすべて処分するっていうのももったいないですよね。別にそこまでする必要ないし」
「そうですけど……例えば、まあ、心機一転、みたいな?」
「あれほど、妹さんが何か怒りを抱えているというのも不思議です」
「それは演技とか」
「あの怒りは本物と思いました。僕も愛する人が急にいなくなったら同じように悲しむだけでなくて、憤るかもしれない」
「まあそれは、そうですが」
篠井が「愛する人」という言葉を使ったことと、憤るほどに愛する人がいるのだろうかということは意外に思った。話しているうちに駅に着き、篠井が切符を買ってくれた。これは経費にするから、と言いながら。
「……そんなに生きていてほしいのなら」
篠井はホームに上がるエスカレーターの途中で振り返って、乙葉に言った。
「樋口さんの中で高城さんは生きていることにしたらどうですか」
「生きていることに?」
「そう信じることは自由です。死んだと発表しているけど、本当は生きていると。どこかに生きていて、また、作品を発表することもあるかもしれないって」
乙葉は今、行ったばかりのタワーマンションを思い返した。建物のてっぺんは今出てきた場所とは思えないほど遙か遠く思えた。
「思っていいんでしょうか」
「いいんですよ。好きなように思えばいい。僕たちは自由です」
ほんの少し元気が出た気がした。
蔵書整理が始まって一週間ほど経った日、乙葉は昼頃起きて、テレビを観ながら朝食……世間で言うところの昼食を食べていた。観ていたのは前日に録画したミステリーと恋愛が混じったようなドラマで、ヒロインがほのかに好きになっている相手を犯人ではないかと疑っているシーンが延々と続いていた。
「いいかげんに気づきなよ。犯人は彼じゃなくて、彼のお兄さん!」
乙葉がテレビに向かって小さく叫んだ時、そっとドアを叩く音がした。
同じ寮の人か実家からの小包かなと思ってのぞき穴をのぞくと、そこには自分と同じくらいの歳の知らない女性が立っていた。いったい、誰だろうといぶかしみつつ、ドアを開けずに「どなたですか」と尋ねた。何かを言っている気配はするのだが、名前までよく聞こえない。仕方なく、チェーンをつけたまま、ドアを開けた。
セミロングの髪に、カーディガンとロングスカートというごく普通の服装の女性だったが、背が高く、がっちりした体型をしている。そのためか、とてもしっかりして世話好きな人に見えた。体育会系の部活で副キャプテンか何かをしているような。
「すみません、どなたですか」
もう一度尋ねると、彼女は言った。
「岩崎と申します。前にここに住んでいた小田早穂の友人です。ここに置いてきたものがあるそうで、代理で取りに来ました」
「あ」
この部屋に来た日、クローゼットの中に段ボール箱が一つ置いてあって、前任者が取りに来ると篠井が言っていたことをすぐに思い出した。
「彼女によると段ボール箱……ミカンが入っていた箱だって言ってたんですけど」
大きさも話も合っている。
「あの、それここにありますけど、いいですか。一応、上の人に確認しても」
「わかりました。こちらも一応、早穂の身分証を持ってきました」
彼女は写真入りの自動車免許証を乙葉に見せた。おとなしそうな女性が写っている。歳は乙葉の一つ上だった。
「あの、ひっくり返してもらえると、ここの住所が書いてあります。一度、住所変更して、また実家に戻っています」
彼女の言葉通り、確かに免許証の裏側に住所の記述があった。
これだけで、十分、彼女の証明はできたと思ったけれど、一度、ドアを閉めて篠井に連絡し、事情を説明した。
「なるほど、確かに、小田さんの代理人のようですね」
乙葉の説明を聞いて、篠井も納得した。
「お渡しして、大丈夫そうです」
乙葉はクローゼットの中から段ボール箱を取った。今までそこから動かしたことはなかった。中身はほとんど入っていないようで、拍子抜けするほど軽かった。
「どうぞ」
もう一度、ドアを開け、今度はチェーンをはずして段ボール箱を渡した。
「ありがとうございます」
岩崎と名乗った女性はお辞儀をして受け取った。
「……季節物の服が入っているらしいです」
「そうなんですか」
それ以上、なんと答えていいのかわからなくて、乙葉はうなずいた。
「お世話になりました。ありがとうございました」
彼女はもう一度お礼を言って、頭を下げた。
「では……」
乙葉がドアを閉めようとした時、岩崎が「あの」と言った。
「はい?」
「ここ、おかしいことないですか」
「え?」
おかしいこと? それはこの寮でということだろうか、図書館でということだろうか。図書館でということなら、まあ、おかしなことだらけ、とも言えるが。
「ここです。この部屋です」
岩崎は段ボール箱を持ったまま、顎の先で床を指すようにして言った。
「おかしいこと、ですか……? 部屋の設備とか間取りですか? それとも幽霊的なことですか?」
「幽霊と言うか……」
岩崎は少しだけ乙葉に近づいて、声を潜めた。
「早穂、この部屋になんかいる、なんか出る、って言って、ずっと怖がっていたんです。自分がいない時に誰か部屋にいる気がするとか、誰かが部屋に入ってきていた気配があるって。一度なんか、仕事中に忘れ物をして取りに帰ってきたら、隣の部屋から物音がした、とか」
「へえ」
隣の部屋なら、多分、みなみのところだ。
「図書館の人たちにも相談したり、訴えたりしたんだけど、あんまり信じてもらえなくて、実際、何かがなくなったりはしていないので、早穂も証明できなくて。それで、すっかり怯えて、ここをやめてしまったんです」
「そうですか……」
「すごく本が好きで、ここに勤め始めた時には張り切っていたんですけどね」
「私はぜんぜん気がつかなくて。霊感とかもないし」
そうか……やっぱり、早穂の気のせいなのかなあ、と岩崎は首をひねった。
「そのせいもあって引っ越しの時、ばたばたしてて、この荷物も忘れて来ちゃったんだけど、自分じゃ怖くて取りに行けないって言うから、私が来ました」
「そうだったんですか。ご苦労様です」
そうか、やっぱり違うか、と少し残念そうな顔をしながら、岩崎は帰っていった。彼女自身も小田早穂の言うことはあまり信じていないようだった。
その日の出勤時、乙葉は何気なく……本当にふと何気なく思いついて、図書館の出入口の大理石の壁に埋めてある、蛾の標本の写真をスマホで撮った。毎日のようにそこを通るようになって、怖さも多少薄れてきていた。
「それ、どうするんですか」
受付に座っていた北里が尋ねた。そうしていると、開館していた時とあまり変わりない。
彼女とはこれまでほとんど話すこともなかったが、蔵書整理が始まって一度ペアを組んだこともあり、前よりは言葉を交わすようになっていた。彼女はとても几帳面で、字がきれいで、面倒な仕事も進んでやってくれる人だということもよくわかった。
「なんていう虫か、調べてみようかと思って」
「わかるんですか?」
「画像検索をかけてみようかと」
「へえ」
彼女はやはり興味なさそうにうなずいた。
図書館の中に入りながら、乙葉は自分が撮った写真で検索をかけた。
同じような瑠璃色の蛾の写真がずらりと出てきて、ちょっとたじろぐ。慣れたといっても蛾が木の幹にたくさん張り付いているような写真はやはりぞっとしない。
いくつかの写真の中で比較的似ているものを見つけてはタップして元のページの説明を読んだ。しかし、どれも玄関の蛾とは、よく見ると少し柄が違っていたり、説明文にある大きさとは合わなかったりした。
そんなに簡単には見つからないか……と諦めかけて最後の写真をタップし、出てきた結果を見て思わず、足が止まった。
――MITSUKO・SUZUKII
説明文には「マレーシア原産。日本人女性の名前が学名になっているめずらしい蛾。一説には蛾の発見者である、井田孝三教授と親しい女性の名前とも」とあった。
鈴木……この図書館で聞いたことがある名前だ、と気がつく。この鈴木さんは、スズキミツコさんはこの図書館の関係者なのだろうか。
乙葉は立ち止まったまま上を見上げた。そこには二階まで吹き抜けで、天井まで届く本棚があった。この書架を作ったのも、この「鈴木さん」なんだろうか。でも、鈴木という名前はよくある苗字でもある。
「樋口さん」
後ろから呼びかけられて、はっと驚いて振り返ると、篠井だった。スマホを慌ててポケットにしまう。
「なんですか」
驚いたせいで、ちょっと攻撃的な声が出てしまった。
「いえ、立ち止まっているからなんなのかと思って」
篠井の方がひるんだように尋ねた。
「あ、いいえ。すみません」
「大丈夫ですか」
「もちろんです」
無理矢理、笑顔を作った。
「先ほどはすみません。小田早穂さんの」
「あ、大丈夫です。段ボール箱をお渡ししただけですから。ただ、小田さんの代理の方がちょっと変なことを言ってたんです」
「変なこと?」
「小田さん、あの寮の部屋に何かいるって。なんか、他の人が自分の部屋に入ってきたような気がするって言って、やめたそうですね」
「ああ」
篠井はうなずいた。
「小田さん、ちょっと神経質なところがある方で、あまりここが合わなくて。僕もうまく対処しきれなくて……申し訳ないことをしました」
「そうだったんですか」
「乙葉さんはどうですか」
「え」
篠井に初めて名前で呼ばれて、そちらの方に気を取られてしまった。
「乙葉さんは今の部屋で何か気になることとかありますか?」
「……いえ、別に。特には」
「よかった」
篠井はにっこり笑って、乙葉を見た。
「ここの皆さんが、快適に働いて、過ごされること、それが僕の願いです」
「はあ」
「何かあったら、すぐに僕に言ってください……そうそう、高城柚希さんの妹さんからまた連絡がありましたよ」
「え、なんですって?」
「やっぱり、猫のデザインはやめて、ごくシンプルなものにするって」
「ああ」
乙葉は思った。少し残念な気もしたが、その方が高城らしい気もした。
「また、あの部屋に行くんですか?」
「いいえ」
篠井は首を振った。
「もう、あとはデザインをメールでやりとりすることになりました。あの部屋も売却が決まったそうなので」
「決まったんですね」
乙葉の沈んだ顔を見て、篠井は笑って言った。
「この蔵書整理が終わったら、高城柚希の本の整理もしなければなりませんよ。樋口さんや正子さんたちはまた大忙しです」
「すぐに蔵書を展示していいんですか」
「まあ、他の作家さんと同じように、順番が来たら発表するような感じでいいんじゃないかと思っています。あの妹さんもそれに同意してますし。また皆で話し合いましょう」
「はい」
乙葉は小さくあたりを見回すようにしてから尋ねた。
「あの。お掃除の……いつもお掃除をしてくれている鈴木さんは今どうしているんですか」
「え?」
篠井は乙葉を見た。その顔が硬直しているように見えるのは考えすぎだろうか。
「鈴木さんは、今日はお休みしてますよ。どうしてですか」
「いえ、他の人……黒岩さんや木下さんについてはお休み中、どうするかお聞きしましたけど、鈴木さんについては改めてお尋ねしなかったな、と思って」
「鈴木さんには僕が直接聞きました。基本的にはお休みして、週一回だけ掃除に来てくれることになったんです」
「ああ、そうなんですか。では、あとあの」
「なんですか」
篠井に蛾の標本について尋ねようとして、口をつぐんでしまった。
彼に「オーナーについて詮索するのは、あまりよくない結果を招くと思います」と言われたことを不意に思い出したからだ。
「いえ、なんでもありません」
「そうですか。あ、それでは、これで」
篠井は返事をすると、そそくさと、スタッフルームに入っていった。
※ ※ ※
僕は篠井弓弦、三十三歳。
オーナーは僕の伯母さんだ。
両親は僕が小学校五年生の時に二人そろって死んだ。交通事故だった。
僕は父方の祖父母に引き取られた。この時、僕の親権を巡って父方母方、双方の祖父母が争った。どちらも僕を引き取ると言って引かず、争いは裁判にまで持ち込まれた。結局、父方が勝ち取って、亡き両親から僕が受け取ることになっていた財産とともに、僕は彼らのもとに送られた。
のちに聞いたことだが、母方の祖父母は、父方の祖父母が僕の親権を持ち、同居することに概ね同意していたという。その代わり、一ヶ月に一回以上の面会と長い休みの時に遊びに来ることなどを頼んでいただけなのだが、父方の祖父母の「長男の息子は渡せない」という気持ちはとても堅く、その面会でさえも拒まれて、さまざまな行き違いの末、感情的にこじれてしまったらしい。
それほど切望され勝ち取った親権だったが、高齢だった祖父母は、僕が思春期になると持て余し……全寮制の中高一貫校に押し込んだ。そこは山の中にあって、不良少年の更生ができると有名な場所だった。だけど、その実態はほとんど少年院か刑務所だった。まともな親なら絶対に入れないような学校だった。僕は別にぐれたりしていなかったのに、その評判を知らない祖父母に否応なしに突っ込まれた。教師からの暴力や、クラスメイトからのいじめは日常茶飯事で、地獄のような日々だった。
高校に入った頃、父方の祖父母は二人とも死去した。しかし、家に引き取ってくれるような人もなく、両親の遺産から学費と寮費が支払われる、という連絡があっただけだった。
高校二年生の秋、僕は校長室に呼ばれた。そこには校長先生と、中年男性がいた。
「篠井君、こちらは……」
いつもはただただ機嫌が悪く、朝礼で生徒に檄を飛ばす時だけ生き生きとする校長が揉み手をせんばかりの笑顔で言った。
「弁護士の砂川誠さん、あなたのご親戚の依頼でいらっしゃった」
彼は、僕の方を振り返った。テーブルの上にコーヒーが置いてあったが、口を付けていないということはすぐにわかった。彼は僕を見ると、すぐに立ち上がった。身長が百八十センチくらいあって、胸板が厚かった。その身体をつつんでいるスーツが、校長や教員(ほとんどはジャージを着ていたが)が着ているものとはまったく質の違うものだということは、高校生の僕にも一目でわかった。
「君が篠井弓弦君?」
「はい」
すると、彼は校長に向かって言った。
「部屋から出て行ってもらえますか。彼と二人っきりで話したいので」
「え、いや……」
校長はあまりにも驚いたのか、まじまじと彼を見つめた。
「いや、しかし……彼は未成年でもありますし」
「先ほど、私が彼の後見人だという書状は見せましたよね?」
弁護士は頭の悪い人に対するように、噛んで含めるような口調で言った。
「はい」
「あれ、正式なものだとは言いませんでしたか? 今は私の依頼者が彼の親権者ですので、その人から依頼された私が彼の後見人な訳ですが?」
「まあ、そうですが……」
校長はそれでもしばらく、もじもじとその場にいたが、砂川弁護士がじっとその様子を見ていると、仕方なさそうに部屋から出ていった。つまり、校長が校長室を空けたのだ。
「まあ、座ってください」
彼は、どうどうと、今まで校長が座っていた場所を指さした。自分の部屋みたいに。僕は黙って腰掛けた。
「先ほど言った通りだけど、君の親権は、君のお祖父さん、お祖母さんが亡くなってから、さらに遠縁の人に移っていた。それを私たちが探し出し、私の依頼人が正式な手続きを経て取り返した」
「そうだったんですか」
「依頼人からの伝言です。そういうわけでお祖父さん、お祖母さんが亡くなってからなかなか迎えに来れなくて申し訳なかった、と」
「はい」
「で、正式に親権者になったので、君を引き取りたいそうです」
「……はい」
返事をしてから、僕は黙って彼の顔を見つめた。
「……何も聞かないのかい?」
しばらく沈黙した後、彼は笑いながら言った。
「例えば、何を聞くんですか?」
「依頼人て誰ですか? とか、どんな人ですか? とか」
「依頼人て誰ですか」
僕はそのまま、尋ねた。
「今は言えない」
じゃあ、聞かせるなよ、と僕は思った。
「君にその気があるなら、ここを出て、一緒にその人のところに行くことになっている。少なくともここよりもましな場所だということを保証するし、君が受けたい教育を受けさせてもらえることも保証する。教育を受けたくなかったりその人と合わなくても、二十になれば自由になれる」
「はあ」
「行くよね?」
彼はにこやかに言った。
「どうでしょう?」
僕はどうしたらいいのかわからなくて、首をひねった。
「端的に言って、ここはこの世の地獄なんでしょ?」
「なんで知っているんですか?」
「ちょっとネットで検索した。ここの卒業生たちはこの学校をぼろくそに言っていたよ」
「でしょうね」
「迷う理由がわからない。どこに行ってもここよりもマシだと思う」
「でも、あなたが本当に弁護士かわからないし、もしかしたら人身売買の親方かもしれないし、その依頼人がペドフィリアかもしれないし」
ここではほとんどネットやテレビは見れなかったが、図書館で本は読める。僕は都市伝説の本を結構、愛読していたから、そういうことは一通り、知っていた。
彼はげらげら笑った。
「君、もう十三歳以上だろう?」
「はい。関係ありますか?」
「ペドフィリアって、十三歳以下の子供を相手にすることだろう?」
「はい。だけど、若く見えるとは言われますし……依頼人さんは、ペドフィリアでなくても、いわゆるショタコンというのですか? そういうのかもしれませんし」
「天気はいいし」と言って、彼は外を見た。実際、天気は良く、真っ青な空の下、ジャージを着てだらだらと運動する生徒たちが見えた。
「時間は限られている。君とペドフィリアのなんたるかについてなんて、語り合いたくないんだよ……仕方ないな」
そう言って彼はスマートフォンを出し、何かを検索して、ネットの映像を僕に見せた。そこにはマスコミにもみくちゃにされる外国人と、その人をかばうように付き従って車に乗せる彼が映っていた。
「この人、知ってる? ほら、ジャパン電機の社長の」
少し前に脱税を疑われて捕まった有名な外国人社長の名前を言った。
「彼の弁護士が僕。日本では割に有名な弁護士」
「ふーん」
「顧客も選ぶ。金だけでは動かないって有名なんだよ」
「金でなかったら、何で動くんですか」
「まずはここ」と言って、彼は自分の心臓のあたりを叩いた。「心だよね。自分が納得いく案件でなくてはね。あとは今後の自分のためになる仕事、成長できる仕事」
「ジャパン電機社長の巨額脱税事件があなたを成長させてくれる仕事だったんですか」
「まあ、あれにはいろいろあるんだよ。とにかく、僕にも一応、信用はあるし、信頼できないような人に君を渡したりはしないよ」
「わかりました」
「わかりましたって何が?」
「あなたと行きます」
「これは、また、急だね」
「だって、本当にここよりも悪いところないし」
彼はまた笑った。
数十分後には、僕は彼と一緒に成田空港に向かっていた。ほとんど身一つで。 彼は僕が一緒に行くことを承諾すると、すぐに校長を呼び戻した。
「じゃあ、私たちはこれで失礼します。彼の荷物はまとめて、私の弁護士事務所に送っておいてください」
これには僕も校長も驚き、「え」と聞き返した。
「どうせ、たいした荷物はないでしょ」
人を使い慣れている人の快活な声だった。
「じゃあ、行こうか。車を待たせてある」
「いえ、でも……まだ二学期の半ばですし。他の生徒も驚きます、いや、悲しみます」と校長が焦ったように言った。
すると、砂川は僕の方を見た。
「誰か、お別れの挨拶したい子とか、いる?」
僕は首を振った。僕たちのクラスはひどく荒れていて(というか、学校全体が荒れていたが)、誰が次のいじめの標的になるか、毎日、怯えながら学校生活を送っていたし、お互い疑心暗鬼になっていた。仲のいい友達なんか一人もいなかった。
「じゃあ、篠井君は退学ということにしておいてください。かまわないから」
まだ、ごちゃごちゃ言っている校長を尻目に、砂川はさっさと僕を車に乗せた。タクシーではない、黒塗りの車だった。
車の中で、また、彼から少し話を聞いた。
「僕が言うのもなんだけど、依頼人は君を探し出して親権を取るまでに、そこそこの犠牲とお金を払った。時間もかけたし、人に恩も売った。それから危険もあった」
「お金そんなにかかったんですか? 僕一人に?」
「もちろん。そこらの」
と彼は街道沿いにあるマンションを指さした。
「マンション一個分くらいのお金は使ったと思う」
「それはあなたに払うお金も含めて?」
彼はちょっと苦笑いして、うん、とうなずいた。
「だからなんですか」
「別に。ただ、そういうことはきっと君の依頼人は言わないから、一応、伝えておきたかった」
その時、僕は緊張し始めたことを覚えている。そのお金に見合うようなことを、自分ができるのか、その人を後悔させないのか、見当がつかなかったからだ。
三時間ほどで成田に着いて、彼は近くのホテルの日本料理店の個室に僕を連れて行った。個室のドアを砂川が開くと、窓際に女性が立っていて、外を見ていた。そこからは成田から出たり入ったりする飛行機がよく見えた。
「お連れしましたよ」
彼女は振り返った。母によく似た五十代半ばの女の人だった。
「久しぶり。私のこと、覚えてる?」
彼女がそう言った時、僕はほんの少し泣きそうになった。やっぱり、不安だったんだと思う。なぜ、僕を引き取ろうという親戚が伯母で、そのことを彼らが隠したのか、まだわからなかった。でも、それを教えてくれていたら、あれほど不安な気持ちで、車に乗っていなかっただろう。
伯母は、母と十二も歳の離れた姉だった。両親が死ぬまでは一年に一度くらいは会っていた。伯母は独身で東京に住んでいると聞かされていた。会った時は必ず、なんでも好きなものを買ってくれた。確か、最後に会ったのは両親の葬式だった。
「なんで」
いろんな意味を込めた、なんで、だった。
なんで、伯母だと教えてくれなかったの? なんで、今になって現れたの? なんで? なんで?
しかし、伯母は僕の姿を見ると、首をひねって砂川を見た。
「この服しかないの?」
彼はうなずいた。僕は学校の制服……白い半袖シャツに黒のズボンをはいていた。
「じゃあ、適当に空港の店か、ホテルの売店で服を買ってきてくれる? この格好じゃ、シンガポールには行けないわ。そうねえ、Tシャツとジーンズでいいから。あと、下着も数枚」
シンガポールに行くの? これから?
僕はあまりにも驚いて、何も言えなかった。涙も引っ込んでしまった。
砂川は顔をしかめた。
「……そういう使い走りはしたことがないんだけど。一応、日本で一番有名な弁護士なんだけど」
「じゃあ、あなたの事務所の若い人にやってもらえば?」
「あいにく来てない。あまりたくさんの人は関わらせられない案件なもんでね」
「じゃあ、あなた、お願い。私はこの子と話すことがある」
伯母はテーブルの上に載っていた、えんじ色の革のハンドバッグを開いて、財布を出し、砂川に数枚の札を渡した。仕方なく彼は僕に服のサイズを聞いて、出て行った。
「ごめんね」
彼が出て行くと、それまでの、どこか威張った感じの雰囲気は消えて、彼女は素直に謝った。
「久しぶりだから驚いたよね。でも、これにはいろいろ理由があるし、それは今すぐには話せない。今後、少しずつ説明する。あと、さっきも言ったけど、あなたはこれからシンガポールに行くことになる」
「どうしてですか?」
「今、私が住んでいるところだから」
「シンガポールに住んでるの?」
「悪くない場所だよ。安全だし、ご飯はおいしいし、のんびりしている」
「……僕はシンガポールでどうするんですか?」
「どうしてもいい。そこで学校ややりたいことを探したらどうかしら。あなたが良ければ」
「英語話せないし」
「大丈夫、私もそんなに話せない」
「え」
「どう思う? 高校のこと」
「今、急に言われたんで」
「そうよね。じゃあ、しばらくシンガポールで考えればいい」
「でも、そうしたら、二学期はどうなりますか」
「一年や二年、ぶらぶらしても、人生なんとかなる」
そんな話をしているうちに砂川が戻ってきて、僕は彼が選んだTシャツとデニムに着替えさせられた。そして、彼らが手配していた航空券とパスポートでそのままシンガポールに向かった。
伯母が言った通り、シンガポールはすごくいい場所だった。
彼女の知り合いが貸してくれる、オーチャードロードのキッチン付きのホテル、サービスアパートメントに住んだ。毎日動物園や植物園に行ったり、知り合いの日本人が経営しているカフェの手伝いをしたり、ほんの少しだけ英語学校に通ったりして過ごした。カフェではお給料はもらえなかった。ビザの関係で働くことはできなかったからだ。ただ、お昼ご飯を食べさせてもらって、高級なコーヒー豆をお土産にもらったりした。
僕が進んで学校に行きたがらないことに気づくと、伯母はシンガポールの紀伊國屋書店に連れて行ってくれた。そこで日本の本をたくさん買ってくれた。
「本を読めばたいていのことは学べる。学校に行かないなら、週に一冊読んで、その内容を日曜日の夕食で私に話すこと」
伯母も本が好きだった。暇な時はいつでも本を手にしていたし、本だけは好きなだけ買ってくれた。
そこで三ヶ月ほど経ったある朝、伯母はパソコンを見ながら、「ねえ、次はヨーロッパに行かない? イタリアとか」と言った。
「イタリア?」
僕はコーヒーを淹れながら尋ねた。
「パリでもいいわよ」
僕自身はコーヒーがあまり好きではなかったが、淹れ方はカフェの人に習った。伯母が「うまい、うまい」と褒めてくれるので、それだけが僕が家でしなければならない仕事になった。
正直、ヨーロッパにはぜんぜん行きたくなかった。シンガポールの空気が気に入っていたし、カフェで一緒にアルバイトしている、日本から来た女の子がちょっと好きにもなっていた。彼女に英語を習って、休みのたびにカトンやブギスを案内してもらっていた。
「あなたが高校に行くなら、しばらくここにいてもいいかな、と思っていたんだけど、そうじゃないなら出国したいのよね」
伯母は真面目な顔で言った。
「きっと、すごく気に入ると思う。イタリアだったら田舎で、農家の人がやってるホテルか民泊に泊まりましょう。ご飯がおいしいの」
来年にはまた、ここに戻ってくるから、と言われて、僕はしぶしぶ承諾した。
イタリアもまた素晴らしかった。僕はやっぱり無給で近くのブドウ畑の手伝いをしたり、イタリア語学校に少しだけ通ったり、農家の人に車の運転の仕方を習ったりした。
伯母は英語よりイタリア語が堪能で、僕にも教えてくれた。若い頃、イタリアの美術大学に少し通ったことがあるらしい。
しかし、また、三ヶ月ほど経つと、伯母が言った。
「ねえ、次はカンボジアに行かない? アンコールワットで歴史と美術の勉強をしましょ」
そうして彼女と世界中を旅しているうちにわかったのだが、伯母は「永遠の旅人」と呼ばれる人種だった。ほとんどの国では半年以上の居住で税金の支払い義務が生まれる。その制度を使い、ビザなしで滞在できる国を半年以内で移動し、家や居場所を持たないことによって、合法的に一切の税金を払わない人だったのだ。
ただ、僕と伯母が出会った頃だろうか、そういった「永遠の旅人」たちへの税金の支払いを義務化する制度が世界的な規模でできあがりつつあった。そのため、追及は厳しくなり、日本などで納税義務が発生する可能性もあった。そのため、伯母は極力、人に知られることなく、日本に出入国する必要があり、必要最低限の人にしか、居場所を知らせられなかった。
「でも、あなたが高校に通いたい、と言ったら、どこかで定住することを考えていた。それは本当」
自分の生き方について説明してくれた時、彼女はそう言った。
「だけど、高校に行く気がないみたいだったから」
「これ幸いと利用した?」
「はははは。ばれたか」
しかし、その言葉は思いがけないところで真実とわかることになった。
伯母とは数年間、世界中をぐるぐると回った。ハワイにもパリにも、タイにもインドにも行った。ロンドンでは映画にも出てくる五つ星ホテルに長期滞在したし、マラッカの一泊千円のドミトリーに泊まったこともあった。でも、ほとんどは、知り合いの別荘や民泊に住んだ。
気がついたら、僕の方が英語がうまくなっていて、次に行く場所をこちらから提案したりした。
転機は僕が二十歳になる少し前にやってきた。ある朝、急にベッドから起き上がれなくなったのだ。
「きっと、今までの疲れが出たんだね」と伯母は言って笑った。
当時、僕らはハワイ島に住んでいた。
手伝っているコーヒー農園に僕が一日休むと伯母が電話をかけてくれた。伯母が「今日、ユヅは具合が悪いのよ。そういうの、日本語では鬼の霍乱と言うの」とどこか楽しそうに告げている声を、ベッドの中で聞いたことを今でもよく覚えている。
しかし、次の日も朝起きれなかった。その次の日も、次の日も。
「いったい、どうしたのかしらね? 一応、病院に行ってみる?」
最初はまったく心配していなかった伯母の顔色がだんだん悪くなってきた。
熱もないし、咳も出ない。だけど、身体がだるくてだるくて、起き上がることができないのだった。なんだか、ずっと船酔いしているみたいだった。その前年に僕らは豪華客船に一ヶ月ほど乗っていたから、船酔いの感覚はわかる。
いや、吐き気やめまいはない。だけど、あの、気分が悪くても船から下りれない、絶望的なあの感じと似ていた。精神的な船酔いというか。
近所の人の車を借りて、島の総合病院に行った。診断はすぐに出た。軽いうつ病。
「どうしたらいいのかしら」
これまで、ほとんど慌てたり、焦ったりしたことがなかった伯母が、帰りの車の中で初めて、おろおろした声を出した。
「寝てたら治るよ。薬ももらったし」
僕の方が落ち着いていた。
だけど、そうもいかなかった。それから一ヶ月ほど、僕は部屋にこもり続けた。
伯母は僕をオアフ島に連れて行き、ハワイで一番大きな、評判のいい病院で診察を受けた。結果、長い療養生活に入ることになった。日本語ができる、腕のいい精神科医と精神分析医も見つけた。
僕の病気の原因は、やはり、小五の時に親が亡くなり、親戚が争って、あの学校に入れられ、毎日、神経をすり減らしたことだったようだ。
「私のせいかしら。私が世界中を引っ張り回したから」
伯母はそう言って少し泣いた。
「違うと思う。それに、たとえ病気になったとしても、楽しかったから別にかまわない」と僕は答えた。
「かまうわよ」
「それより、そろそろアメリカから出ないといけないんじゃないの?」
「永遠の旅人」である伯母の期限が迫っていた。
「あなたは何も心配しなくていい」
僕がそのことを問いただすと、彼女はそう答えた。
「あなたと暮らしてわかった。私はあなたのことが世界で一番大切。だから、何も気にしなくていい。私は書類とかは苦手だけど、むずかしいことは全部、砂川がやってくれる」
「でも、お金がかかるでしょう」
「お金で解決できることほど、楽なことはない」
伯母はあちこち連絡して、しばらくハワイに住めるようにしたようだった。納税は当然のことながら、ビザや通院費、莫大なカウンセリング料、いろいろ大変だったはずだ。だけど、伯母はその時、すべてを投げ打って、僕を治してくれた。
カウンセリングには伯母も通った。それもまた、精神分析医が僕らに要求したことだった。僕の病気は、僕一人の問題ではなく、長年に渡る、僕ら親族のことが関係している、と診断されたのだ。彼女はそれも承諾し、僕とは別の時間に、同じ精神分析医にいろいろなことを相談し、話したようだった。
一年ほどして、僕は普通に外を歩けるようになった。その日は、二人でハレクラニの朝食を食べに行った。海を見ながら伯母は言った。
「やっぱり、あなたは、私の妹からの最高の贈り物だった」
「そう?」
「おかげで私の精神まで健康になれた」
治療が終わってからも、僕らはしばらくオアフ島で暮らした。伯母はどこかに移ることでまた、僕の病気がぶり返すことを恐れているようだった。
そして、ある朝、コーヒーを淹れながら、僕は言った。
「やっぱり、どこかの学校……できたら大学で学びたいと思う」
伯母はゆっくり微笑みが顔に広がるような笑い方で笑った。
「いいんじゃない?」
きっと彼女は僕がそう言い出すのを待っていたのだという気がした。
「あと」
次のことを言うのは、大学に通うことより勇気がいった。
「あなたの子供になりたい。親子になりたいんだ」
二十になった時、伯母が持つ僕の親権は終わっていた。
伯母は首を振った。
「ありがたいお話だけど、あなたのお父さんの篠井の苗字は残さないと。きっとそれを妹たちも望んでいると思うの。それにもう親子みたいなものじゃないの」
これだけは頑として、伯母は譲らなかった。だから、僕は伯母の養子にはなっていないけど、自分の親だと思っているし、そのように振る舞っている。これは逆に僕が譲らないことだ。
一人で日本に戻って、高卒認定試験を受けた。そして、アメリカの大学に通った。費用はもちろん、伯母が出してくれた。
伯母と僕の世界旅行はここで本当に終わった。彼女はまた、旅行に出た。二度と、一緒に暮らすことはなかった。彼女は相変わらず、一人で旅行を続け、時々、連絡を取り合った。
しかし、五年前、伯母が宣言した。
「私、日本に戻ろうと思う」
少し前から、伯母たち「永遠の旅人」への規制はさらに厳しくなっていた。そう簡単に税金をまったく払わずに生きていけなくなった。
「それもあるけど、そろそろ、旅にも飽きた。下駄履きで立ち食い蕎麦を食べられるような場所に住みたくなった。それにやってみたいことも見つかった」
僕はその頃、大学を卒業して、東京のIT関係企業に勤めていた。
伯母のやりたいこと、というのが「夜の図書館」だった。伯母は美術の勉強を通して、過去というものを保存することに、大きな意味を見出していた。
「ねえ、過去より今の方が進化しているなんて、あまりに思い上がりよ。工業や科学、化学なんかならともかく、美術芸術文学の上で、進化し続けているものなんてない」
彼女はその話を、アカデミア美術館のダビデ像の前でした。
「たぶん、これと同じものは、今は作れない。模写という意味ではなくてね」
「ふーん」
「だから、私は過去を封じ込めようと思う」
僕は「夜の図書館」の構想を聞き、すぐに言った。
「それ、僕にもやらせてくれない?」
伯母はうなずいた。やっぱり、徐々に笑みが顔の中央から端に広がっていくような笑い方で。
たぶん、僕がそう言い出すとわかっていたのだろう。
※ ※ ※
「お休み、どう過ごすか決まりましたか?」
乙葉は図書館が休館になって二回目の休日、『赤毛のアン』のドラマの後、尋ねた。 みなみがさっと正子と亜子の顔を見た。特に意識したわけではないと思うが、正子は伏し目がちになり、亜子は目をそらした。
「……私は親に来てもらおうと思ってるんですけど……」
乙葉は他の人のことにはあまり関心がなく、二人の様子を気にせずに続けた。正直言って、自分の話を聞いてもらいたくて始めた会話だった。
「あらっ。いいじゃない」
その言葉を聞いて、正子がすぐに顔を上げて言った。
「もう、お誘いしたの?」
乙葉は亜子が焼いてきてくれたピザに手を伸ばしながら、うなずいた。亜子は最近、集まる時はカレーやピザ、キッシュなど、若い女子が喜ぶようなものを必ず作ってきてくれるようになっていた。
「親たちも仕事しているので、土日にしか来られませんが」
「もう行くところ決めたの?」
「それが困ってるんですよねえ。行きたいところを言ってって頼んでるんですけど、どこでもいいって言うんです。そう言われてもね……上野動物園とか東京タワーとか六本木ヒルズとか、全部、ここから遠いじゃないですか。このあたりの山とか畑とか見たら、地元とあんまり違わないねって、また、がっかりさせそうで」
「……それはね、あなたと一緒なら、『どこでもいい』っていうことよ」
亜子がアイスティーを注いでくれながら笑った。これもまた、彼女が作ってきてくれたものだった。香り高くて、ほんの少し爽やかなミントの匂いがする。ここの小さなベランダで、ペパーミントを育てているらしい。
「親ってそういうものよ。どこか特別な場所に行きたいんじゃないの。あなたの顔を見て、話せればそれでいいのよ」
「いや、うちの親、そんなに甘くないんですよ! 就職のこととか、平気でずけずけ言うし、私のことなんてぜんぜん認めてくれてないし。今回もきっとお説教されるに決まってる」
乙葉は顔をしかめた。
「そんなことないわよ。寮の部屋を見て、図書館を見られればいいんじゃないかしら。どんなところで働いているのか、心配していらっしゃるんでしょ?」
正子も同意した。
乙葉の就職に伴う両親の反対などは、皆に一通り話してあった。
「そうですかあ?」
「そうよ、そうよ。部屋に泊めて、駅前の商店街で買い物でもして……できたら、図書館の中も見れるようにしてもらったらいいんじゃないかしらね?」
「あ。でも、休みだから」
「鍵をその日だけ貸してもらったら……?」
「そんなことできますか? きっと、休みの間、鍵は篠井さんが持ってますよね」
「篠井さん、ここから自転車でちょっとのところに住んでいるから、相談してみたら? 鍵を取りに行って、半日くらいで返しに行くって言えば、大丈夫よ、きっと」
「考えてみます」
乙葉は仕方ない、というようにうなずいて見せたが、亜子たちが言うことには一理あるかも、と思い始めていた。それに、そのコースならあまりお金もかからない。
「お部屋に泊まってもらうなら、うちの布団とかも貸すから言ってよ」
正子が申し出た。
「え、正子さんは大丈夫なんですか?」
「ええ。私はちょっと旅行に行くつもりだから」
「えー、いいですね。お一人ですか?」
みなみが声を上げたあと、ちょっと気まずそうな顔をする。どうということもない質問だが、正子のプライバシーに踏み込んでしまったことに気がついたのだろう。
「そうよ」
正子はみなみの心配を笑い飛ばすように、明るく答えた。
「温泉に行こうと思うの」
「温泉三昧ですかー。優雅ですね」
「そんな優雅じゃないの。山奥の小さな宿よ。部屋も四畳半くらいの和室で、布団とテレビくらいしかないところ。昔は湯治に使われていて共同の台所もあって、自炊もできるの。素泊まりなら一泊五千円以下なのよ」
「昔はそういうお宿、結構あったわよねえ」
亜子もうなずいた。
「でも、おさんどんするのも面倒だから、簡単な食事を付けてもらうつもり。ネットもスマホもほとんど通じないところなんだって」
「え。そんなとこに行って何をするんですか?」
乙葉は思わず、尋ねた。
「……それはもちろん、読書三昧よ。これまで読んでいなかった本をもちこんでまとめて読み尽くそうと思うの」
皆が「いいですねえ」「優雅だわねえ」「正子さんらしい」などと声を上げているのを、正子は微笑みながら見ていた。そして、そういう賞賛の声が止むと、小さくささやいた。
「そこで見極めようと思うの」
「え。何をですか?」
しかし、それ以上は答えなかった。
「ひみつ」
謎めいた微笑みだけが残った。
「亜子さんは?」
みなみが尋ねた。
「あたしはね、家を処分してこようと思うの」
「え」
乙葉とみなみが驚いて声を上げた。正子は声を出さなかったが、亜子の顔をまじまじと見つめた。
「ずっと、迷っていたんだ。田舎の家……というか店ね。小さな小さな書店をどうしようか。ネット書店が増えてからぜんぜん本が売れなくなって、もうずっと閉めていたけど、売ったり、中を整理する気になかなかならなくて」
「……いいの?」
正子が亜子の顔をのぞき込んだ。
「うん。決めた。何もない場所だし、小さくて古いけど、一応、駅前のロータリーのところだから売って欲しいという人が現れたの。コンビニにするんだって。金額も悪くないの。あたしが……」
亜子は一度、唇を舐めた。
「売ったお金を家族で分けても、ちょっとした老後の蓄えにはなる程度だけどね」
「ご家族も賛成しているんですか?」
亜子の家族について一度も聞いたことがなかった、と乙葉は気がついた。
「どうだろ? わからない。というか、むしろ、その店をどうしたいとか、きっと何も考えてないの。ただ、決めているのはあそこにもう戻って来ないということだけ。だからいいの。むしろ、そうしてあげたらきっと喜ぶ」
主語がわからない話をしていた。だけど、それを聞き返すこともできなかった。
「亜子さんがいいならいいんですけど……」
「売ってお金を振り込んであげたら、きっと彼女のためになる。今はその口座くらいしか、あの子とつながっているところはないしね」
自分に言い聞かせるような口調だった。
「あの子? ですか?」
そこまで聞いて知らん顔はできなくなって、乙葉は尋ねた。
「うん。娘」
「お嬢さん、いたんですか」
「うん。今、たぶん、関西の方で働いてる。はず。もしかしたら結婚もしているかもね。そうだったら嬉しい。いえ、結婚していてほしいと言うんじゃなくて、だれか、そういう一緒にいてくれる人がいて幸せでいてくれたら嬉しい」
亜子は自分で自分の言葉にうなずいた。
「大丈夫ですか、亜子さん?」
みなみが心配そうに問う。
「大丈夫。娘とあたしがね、うまくいかなくなったのはあたしが悪いの。全部、あたしが悪いの。あの子に期待をかけ過ぎてしまった。主人は娘が小さい時に死んで、それからああしてほしい、こうしてほしいって言い過ぎた。ずっと近くにいてほしい、高校も大学も近くでね、就職もうちの店を継いで、できたらお婿さんをもらって……そんなに強く言っているつもりはなかったの。願望をなんとなく話しているだけのつもりだった。だけど、娘には重荷になっていたみたい。あの子はあたしの言葉でがんじがらめになって、気がついたら、大学は東京に行く、って言って家を出ていってしまった。それから会ってない。従姉妹とは連絡が取れていて、生きてることだけはわかってる。だけどあたしとは話したくないんだって」
「そういうことだったんですか」
「銀行口座はね、うちを手伝ってもらう時、アルバイト料を振り込んであげるね。貯めておいて、結婚する時、結婚資金にしなさいねって言って作ってあげたから、番号はわかっているの。あそこに振り込むことが今はあの子とあたしの唯一のつながり」
皆、黙ってしまった。
「……いいんだ。ここで、仕事をまだ続けられて、あたしとてもありがたいの。そしたら、決心がついた。あの店を売って、娘を解放してあげようって」
本当だろうか、と乙葉は思う。
もちろん、本心だろうけど、本当は少しだけ期待しているのではないか。大金を振り込んだら、娘さんから連絡がくること。
いや、そうなってほしいとも思ったし、そういうわずかな望みを繫いでいる亜子が気の毒にもなった。一方で、親子のことは、彼らにしかわからない、とも。自分たちとはうまくやっている亜子が、娘にとっては一緒にいるのも嫌な人なのかもしれない。
人はそれぞれ相手によって顔を変える。
「……あたし、言うかどうか迷っていたんですけど」
みなみがおそるおそるという感じに声を出した。
「実は、皆には言わないでおこうと思っていたんですけど」
「何?」正子が尋ねる。「衝撃の告白?」
重たい雰囲気を和ませようとしているのか、わざと大袈裟な言葉を使ったみたいだった。
「違いますよ……というか、ちょっとそうかも。この休みに……ちょっと東京で面接を受けて来ようかと思っています……」
みなみの声はだんだんに小さくなった。
「えー。面接って就職の面接ですか」
乙葉が尋ねる。
「そう。黙っていようと思ってたんだけど」
みなみは亜子の方を見る。
「亜子さんが衝撃の告白するから、なんか、言いたくなっちゃった」
「あら。あたしのせい?」
亜子はいつものどこかのんびりした調子に戻っていた。
「どうしてですか! みなみさん、いつも楽しそうにしてたのに」
乙葉は驚きすぎて声がどうしても大きくなってしまう。
「……ここの仕事に不満があるわけじゃないの。むしろ、逆。楽しいし、皆、いい人だし……でも、あたし、本当はそんなに本が好きじゃないかもしれない、と思って。皆さんみたいに、本とか小説とかに情熱を向けられないの。だったら、この仕事は他の人に譲った方がいいかと思って」
「そんなあ」
「書籍や小説を愛している人だけが図書館員じゃなくてもいいと思いますよ」
正子が静かに言った。
「むしろ、そのあたりのことを冷静に判断できる人も図書館には必要ですよ」
「ありがとうございます」
みなみは軽くお辞儀をした。
「だけど、他の職場……普通の会社員? オフィスの仕事も一度はやってみたいと思ったんです。大学を卒業してから、図書館で働いて、いつもちょっと古い本ばかりを相手にしてきて。なんだか、本というものをもう少し、外から見てみたくなった」
「なるほど」
乙葉にとってはものすごくショックな話だし、みなみがいなくなったら同じ年頃の人がいなくなってしまうのも不安だった。だけど、応援してあげたいとも思った。
「まだ、わかんないよ。だって、どこも落ちるかもしれないし。っていうか、その可能性の方が高いし。面接受けてみて、やっぱり、こっちの方がいいってなるかもしれないし」
みなみはそう続けたが、乙葉にはもう彼女が気持ちをほぼ決めているように見えた。
その日、部屋に戻って気がついた。
小田早穂のことやスズキミツコのことを話し忘れたことに。
※ ※ ※
伯母の資産がどこから生み出されたのか、気になる人もいるだろう。
彼女は若い頃、イタリアのボローニャで美術の勉強をしていたのだが、大学に入る前、一時期、地元の語学学校に通っていた。そこにはさまざまな国から来た人たちがいて、中にアラブから来た集団がいた。
彼らは王の親族と噂される男と、その取り巻き兼ボディーガードたちだった。いつも五、六人でまとまって行動していた。
彼らはとても横暴で、我が物顔に徒党を組んで語学学校内を歩いていた。特にその王の親族である一番のボスは皆に忌み嫌われていた。クラスの中を見回しながら「こいつら全員が一生のうちに稼ぐ金より、自分が一年に使う金の方が多いだろうな」とか、「イタリア語を勉強して、イタリア女を四番目の妻にして連れて帰るんだ」などと言うから、先生にも嫌われて、彼の少しつっかえるような発音をわざと何度も何度もやり直させられたりしていた。
しかし、伯母はある日、その中の一人が学食で困っているのを見て、助けてあげた。
「確か、クレジットカードの不具合で支払いができなかったから、現金を貸してあげたの。嫌われていたから、彼が困っているのを見ても、皆、知らん顔して助けてあげなかったのよね」
彼はその集団の中では一番若く、一番おとなしそうだ、と伯母は前から気がついていた。クラスで白眼視されている時、彼だけがどこか悲しそうな顔をしていることにも。
彼はお礼に、伯母を食事に連れて行ってくれた。もちろん、他の取り巻きたちはなしで。彼はイタリア語は下手だったが、きれいな英語を話した。子供の頃はイギリスの学校に留学していた、と語った。彼は王族の警護の合間に伯母を誘った。数ヶ月の語学学校のカリキュラムのうちに、伯母とその人は付き合うようになった。
伯母は当時、日本の大学を出た後、何年か普通のOLをし、そのあと留学に来ていたから、すでに三十だった。彼の方はまだ母国の大学を卒業したばかりでずっと年下だった。
「日本人は若く見えるから、まったく気がつかなかったみたい」
語学学校の修了日、彼は伯母にプロポーズした。そして、驚いたことに、王の親族はあの威張っている嫌な男ではなく、彼自身だということも告白した。この留学は大学を卒業したお祝いの旅の一環で、母国に帰れば、政府で重い役割を担うと決まっていることも。
「驚きだよね。警備上の理由でずっと警備員の振りをしていたんだって。あと、王の親族だとわかると人の態度が変わるから、そういうことを抜きにしていろいろな人とふれあいたかったらしい。仕事が始まれば、もうほとんど国外には出られないって決まっていたし」
彼のことは嫌いではなかったが、伯母は断った。伯母にはこれからイタリアの大学に通うという目的があったし、彼の二番目の妻(彼はすでに既婚者で一人目の妻は幼い頃からの許嫁だった)になるのも嫌だった。さらに、彼の取り巻きが、国に伯母のことを報告したところ、彼の親からも大反対された。まあ、かなり年上の日本人を連れて帰るとなったら、普通は反対されるだろう。
彼は悲しんだが、仕方がなかった。彼は母国に帰り、伯母はイタリアに残った。
その後も、海外にはもうほとんど行けなくなった彼に代わって、伯母は何度か彼に会いに行った。そのたびに、彼は伯母に「お手当」を出した。まるで通いの愛人のようで気が進まなかったが、彼にとってはほんのはした金だし、他にあげるものもない、と悲しそうな顔で言われると、受け取るしかなかった。彼は自分からプロポーズしたのに、自分の両親が伯母を拒否したことをとても申し訳なく思い、責任を感じていたらしい。
そうして通ううちに、彼の妻は一人二人と増えた。それもまた、彼らの世界では、政略として仕方のないことらしかった。それが本当に必要なことなのか、ただ単に彼が女好きなだけなのかは伯母にはわからなかった。でも、彼は妻が増えるたびに、伯母に大金を渡した。
彼の妻が三人になった時、彼はもう一度、伯母にプロポーズした。彼は三十に、伯母はそろそろ四十に手が届きそうになっていた。今、結婚しなければ、これ以上、妻は持てないし、これが結婚の最後のチャンスだと言われた。彼はすでに八人の子供がいる、一家の長になっていた。
「まあ、そんなところにのこのこ入る気もないし、妻になったらたぶん、あの国から出ることはできなくなるし」
宗教の問題もあった。結婚するなら改宗し、頭の先から足まで覆うブルカを着て、彼が用意した家に閉じこもることになる。ほとんど知り合いのいない国で。伯母は決してイスラム教を否定するわけではないが、どのような形でも神がいるとは思えない、無神論者の一人だった。
伯母は再度、彼のプロポーズを断った。
彼が最後に四人目の妻を迎える時、また多額の金を伯母に渡した。伯母は一生遊んで暮らせるほどの金を手に入れた。また、母国で金融関係の要職についていた彼は投資にも明るく、伯母に「永遠の旅人」の知恵と、いくつかの投資を教えた。
その頃と前後して、伯母と彼の男女としての関係も終わったようだ。
彼はさらに出世して政府の大臣の一人となり、一族の長となり、多忙を極めた。東洋から来たわけのわからない女と気軽に会うようなこともだんだんできなくなっていた。
伯母も世界を転々とする生活が身についてきていた。彼と伯母はもう十年以上、直接は会っていないはずだ。
彼は今でも伯母を自分のアドバイザーとして雇い、時々、スカイプを使って話している。それだけで、たぶん、かなりの金が支払われているはずだ。さらに、この夜の図書館に、支援者として関わっている。
彼は今でも伯母を愛しているし、精神的支柱として頼りに思っているのだろうと思う。
夜の図書館で盗難が頻発し、おかしな人間が現れた時、伯母を心配して黒岩さんをよこしたのは彼だ。日本のセキュリティー会社に依頼して、元警官の適任者を探してもらったらしい。あの弁護士の砂川を伯母に付けているのも彼だ。
伯母も歳を取った。
僕と知り合った頃と少し変わったな、と思うのは彼女が偏屈になり、人との関わりをほとんど絶つようになったことだ。もともとそういう気質のある人だったが、歳を取って顕著になった。
僕とくらいしか直接、人とは話さない。
スカイプなどを使って図書館員候補者たちの面接をしたあとなどは、数日寝込んでいる。
「他人と話すととても疲れる」と彼女は言う。「生の感情や言葉は悪いものではないが、それを浴びるのはつらい」
ただ単に、伯母は気を遣いすぎなのだというのが僕の見立てだ。
彼らと話したあと、しばらくぶつぶつと独り言を言っている。あの時こう言えばよかった、ああ反応すればよかった、あんな返事をして傷つけてしまったのではないか……そういう後悔を口に出している。
そこから立ち直るには何日かよく寝て、記憶が薄れていくのを待つしかない。
でも、図書館に関して表舞台には立たず、そこや寮を掃除する生活には十分満足しているようだ。館員の誰とも話さないが、彼らのことを一番知っているのは自分だ、と時々自慢する。
「その人の読んでいる本について話せばどういう人かなんてわかる」
「そうかな?」
僕にはよくわからない。
「あとはその人の本棚を見ることね。本棚にはその人の願望が詰まっている。どんな人間になりたいか、ということがそこでわかる」
実は、彼女はあの寮であるアパートのマスターキーを持っている。まあ、掃除をしているし、あそこの実質的な大家であるのだからしかたないけど、彼女は時々、彼らの部屋に入って、本棚を見ているらしい。
「何もしてないのよ。ただ、本棚をチェックするだけ」
伯母がどんどん自分の殻に閉じこもり、偏屈になっていくことが心配だ。それはこれから気をつけていかなければならない。
もしかしたら、伯母は自分が思っている以上にあの人を愛していて、彼とは一緒になれない運命や当時の判断への後悔が、自身を苛んでいるのかもしれない。
まあ、それを尋ねてもたぶん、否定すると思うけど。
ここを夜の図書館にしているのは、他でもない。
最初の頃、なぜ、夜しかやらないのかと尋ねると、「昼間は日の光で貴重な本が傷むから」「あの人の国と日本の時差は六時間。あの人からの連絡は夜来るから、夜行動した方がいいの」とか言っていたけど、本当は昼間の時間は自分が使っているからだ。
昼間、彼女はこの図書館の真実の主人となる。ただただ、この本と言葉の海に浸って、読書を続けている。
この図書館に私財を投げ打っている以上、そのくらいの贅沢は許されると僕は思う。
図書館の玄関の蛾の標本は、彼から贈られたものだ。彼はさまざまな大学や財団に寄付をしているが、昆虫の研究もそれに含まれていて、新種の蛾に名前をつけないかと誘われたのだ。
伯母の名は鈴木三石子という。三つの石の子、と書いてみつこと読む。
※ ※ ※
蔵書整理は休暇が始まる二日前くらいにほぼ終わった。幸い、紛失している本はなく、蔵書印が押してないもの(二宮公子が置いていったと思われるもの)だけ、二冊見つかった。
最後の一日は、掃除をしたり休暇明けにお客様を迎えるための各自の準備をしたりすることになった。
乙葉と正子、亜子たち、蔵書整理係は白川忠介と高城柚希の蔵書を会議室から蔵書整理室に移した。休み明けはこの仕事から始まることになっていた。手の空いている他の人たちも手伝ってくれた。
「食堂に木下さん、来てるよ」
台車で本を運んでいる途中で、みなみに耳打ちされた。
「そうなの⁉」
「夜食作ってくれるんだって」
なんだか、急に元気が出てきた。
本を運び終わったあと、正子たちに断っていそいそと食堂に向かうと、本当に店に明かりが灯っていて、木下がカウンターの中で働いていた。
「木下さん、お久しぶりです!」
「ああ」
彼は短く答える。照れているのか、面倒くさいのか、小さくうなずいただけだった。
「何か、食べられるんですか」
「うん。そこに座って待っていて」
みなみや徳田とおしゃべりしていると、木下がエプロンを着けたまま近づいてきた。「本当は来る気なかったんだけどさ、今日、蔵書整理の最後の日だなって思ったら、なんか、食べさせてやりたいなって思っちゃって」
「ありがたいです!」
乙葉は深く頭を下げて礼を言った。
「それで、何がいただけるんですか」
「気がついたのが夜だし、なんにもないんだけど、ここに買い置きしてある缶詰とかでできるものでいいかな」
「もちろん」
「さっき慌てて炊飯器のスイッチを入れたからね。炊けるまであと少しかかる。十分くらいかな」
「木下さん、他に何人分くらいできるんですか」
「ご飯はたっぷり炊いたし、缶詰は結構あるから、食べたい人はいくらでも」
「じゃあ、他の人とかも呼んできていい?」
「ああ、いいよ。あと、地ビールも買い置きがあるから、皆で打ち上げでもやったらどうだい」
「やった!」
乙葉とみなみは走って一階に降りていき、篠井や正子たちに声をかけた。もちろん、受付の北里にも。
「あたしもいいんですか?」
「今まであそこではほとんどご飯を食べたことはないんだけど……」
亜子たちは少し申し訳なさそうだったが、嬉しそうだった。
乙葉とみなみが食堂に戻ると、すでに料理ができて、テーブルに並んでいた。
「本当に、ただ、あり合わせの缶詰で作ったもんだからね。期待しすぎないでね」
それは丼で、ご飯の上に小さめの魚が四、五匹並んで、ネギが散らされているものだった。それと椀に入った汁が置いてあった。
「……これはなんですか?」
「まず、食べてみて」
乙葉は丼を手に取った。小さな魚とご飯を一緒に口に入れる。
「……木下さん、おいしいです。なんだかわからないし、見た目やけにシンプルなのに、めちゃくちゃおいしい」
「それは、オイルサーディンの缶詰をフライパンで温めて、醤油をじゅっと垂らして、ご飯に油ごとかけたやつ。それだけ。ネギはここに来る途中、コンビニで買ってきた、というか、開いているのはコンビニくらいしかなかったから。結構、いけるだろ」
「はい。ご飯、もりもり食べられます」
「森瑤子のエッセイの中にあった料理だよ。汁は乾燥ワカメと卵のかき玉汁」
乙葉たちが食べていると、その日、図書館に登館している人たちが全員集まった。
木下は皆に、どのくらいお腹が空いているかや好き嫌いなどを尋ね、順番にオイルサーディン丼を出していった。そして、全員に渡ると、地ビールの小瓶も用意してくれた。
「ちょっとした打ち上げになったね」
みなみが乙葉にささやく。
「そうですね……みなみさん……」
「ん?」
地ビールの瓶に直接口をつけて飲んでいたみなみがこちらを見た。皆、木下の洗い物が少しでも減らせるように、瓶のままラッパ飲みしていた。
「やめるなんて言わないでください、さびしいです」
あたりには聞こえないくらいの声で言った。
「こういうの、楽しいじゃないですか。たぶん、他の会社ではできませんよ」
「……まあ、いろんなところを見て、ちょっと考えてみるよ」
考えてみる、という言葉にすべてが込められている気がした。
きっとみなみはこの一週間で、面接をしたり見学をしたりしながら本当に、ちょっと考えるんだろう。その答えがどのようなものであっても、乙葉たちには止められないし、否定はできない。
少し離れたところで正子と亜子が二人並んで食事をしていて、その二人に木下が話しかけている。めずらしいスリーショットだが、今夜は他にもそういうのがあって、徳田は篠井に何か熱心に話しているし、渡海と北里も微笑み合っている。二人は恋人同士に見えるほどお似合いだったが、だからと言って、別に付き合っているわけでもないだろう。でも、将来、そうなってもいいとも思う。
ここにいる人たちが、どんな選択をしようともいいのだ。
なんというか、そういう雰囲気全部が貴重で、とてもいい時間で、でも、きっとこれは永遠ではない。
永遠でないからこそ、こんなに美しいのだと乙葉は思った。