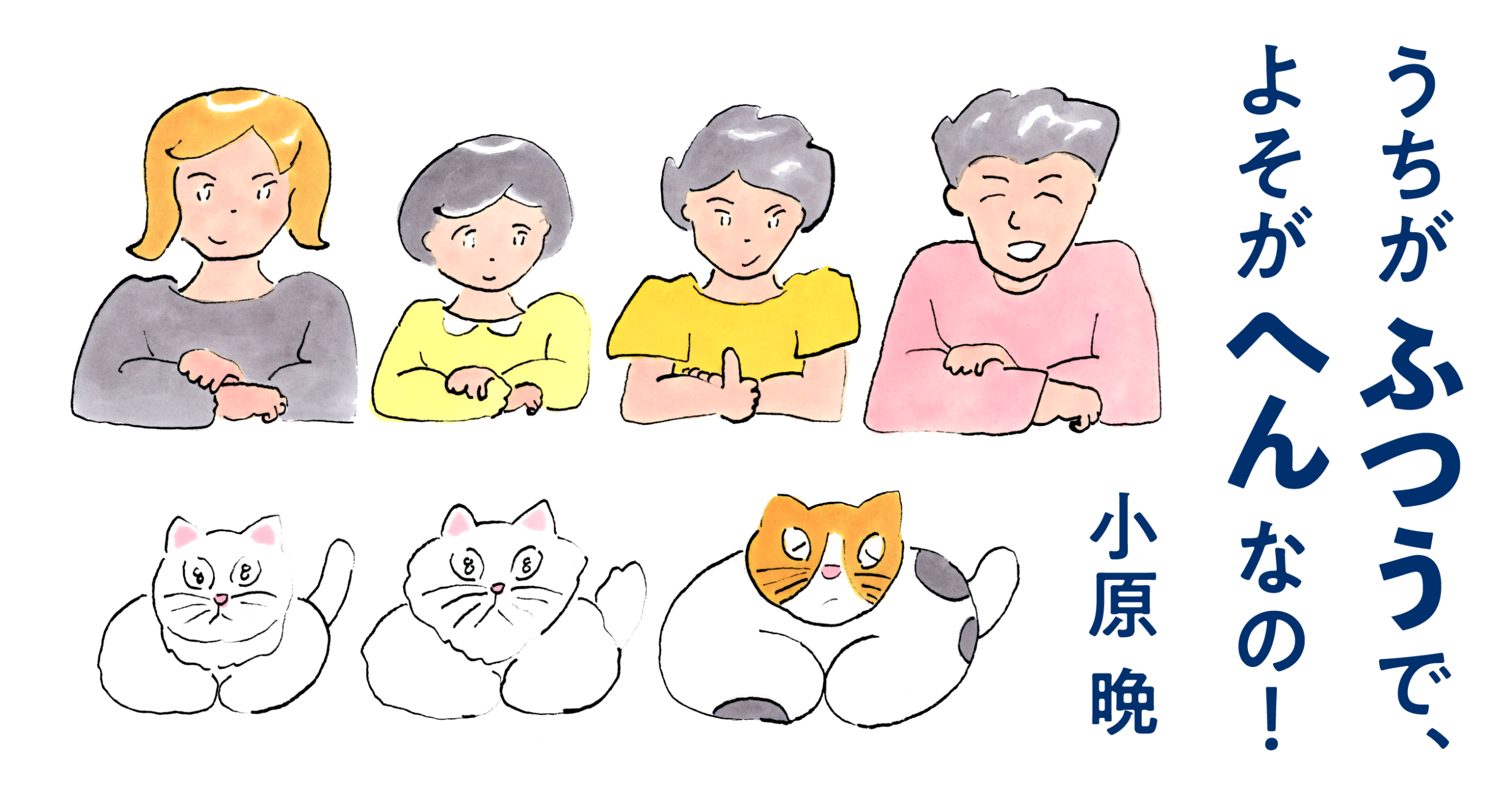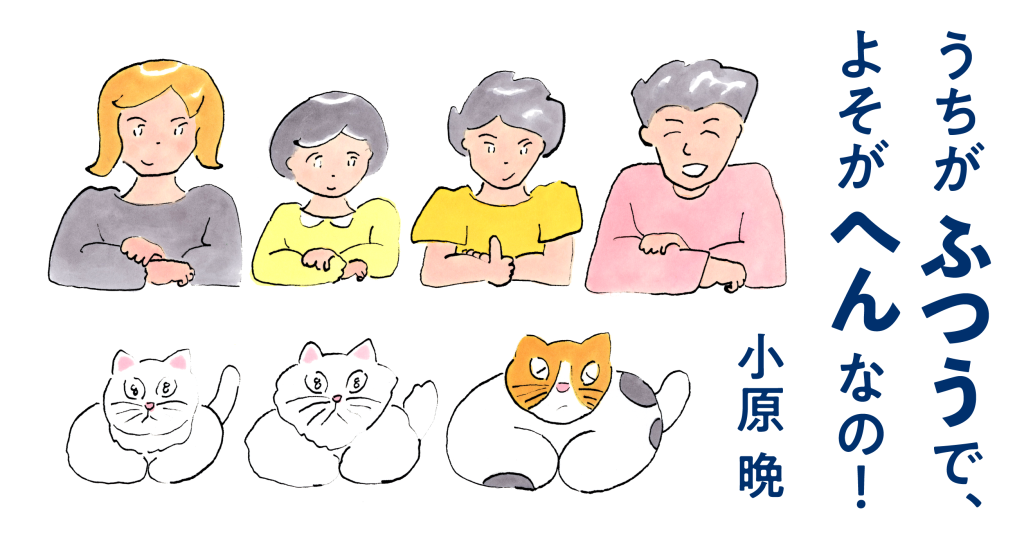
「明日はまつりに行こう」と、土曜の夜に父が言った。
なんだか、へんな気がした。
父はひとの多いところをとことんきらう人で、小原家はこれまで、ひとの集まる場所へは、ほとんど出かけたことがないのである。それが、まつりに行くという。
おまつり。夏まつり。真っ青のかき氷。白くてふわふわの甘いやつ。鉄板の上でおどるたこ焼。瓶のラムネ。浮き立つ気配。人いきれ。水に浮かぶ小さなヨーヨー。すくわれてゆく金魚たち。瞳をうばわれた無数の仮面。
私は、きらきらした気持ちになった。
なにか、いつもの暮しとちがうものが、いま、自分のほうへやってくるように思えた。
翌日、家族でほんとうにまつりへ出かけた。
私は、これはきっと、目が覚めたらなかったことになっているのだろうと、半ば信じていたのである。けれど、嘘ではなかった。まったく、これはおどろくべきことであった。
すぐにでも踊りだしたいような心もちで、しかし踊るのは恥ずかしく、鼻の奥でふんふんと息を鳴らし、めをみひらいて、はじめての夏まつりを見た。
人の波。日の照る下、歩けないほどの混雑。
どこまでもつづく、屋台屋台屋台。
これこそ、夏まつり!
幼いわたしのめに、きらきらと、光っていた。
父を見た。なんとなく、あやしい感じがあった。
屋台の並ぶ大通りから、ふいに、横道へそれた。
なんだ、なんなんだ。
父は階段を降りて、地下へ入っていった。
なんだろう。
ついていった。こどもには、親についていく、という選択肢しかないから。
ジャズバーだった。
見たことのないおじさんたちが楽器をひいてた。店内は涼しく、うす暗く、さきほどまでの蒸されるような夏の熱気はうそのようだった。
お父さんはさっそくお酒を頼んだ。ほどなく赤ら顔になった。お母さんはお酒につよいので、赤くはならなかった。わたしはオレンジジュースをもらった。背の高いグラスのふちにオレンジが刺さっていた。
ジャズが、流れていた。生音のジャズが。
あたまのうしろのほうで、ずっと、鳴っていた。
盆踊りがよかったのだ。瓶のラムネがよかったのだ。かき氷のシロップを何味にするかで迷いたかったのだ。ふわふわのわたあめにかぶりつきたかったのだ。金魚を飼いたかったのだ。ヨーヨーをぼよんぼよんとしながら歩きたかったのだ。あわよくば、人混みの夏まつりで、肩車してほしかったのだ。
わたしはふてくされた。ほんとうにいやだった。
父は音に揺れて、上機嫌だった。
母は、どうだったろう。
上機嫌の父がわたしの顔を見つけて、ひとこと、小さく、何か、怒鳴った。それから父も不機嫌になり、われわれは店をでた。
こんなことになるなら、はじめからジャズをたのしめばよかったと思った。
実のところ、かっこうよかったのだ、ジャズ。夏まつりへ行く、と言われたから、裏切られたような気がしただけで、オレンジジュースだっていつも飲んでいるものよりよっぽど、うまかったのだ。
それでも、それでも。わかってほしかったのである。
父のための日ではなく、夫婦のための日ではなく、わたしのための日がほしかったのだ。
小原晩(おばらばん)
作家。1996年、東京生まれ。2022年にエッセイ集『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を自費出版する。2024年11月に実業之日本社より増補版を刊行。他の著書に『これが生活なのかしらん』(大和書房)がある。