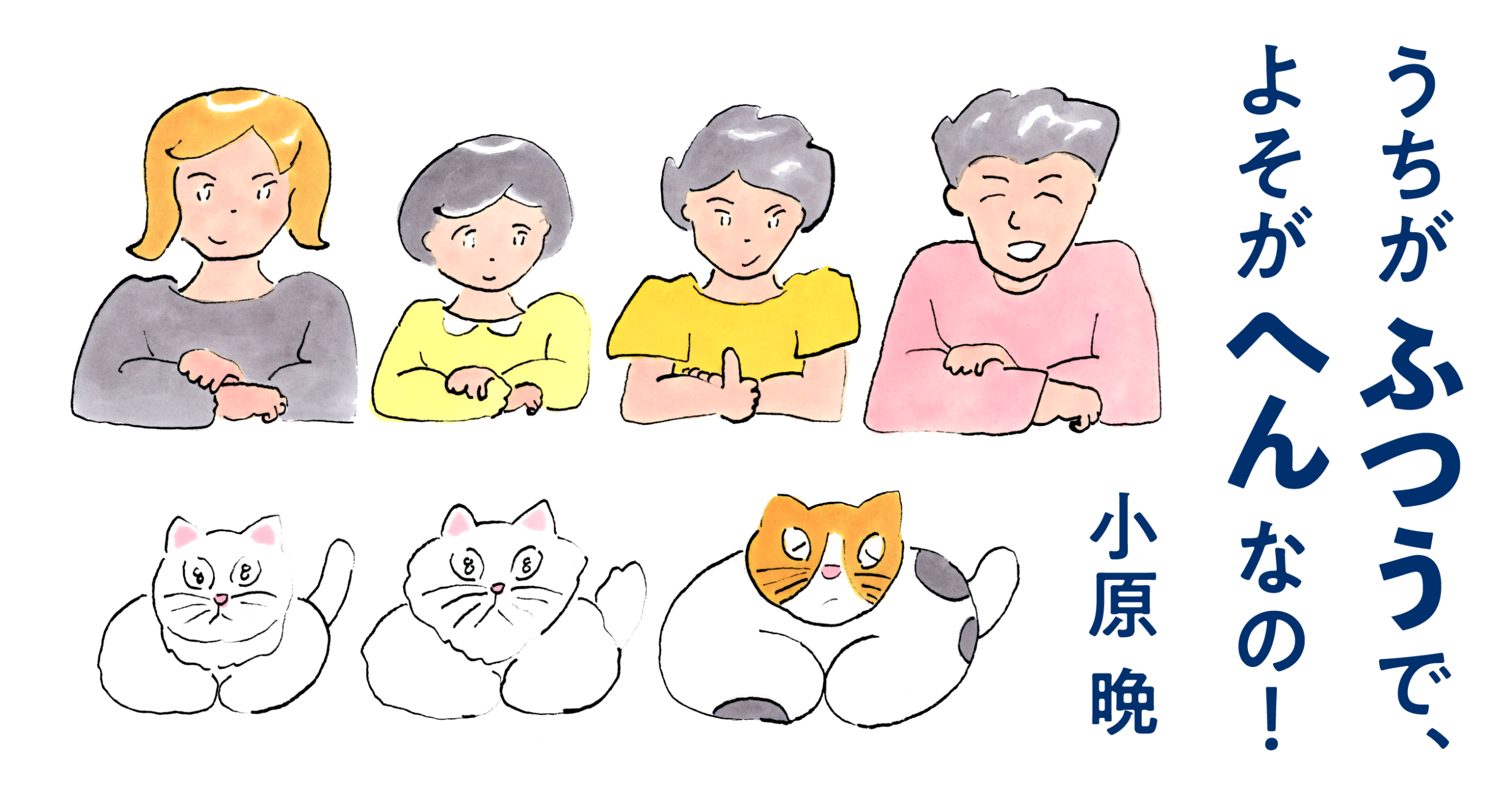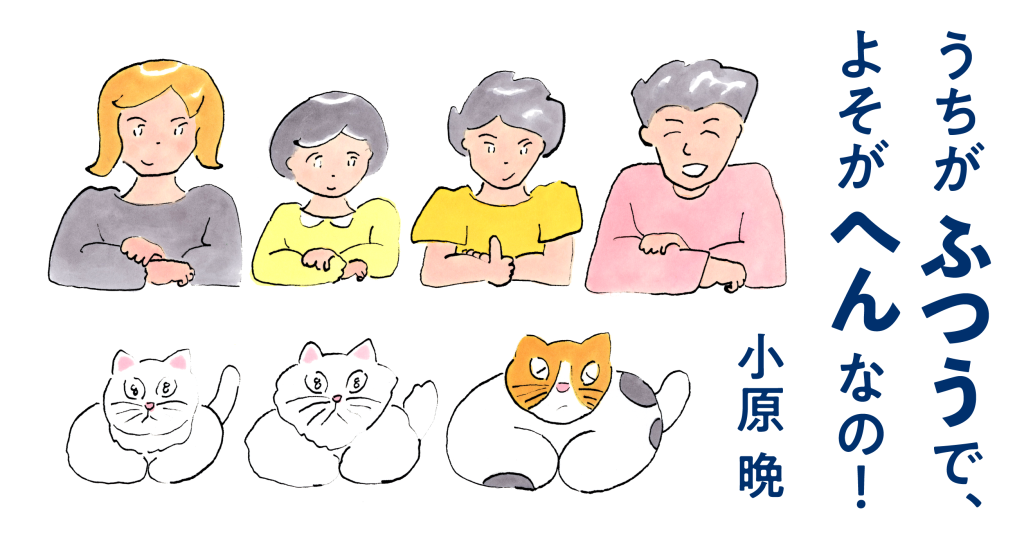
ふすま一枚隔てた向こうが、兄の部屋だった。
広さは変わらないけれど、畳敷きで、いつもお香のあまったるい匂いがした。小さな部屋で長いお香を焚くものだから、入るたび、目がしぱしぱした。
朝になると、兄は大音量で音楽をかけた。KREVAとか、ケツメイシとか、リップスライムとか、SOUL’d OUTとか、ヒルクライムとか。そういう音楽が好きなようだった。
なぜか兄のほうがわたしより早起きで、わたしはたいてい、その大音量に起こされた。うるさーい! と叫んでも、音にまぎれて届かない。やるときゃ、とことんやる男なのである。音楽を流すとなれば、大音量に決まっているのである。
一方で、わたしはお笑いが好きだった。夜になると、お笑い番組をずっと見た。わたしの部屋に、わたし専用のテレビを買ってくれた両親には感謝している。あれは、ほんとうにありがたかった。わたしは、じぶんの部屋で、よくわらった。引き笑いだった。ヒッヒッ! ヒーッ! ヒッヒッヒッヒッ! ヒーーーーッ!
夕食の時間になって、白米をちいさく一口食べたあと、兄は言った。
「おまえ笑い方きもちわりぃんだよ」
「えっ」
ショックだった。
たのしく、わらっていただけなのに。
改善を試みた。引き笑いがいけないのだ、と単純に考えた。
ハッハッハッハハハハハハハ! ハハッ!
吸うのではなく、吐く。そこを意識した。
どうだ、聞こえているかお兄ちゃん。わたしの笑い声。なおしたよ。
また夕食の時間となって、兄は、麦茶をひとくち飲んで、それからほっけをほぐして口にはこび、白米をひとくち食べて、よく噛んでから、麦茶を飲んで、言った。
「おまえさ、いい加減にしろよ」
「えっ、なおしたよ」
「もっときもちわりぃわ」
ショックだった。
「おまえそういう演技みたいだよ、ハハハじゃねんだよ」
「おふくろ、こいつ、笑い方まじきめぇよ、どうにかしたほうがいいよ」
「オヤジ、わかるだろ」
家族でかばうひとは、だれもいなかった。お父さんもお母さんも、兄の言葉なんて聞こえていないみたいに集中して、ほっけの身をほぐしていた。やさしさだった。答えだった。
それからも改善を試みた。
ヒッヒッ、でもなく、ハハー、でもなく、そのあいだ。
どうやら、ヒャーーーッ、になっていたらしい。ふすまに、テニスボールを投げられた。ふざけているわけじゃなかった。
そうこうしているうちに、兄は、茶髪になり、制服を着崩し、眉毛を細くし、煙草を吸い、学校に行かなくなり、家に帰らなくなった。家に帰ってこないのだから、どんなふうに笑ってみても、わたしの笑い声は届かない。いまも、わたしはよく笑う。高らかに、高らかに。聞こえているか、お兄ちゃん。
小原晩(おばらばん)
作家。1996年、東京生まれ。2022年にエッセイ集『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を自費出版する。2024年11月に実業之日本社より増補版を刊行。他の著書に『これが生活なのかしらん』(大和書房)がある。